

昭和名曲の誕生秘話を堪能できる特別番組のご紹介
5月14日(水)夜8時から放送されるBS日テレの特別番組「そのとき、歌は流れた」では、昭和の名曲たちの裏に隠された感動のストーリーが掘り下げられます。今回、番組では小柳ルミ子さんと川中美幸さんが特集されます。
小柳ルミ子が歌う『瀬戸の花嫁』は、今も多くの人々に愛され続ける名曲です。この曲の誕生にまつわる秘話は、非常に興味深いものです。通常、楽曲は作曲家が先に音楽を作り、その後に作詞家が歌詞を作りますが、この曲では作詞家・山上路夫と作曲家・平尾昌晃が別々に作品を作成しました。そのため、曲と歌詞が初めて合わせた瞬間、ルミ子さんは「背中に電流が走った」と語っています。このような奇跡的な感覚こそが、名曲『瀬戸の花嫁』の魅力の一つですね。
川中美幸さんもまた、名曲揃いの世界で注目されるアーティストです。彼女のデビューから52年、最も思い入れのある楽曲として挙げるのが『遣らずの雨』です。この曲と初めて出会ったとき、美幸さんの背中にも鳥肌が立ったといいます。その感覚は、まさに歌の魔法の一端です。関係者からは「演歌ではない」と驚かれたこともあり、バラード風の表現が好ましいという彼女のスタイルが際立っています。
また、彼女が特に思い出深いのは、160万枚の大ヒットを記録した『ふたり酒』です。この曲の歌詞には、両親への感謝とともに「生きていくのがつらい」という感情が込められています。美幸さんは24歳でこの曲に出会ったとき、曲を聴いた母が電話口で涙を流したことがきっかけで、この歌が売れると確信したのです。
番組ではさらに、母の日特集としても昭和の名曲が披露されます。田川寿美の『おかあさん』や、三善英史の『円山・花町・母の町』、萩原健一の『前略おふくろ』、山口百恵の『秋桜』など、母への思いを込めた名曲が登場し、視聴者の胸を熱くさせるでしょう。
この特別番組は、昭和の時代を彩った名曲を通じて、日本人の琴線に触れる機会を提供します。レコードの普及前の世代も、懐かしい思い出に浸りながら、時代を超えた歌の力を再確認できることでしょう。名曲は、歌詞一つで彩られた思いが、時に時代を超えて心に響くのです。
「そのとき、歌は流れた」という番組を通じて、昭和の名曲たちが持つ特別な意味を探求し、皆さんとともに楽しむ機会となることを願っています。ぜひご覧ください!





小柳ルミ子の名曲『瀬戸の花嫁』誕生秘話
小柳ルミ子が歌う『瀬戸の花嫁』は、今も多くの人々に愛され続ける名曲です。この曲の誕生にまつわる秘話は、非常に興味深いものです。通常、楽曲は作曲家が先に音楽を作り、その後に作詞家が歌詞を作りますが、この曲では作詞家・山上路夫と作曲家・平尾昌晃が別々に作品を作成しました。そのため、曲と歌詞が初めて合わせた瞬間、ルミ子さんは「背中に電流が走った」と語っています。このような奇跡的な感覚こそが、名曲『瀬戸の花嫁』の魅力の一つですね。
川中美幸と『ふたり酒』に込めた思い
川中美幸さんもまた、名曲揃いの世界で注目されるアーティストです。彼女のデビューから52年、最も思い入れのある楽曲として挙げるのが『遣らずの雨』です。この曲と初めて出会ったとき、美幸さんの背中にも鳥肌が立ったといいます。その感覚は、まさに歌の魔法の一端です。関係者からは「演歌ではない」と驚かれたこともあり、バラード風の表現が好ましいという彼女のスタイルが際立っています。
また、彼女が特に思い出深いのは、160万枚の大ヒットを記録した『ふたり酒』です。この曲の歌詞には、両親への感謝とともに「生きていくのがつらい」という感情が込められています。美幸さんは24歳でこの曲に出会ったとき、曲を聴いた母が電話口で涙を流したことがきっかけで、この歌が売れると確信したのです。
母の日特集での昭和の名曲たち
番組ではさらに、母の日特集としても昭和の名曲が披露されます。田川寿美の『おかあさん』や、三善英史の『円山・花町・母の町』、萩原健一の『前略おふくろ』、山口百恵の『秋桜』など、母への思いを込めた名曲が登場し、視聴者の胸を熱くさせるでしょう。
番組の魅力
この特別番組は、昭和の時代を彩った名曲を通じて、日本人の琴線に触れる機会を提供します。レコードの普及前の世代も、懐かしい思い出に浸りながら、時代を超えた歌の力を再確認できることでしょう。名曲は、歌詞一つで彩られた思いが、時に時代を超えて心に響くのです。
「そのとき、歌は流れた」という番組を通じて、昭和の名曲たちが持つ特別な意味を探求し、皆さんとともに楽しむ機会となることを願っています。ぜひご覧ください!





トピックス(音楽)

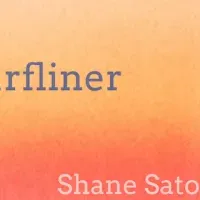
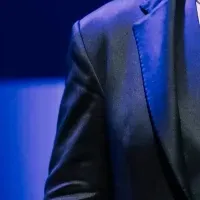


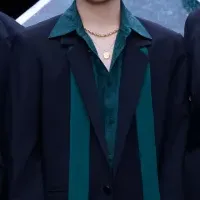

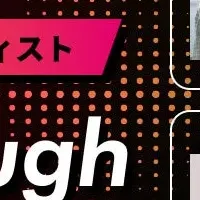


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。