

京大・埼大・富大とBIPROGYが流体装置開発で新たな挑戦
流体装置の進化を切り開く共同研究
京都大学、埼玉大学、富山大学、ダイキン工業、そしてBIPROGYが一堂に会し、革新的な共同研究プロジェクトを立ち上げました。この取り組みは、流体エネルギーの効率的利用と製造コストの低減を目指し、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が提供する「研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)」に採択されたもので、2025年度から本格的にスタートします。
プロジェクトの概要
共同研究テーマは「産業流体装置開発を加速する流線トポロジカルデータ解析ソリューション」です。これは、数理科学を駆使した新しい流体解析手法を用いて、ダイキン工業の空調用圧縮機の開発プロセスを加速することを目的としています。具体的には、内部の流れのスケルトン構造を高速で抽出して可視化できるアルゴリズムとソフトウェアの開発に取り組みます。
この解析により、空調機械の開発現場での流体シミュレーションデータの解釈が容易になり、設計段階からの無駄を省くことで、製造コストを削減し、新しい省エネ製品の開発が期待されています。さらに、他の産業流体装置の開発への応用も視野に入れています。
流体装置の重要性
流体装置は製造、医療、環境など多岐にわたる分野で重要な役割を担っています。一般的に、流体装置の開発にはコンピュータを用いた流体シミュレーションが必須となっており、それを行うCFD(Computational Fluid Dynamics)という解析ソフトウェアが広く利用されています。しかし、CFDのデータを有効に活用することは難しく、設計変更を繰り返し行うことで、結果的に開発期間が伸び、その結果コストの増大を引き起こすことが多いのです。
画期的な解析手法による効率化
本研究で注目すべきは、流線トポロジカルデータ解析という新しい手法の採用です。この手法を使うことで、圧縮機内の冷媒や油の流れを効率的に解析し、その結果を可視化します。これにより、どの部分で問題が発生しているのかを的確に把握でき、それに基づいた効果的な設計変更が可能となるのです。試行錯誤に頼らず、効率的に開発を進めることで、実際の開発期間やコストの大幅な短縮が期待されます。
具体的な研究内容と展望
この研究は、ダイキン工業の空調用圧縮機の性能向上を目指します。圧縮機はエアコンの心臓部であり、冷媒の温度制御を担いますが、その設計においては「油上り」という現象が大きな課題です。この問題に対処するため、流線トポロジカルデータ解析を通じて、内部の流れを詳細に見極め、どのように設計を整えれば良いかを明確にすることが目指されます。
共同研究の将来性
本共同研究は、2025年から20230年の間に、産業流体装置の開発に向けた基盤の整備を進める予定です。拡張性のある「TFDA-iソリューション」というサービスも開発され、流体解析ソフトウェアのカスタマイズに加え、特定の産業ニーズに応じた調整が行えるようになります。さらには、自動車や航空機など、さまざまな産業機器にこの技術を応用し、広範な発展が期待されます。
この連携を通じ、流体エネルギーを効率的に利用した新たな技術の登場と、それによる産業構造の変革が進むことを期待しています。

トピックス(その他)

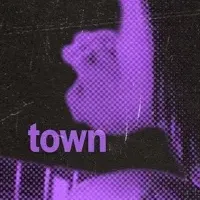








【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。