

125年の歴史を超えた南大東島と八丈島の漁師たちの挑戦
125年の歴史を超えた南大東島と八丈島の漁師たちの挑戦
日本の海に広がる魅力的な漁業の歴史が、東京・八丈島と沖縄・南大東島を舞台に新たな一ページを刻むことになりました。125年間で蓄積された歴史と伝統の中で、それぞれの漁師がどうし、そしてどのようにつながってきたのか。これを知ることで、私たちの食卓にもある「地魚」の宝庫そのものを深く理解できるでしょう。
番組「魚が食べたい!」の特別編
BS朝日で放送される「魚が食べたい!」では、約3000の港を取材し、地元にしかない新鮮な魚料理を楽しむというドキュメントバラエティ形式で、地元の漁師たちの情熱を描いています。2025年には、開局25周年を記念し、125年の漁業の歴史を通じて2つの島のつながりを特集します。特に面白いのは、南大東島の山城京介さんと八丈島の浅沼政宏さんの交流です。この二人の漁師の物語こそが、視聴者の心を打つことでしょう。
南大東島と八丈島のつながり
南大東島は1898年に八丈島の実業家によって発見され、1900年から開拓が始まりました。一見、距離が1157kmも離れている2つの島ですが、実は長年にわたる歴史的なつながりがあります。八丈島の文化や食風習が南大東島にも数多く残っており、特に「島寿司」などはその一例です。この背景を知ることで、漁業だけでなく食文化や生活様式への理解も深まります。
漁業への熱意
山城さんは、南大東島での漁業の未来を切り開くことを志し、八丈島での研修を決意します。南大東島では主にナワキリやキハダマグロを狙っているものの、限られた魚しか釣れない悩みを抱えていました。そこで、キンメダイ漁の技術を学ぶために八丈島へ飛ぶことになります。その際、彼は八丈島の方言「おじゃりやれ(いらっしゃい)」を耳にし、両島のつながりを実感します。
学びと挑戦
八丈島の名漁師・浅沼さんの指導のもと、山城さんはキンメダイを釣るための理論と実技を学びます。漁具の準備から始まり、漁場の選定、仕掛けの投げ方、さらに運航技術や鮮度管理、加工の方法に至るまで多岐にわたる課題をクリアしなければなりません。特に漁具選びやビジュアルな操船は初体験であり、次々と課題が山城さんを待っています。
感動の瞬間
8時間を超えるフライトを経て、彼の挑戦は始まります。八丈島での特訓を受けた山城さんが南大東島で初めてキンメダイを釣り上げようと挑む姿は、視聴者に感動を与えずにはいられません。果たして彼は、最初の漁で成功することができるのでしょうか?ぐっさんこと山口智充も、その奮闘に胸を打たれ、「素晴らしいですね」と感嘆の声を上げます。
まとめ
この特別編を通じて、125年を経ていよいよ新たな時代が切り拓かれようとしています。南大東島の未来を信じて行動する漁師たちの感動の物語が「魚が食べたい!」で描かれます。ぜひ、この感動的な歴史を実際に見届けてください。
番組情報
- - 番組名: BS朝日開局25周年記念「125年の時を超えた奇跡!魚が食べたい!1157kmを紡ぐ漁師の絆スペシャル」
- - 放送日時: 11月19日(水)よる7時〜9時54分
- - 放送局: BS朝日
- - オフィシャルリンク: 公式HP, X, Instagram
この番組を通じて、私たちも新たな価値を見出し、美味しい地魚を楽しむきっかけを掴むことができるかもしれません。ぜひご覧ください。



トピックス(エンタメ)




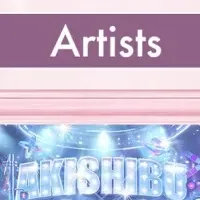



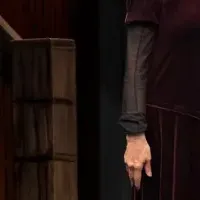

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。