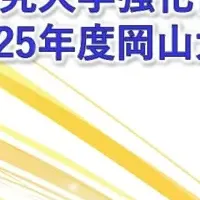

保護犬を守るための意識改革と未来の共生を考える
保護犬を守るための意識改革と未来の共生を考える
近年、保護犬の社会的な問題は、私たちの目の前に深刻な課題として存在しています。日本国内での保護犬の処分数は年々減少していますが、依然として多くの犬たちが命を失っています。これは、飼い主による飼育放棄や悪質な繁殖ビジネスという要因が大きく影響しています。2022年度の環境省の統計によれば、約2,400頭が処分され、私たちはこの現実に目を背けてはいけません。
保護犬を取り巻く現状と課題
日本国内での犬の処分数が減少しているとはいえ、私たちの認識や行動が伴わなければ、根本的な解決は難しいと言えます。飼い主の無責任な行動は、犬たちにとって非常に不幸な結果を招きます。また、地方自治体や動物愛護団体が抱える負担も増大しており、この問題は一個人だけで解決できるものではありません。これに対して、制度面での取り組みも進んでおり、動物愛護管理法の改正によって、マイクロチップ装着義務やブリーダー、ペットショップへの規制が強化されています。
個人の意識改革が不可欠
しかし、制度の整備だけでは不十分です。私たち一人ひとりが「最後まで責任を持つ」という意識を持つことが不可欠です。例えば、保護犬の譲渡活動に参加したり、寄付を行ったりすることができ、個人の力でサポートできる道は多様に存在します。私たちが小さな行動を積み重ねることで、大きな変化を生み出すことができます。
安心して共生できる未来へ
「不幸な命を生まない」ための取り組みは、善良なブリーダーや保護団体を守ることからも始まります。私たちが求められるのは、犬と人が安心して共生できる社会を築くための意識を高めることです。悪質な業者を排除し、全体としての動物福祉への意識を向上させることが、今後の課題となります。私たちの小さな選択は、犬と人の未来に大きな希望をもたらすことにつながります。
今回のレポートは、株式会社電巧社の「脱炭素経営ドットコム」が監修したもので、環境・健康・地域社会の持続可能性について触れています。サスティナブルな社会の実現は、すべての人々が力を合わせることで可能になると信じています。私たちが今、何を選択し、どのように行動するかが、未来への鍵を握っているのです。
詳しいレポートについては、こちらをご覧ください:レポートの詳細はこちら。

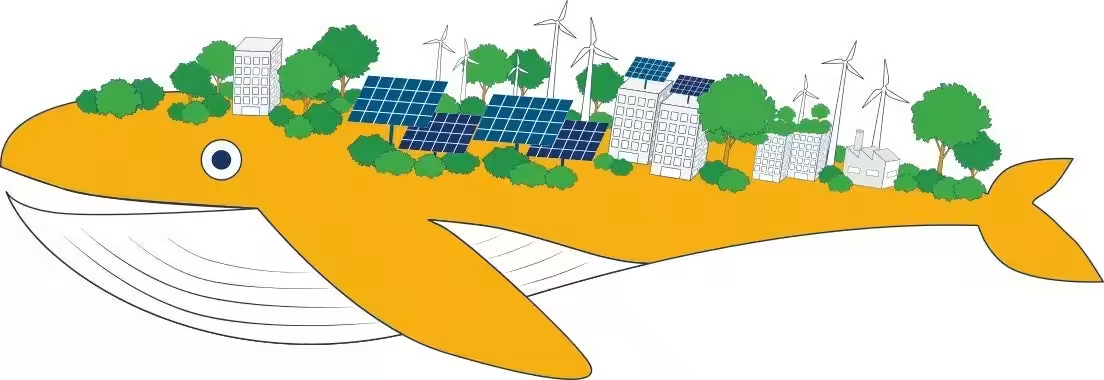

トピックス(その他)
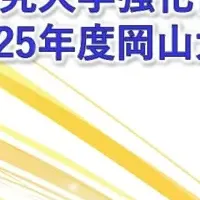

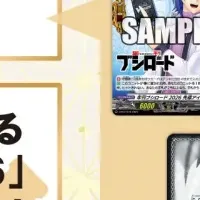
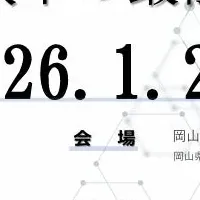
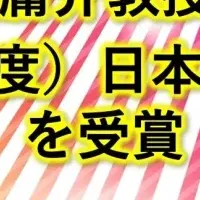





【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。