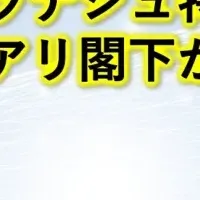

高齢社会の未来を探求する「Age-Well Conference 2025」報告
「Age-Well Conference 2025」開催の意義
9月16日(火)、東京ミッドタウン八重洲で、超高齢社会に向けた「Age-Well Conference 2025」が開催されました。このカンファレンスは、累計4回目となり、約400名が来場、延べ1,000名を超える参加者が各プログラムに参加するなど、大盛況でした。主催者であるAgeWellJapanは、超高齢社会の現実を見据え、豊かな老後を実現するための新たな価値を追求することを目的としています。
基調講演の重要性
イベントの冒頭には、東京大学高齢社会総合研究機構の秋山弘子名誉教授による基調講演がありました。「長寿社会に生きる」と題されたこの講演では、高齢者の心身の変化や人間関係について35年にわたり調査してきた結果に基づき、自らの老後を設計する必要性や、新たな社会インフラの構築の重要性が説かれました。長寿社会を支える産業の創生が求められる中、教授は未来への可能性を強調しました。
多様なセッションでの議論
続いて、企業セッションが行われ、各業界のリーダーたちが「Age-Well」をテーマに新たな視点からの「老いの再定義」を模索しました。特に「Age Well × 食」では、次世代の「日常食」に関するディスカッションが行われ、栄養バランスや発酵の重要性が語られ、未病ケアへの新たな道が探求されました。
さらに「Age-Well × ポジティブエイジ」セッションでは、ポジティブエイジの理念を持つ再春館製薬所が、五感に訴える健康管理のアプローチを紹介。シニアの自立性を尊重する視点が印象深かったです。
テクノロジーと働く未来
「Age-Well × テクノロジー」では、ソフトバンクの専門家が、超高齢化社会におけるシニアの社会参加をどう実現するかについて語り、今後の顧客体験のあり方を模索しました。また、高齢者が働き続けることの価値についても、「Age-Well × 働く」セッションで実例をもとに議論が進められました。
このように、カンファレンスでは多岐にわたるテーマで、各業界の専門家が活躍し、未来に向けたヒントが提供されました。
Age-Well Design Awardでの表彰
カンファレンスの一環として実施された「Age-Well Design Award」では、老いに対する固定観念を打破し、新たな視点を持つ企業や個人への表彰が行われ、受賞者が自身の取り組みを発表。会場は活気に溢れ、参加者の共感を呼びました。
参加者との意見交換
カンファレンスでは、ただの情報提供にとどまらず、参加者同士の対話も重要視され、コ・クリエーションボードを設けるなど、皆が積極的に意見を出し合うことができる環境が整えられていました。「Age-Well診断」ブースもあり、参加者は自らのライフスタイルを考えるきっかけを持つことができました。
今後の展望
カンファレンス終了後には懇親会が行われ、新たな人間関係が築かれる場ともなりました。将来的には、皆がポジティブに歳を重ねられる社会づくりを目指し、さらなる共創の機会を創出していく意欲が示されています。
Age-Well Design Labについて
「Age-Well Design Lab」は、株式会社AgeWellJapanが運営する高齢社会に関する研究機関です。新たな価値を生み出し、ポジティブな老後を促進する取り組みを進めています。一般的なシンクタンクの枠を超え、対話を通じた知見の共有を通じて、持続可能な社会を目指しています。詳細は公式ウェブサイト(AgeWellJapan)をご覧ください。








トピックス(イベント)
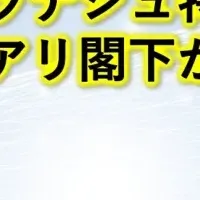

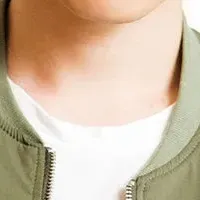


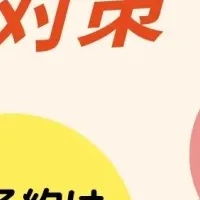


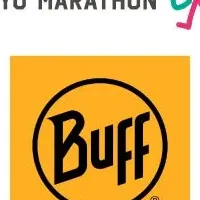

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。