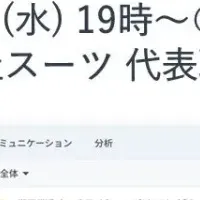
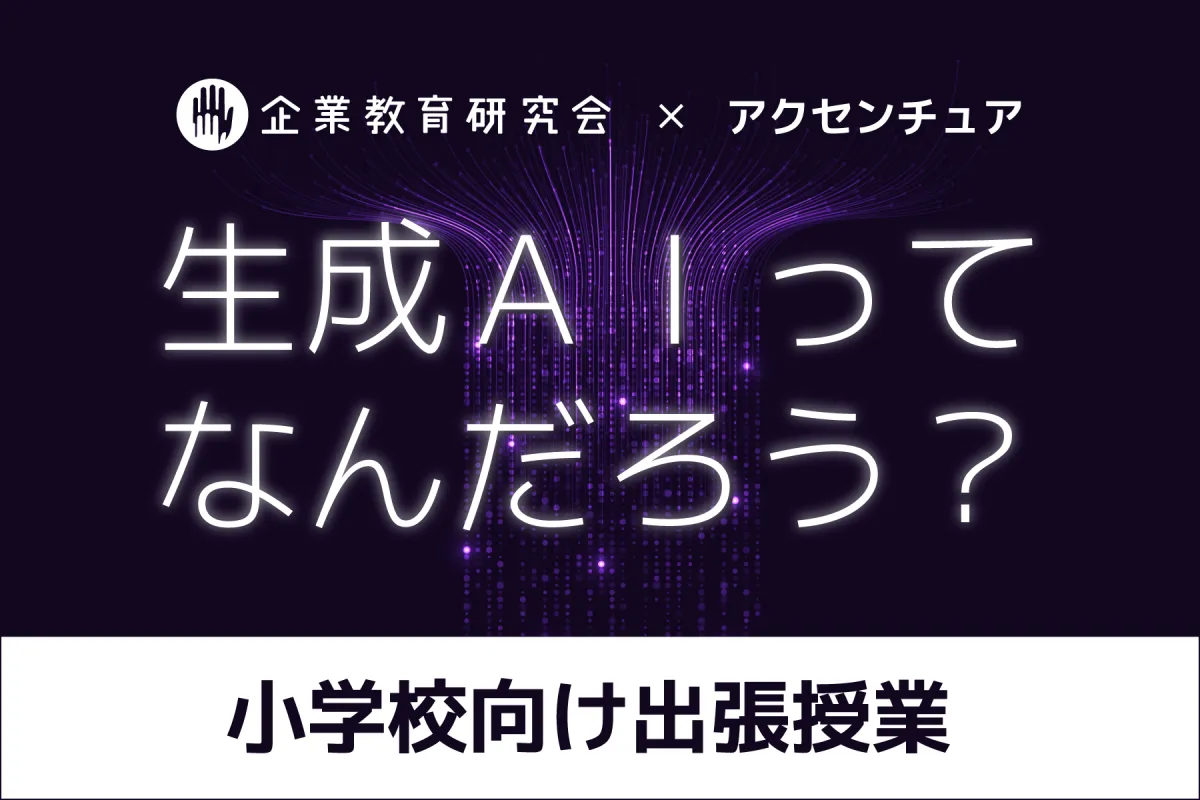
小学生が生成AIを学ぶ新プログラム「生成AIって何だろう?」始動
小学生が生成AIを学ぶ新プログラム「生成AIって何だろう?」始動
NPO法人企業教育研究会は、アクセンチュア株式会社の支援を受け、小学生に向けた新しい授業プログラム「生成AIって何だろう?」を開発しました。このプログラムは、生成AIが私たちの生活にどのように影響を与えるのかを子どもたちに理解させることを目指しています。パイロット授業は6月から始まり、教材も配布される予定です。
開発背景
現在、10歳前後の子供たちがスマートフォンを持つことが一般的になり、インターネットに接続する機会も増えています。実際に、調査によると小学生の66.7%がスマートフォンを通じてインターネットにアクセスしています。これに伴い、生成AIも日々の生活に溶け込んでおり、教育現場ではこの変化にどう対応するかが重要な課題となっています。
文部科学省が出したガイドラインでは、生成AIを授業に取り入れ、その利用方法と倫理的な視点を教育する必要性が強調されています。この新たなプログラムは、生成AIの基本的な理解を深めることを目的とし、AIと共存する力を育むために開発されました。
プログラムの概要
この授業は小学校5・6年生を対象としており、1回の授業は45分です。具体的な内容は以下の通りです:
- - AIの基礎を学ぶ: 日常生活の具体例を通して、AIの仕組みや役割を理解します。
- - 生成AIの可能性を知る: 講師によるプロンプト入力の実演を通して、実際に文章や絵が生成される様子を体験し、従来のAIとの違いを学びます。
- - プロンプト作成のコツを習得: 生成AIを使った学習方法を学び、「苦手な学習の克服」をテーマにしたプロンプト作成のコツを実習します。
- - 生成AIの注意点を考察: 生成AIが作成した情報の正確さや著作権について考え、最終的な情報判断は自分で行う重要性を認識します。
教育の必要性
AIは今後、子供たちが成長する環境で欠かせない存在です。藤川大祐教授(千葉大学教育学部長)は、AIを単に使うのではなく、その仕組みや倫理問題についても考える機会を持つことが重要だと述べています。子どもたちが未来の社会でAIを「使いこなす」のではなく、「共に生きる」ための基盤を築くことを目指しています。
普及への取り組み
この教育を広めるため、対面授業だけでなく、全国の教師が利用できるダウンロード教材の開発も進めています。今後、プログラムの授業風景を報道機関に公開する計画もあり、社会全体での生成AIリテラシーの向上に貢献する意向です。
企業教育研究会の役割
NPO法人企業教育研究会(ACE)は、教育の質を高めるために設立された団体で、企業と連携して新しい授業プログラムや教材を提供しています。今回の生成AIプログラムもその一環として位置づけられています。アクセンチュア社の協力を得て、教育現場でのAIリテラシー向上に寄与しています。
詳細はこちらからでご確認ください。
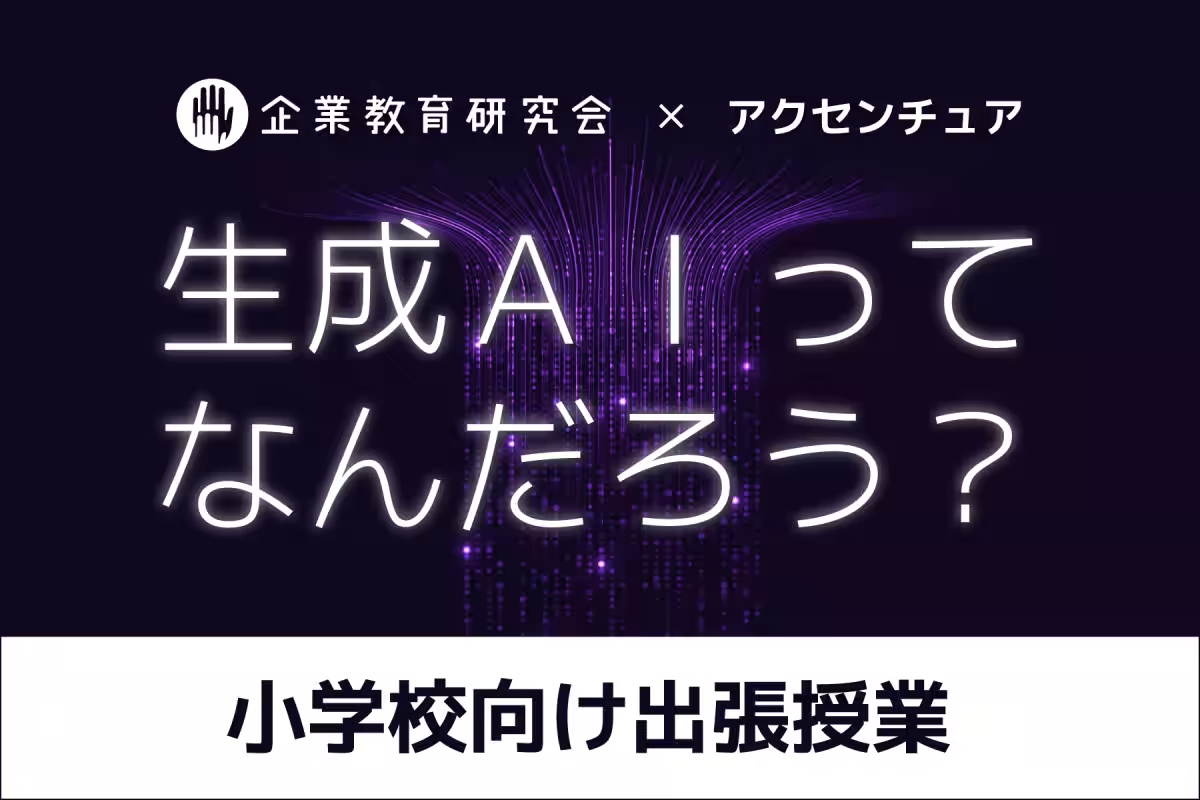

トピックス(その他)
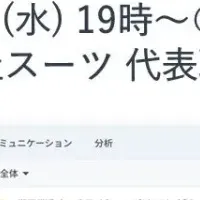
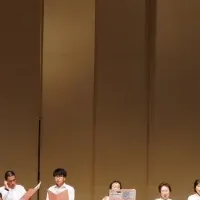
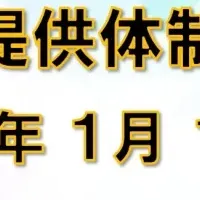




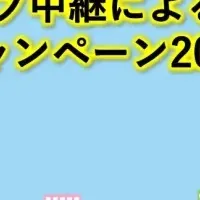
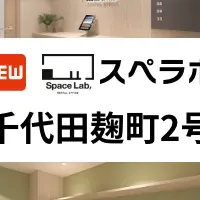
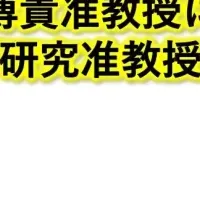
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。