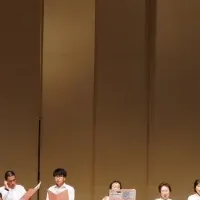

高校生落語プログラムが始動!海の未来を笑いで考えよう
高校生落語プログラムが始動
一般社団法人うみ落語協会は、2015号にあたる「海の落語プロジェクト」を立ち上げ、海の環境問題を笑いとトークを通じて学ぶ新プログラム、その名も「高校生落語プログラム」を発表しました。この取り組みは、2025年度の新たな試みとして、2025年7月27日にビジョンセンター品川でのキックオフイベントを皮切りに始まりました。
海の豊かさを次世代へ受け継ぐべく、人と人をつなぐ「日本財団 海と日本プロジェクト」の一環として、参加者たちは新鮮なアイデアを交流し、海洋問題を楽しく身近に考える機会を得ることが期待されています。
プログラムの目的
高校生落語プログラムの本質は、笑いや話術を通じて海洋問題を理解しやすく、また楽しく学ぶことにあります。若者たちが環境保護を自分たちの問題と捉え、積極的に発信する力を育むことを目指しています。プロの落語家による指導のもと、10名の高校生が集まり、彼らは「海落語」と「アクティブラーニング」に取り組むための5つのチームに分かれました。
キックオフイベントの内容
キックオフイベントは、約3時間にわたり様々な活動が展開されました。最初に行われたのは、落語家の吉原馬雀さんの「海落語」と、環境科学者の井手迫義和さんによる「アクティブラーニング」のセッションです。このセッションでは「海洋ごみ」をテーマにした演目が行われ、参加者たちは笑いながらも深刻な環境問題について学びました。プロの演技に触れることで、若者たちはこのプログラムの意義を深く感じたようです。
続けてのワークショップでは、「海」をテーマにした相互インタビューや、チームメンバーの共通点を見つけるゲームが行われ、見ず知らずの仲間たちが一体感を持つ場となりました。
実践的な講義と指導
その後、落語家の三遊亭朝橘さんからは、海落語を創作する際の基本的な作法と技術がレクチャーされました。「海の問題」を笑いに変えて伝える独自の視点が求められることが強調されました。一方、井手迫先生の講義では、「海洋温暖化」と「漁業資源」についての深い知識が共有され、高校生たちは真剣に耳を傾けていました。
今後の展開
今回のイベントで結成された5つのチームは、それぞれ異なるテーマでの創作や研究に取り組むことになります。落語を学び、海洋問題を考察するなかで、参加者たちの意識がどのように変わっていくのか、非常に楽しみです。また、各チームはフィールドワークの計画を進め、井手迫先生の指導を受けながらアクティブラーニングを進めます。今後の成果発表は、12月を予定しており、このプログラムがどのような形で結実するのか、多くの人々が注目しています。
団体の紹介
うみ落語協会は、日本の文化である落語の力を活用し、海洋保護の教育を推進するための活動を行っています。公式ウェブサイトには詳細が掲載されており、今後のイベントに関する情報も随時更新予定です。
私たちの海を守るための新たなアプローチとして、笑いを通じて環境問題に挑む高校生たちに、皆さんもご注目ください。






トピックス(その他)
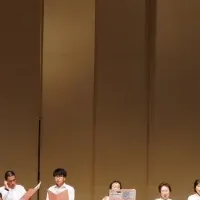
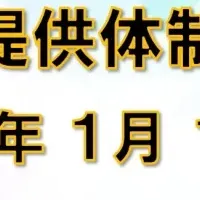




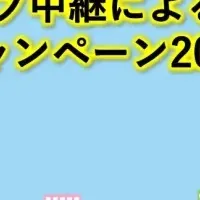
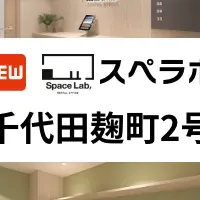
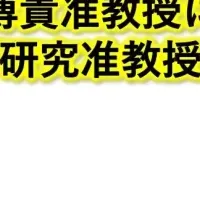
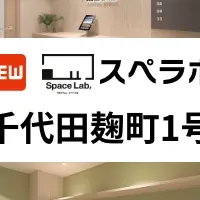
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。