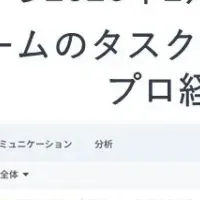

東京でのドローンを用いたCO2濃度測定実験の実施と未来展望
ドローンを活用したCO2濃度測定実験
2023年3月17日と18日の二日間、東京都内で行われたドローンを用いた温室効果ガス、特に二酸化炭素(CO2)濃度の測定実験が行われました。このプロジェクトは、株式会社東北ドローンが合同会社ソラビジョンの依頼を受けて、東京大学や東京都立大学、秋田県立大学などの専門家チームとともに実施しました。
実験の概要
この実験では、夜間、目視外、高高度という難しい条件下でのドローン飛行が求められました。使用された機材は、DJI Matrice 300 RTK。飛行は地上700メートルから行われ、100メートルごとにホバリングをしながらCO2濃度を測定しました。特に、井上誠准教授が開発した測定システムを装備し、高精度なデータを取得することに成功しました。
技術的な挑戦
今回の実験においては、ドローンが500メートルを超える高度で空気の質を観察するという重要な成果も得られました。ここまでの高高度での測定は、ドローン機材では初めての試みとされています。また、観測には数多くの許可申請が必要であり、特に新たな条件に応じて実施するのは多くの調整を要するため、困難を伴いました。共に関わった矢野法務事務所の代表、矢野耕太氏はその大変さを強調しました。
実験用のマウント設計には3Dプリンターを使用し、重量と強度のバランスを保ちながら、センサーが適切に機能することを実現しました。これにより、CO2濃度測定用の装置がスムーズに取り付けられるようになりました。
実験結果の分析
今回の測定データは、東京都内のCO2濃度が人間活動によって大きく変化することを示しています。特に、日の出と共に地表付近の高濃度の空気が上昇する様子が確認されました。この結果に対して、井上准教授は今後の観測にさらなる発展の可能性を感じているとコメント。
社会的意義と今後の展望
今須良一教授は、2025年に発射予定の温室効果ガス観測衛星GOSAT-GWと合わせて、この技術を活かすことの重要性を強調しました。将来的には、都市と森林地域での観測を進め、二酸化炭素濃度の違いとその原因を探求し、地球温暖化対策につなげていく方針です。
また、薄型で軽量なセンサーの開発を進めることで、コストを抑えつつ同時に多くのドローンを飛ばせるよう工夫する必要があるとのことです。
最後に
この新たな試みに関与した専門家たちは、ドローン技術の可能性とそれを通じた科学的な知見の蓄積を共有し、未来に向けての新たな挑戦を続ける抱負を述べています。株式会社東北ドローンの桐生俊輔代表は、今後も大学や研究機関と連携し、社会的な課題解決に寄与する取り組みを続けることを強調しました。今回の試みが新しい地平を切り開く一歩となることを期待しています。








トピックス(その他)
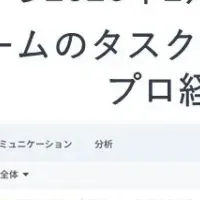

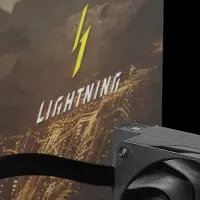
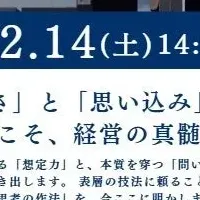

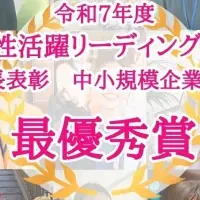
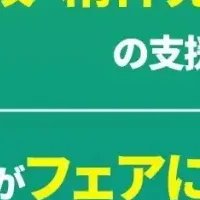

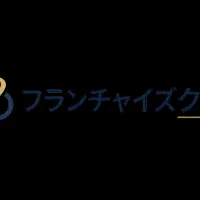

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。