

TOKYO SUTEAMで医療イノベーションの未来を切り拓く取り組みと期待
TOKYO SUTEAMで医療イノベーションの未来を切り拓く取り組みと期待
こんにちは。今回は、ReGACY Innovation Group株式会社と東京科学大学が協力して実施している「TOKYO SUTEAM」について、同大学の医療イノベーション機構に所属する特任教授、松浦昌宏氏へのインタビューをお届けします。このインタビューを通じて、これまでの取り組みや今後の期待についてお話しいただきました。
経歴と役割
松浦教授は、化学品メーカーでの研究開発者として20年の経験を経て、バイオベンチャーへの転職を果たし、事業推進や知的財産のマネジメントを担当してきました。さらに、科学技術振興機構で特許主任調査員を務め、多くの大学の知財支援も行ってきました。そして、滋賀医科大学での産学連携活動を経て、2023年から東京科学大学においてスタートアップ支援を行っています。
医療イノベーション機構の取り組み
過去の活動
これまで松浦教授は、医療やライフサイエンス分野での産学連携やスタートアップ支援に注力してきました。特に東京医科歯科大学時代には、オープンイノベーション機構を通じて、研究者や企業と密接に連携し、研究成果を社会に実装するための基盤を築いてきたそうです。
地域のニーズに応じた支援
しかし、2024年10月には東京工業大学との統合を経て、東京科学大学が発足し、再々度の構造改革が必要になりました。引き続き、産学連携を強化しながら新しい起業支援の仕組みを模索する日々が続いています。特に、「TOKYO SUTEAM」の活動では、技術シーズの効率的な管理や社会実装に向けた支援が重要であるとの認識があります。
TOKYO SUTEAMの意義
田中慶利氏、ReGACYのディレクターとともに、松浦教授はTOKYO SUTEAMの目的について次のように述べました。具体的には、研究者のスクリーニングやシーズリストの作成などを通じて、医療分野における新たなスタートアップの創出を実現しようとしています。特に、社会実装に向けた道筋をしっかりと築いている点が大変重要です。
今後の目標
松浦教授は、「今回の取り組みによりスタートアップが生まれ、外部からの資金調達を受けてさらなるGAPファンドの形成が可能になる」と期待を寄せています。そして、この取り組みによって東京科学大学が医療・ライフサイエンス系のスタートアップ創出に繋がるエコシステムを形成できるよう努力していくことが目標だと語りました。
結論
これからも、ReGACYを中心とした_tokyo SUTEAM_の活動が続いていくことは、医療業界だけでなく社会全体にも大きな影響を与えることでしょう。その成果がどのように現れるのか、今から楽しみです。松浦教授にお話を伺ったこのインタビューを通じて、未来の医療イノベーションに対する期待が高まりました。



トピックス(その他)






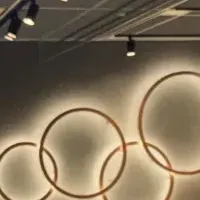

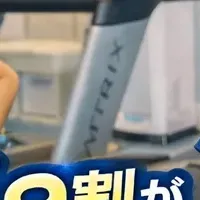
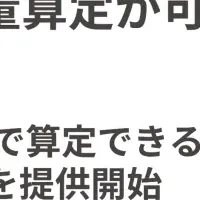
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。