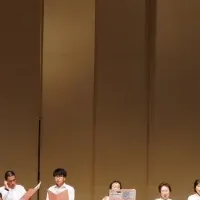
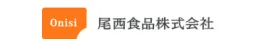
防災教育の新しい潮流:自分事として考える力を育む
防災教育の新しい潮流:自分事として考える力を育む
近年、防災教育が注目を集めています。特に、阪神・淡路大震災以降、災害に対する意識が高まり、現代においてもその重要性は増す一方です。兵庫県立舞子高校の環境防災科における取り組みや、尾西食品が提供する防災教育に関するコラムを通じて、自分自身、そして未来の世代がどう防災を捉えるべきかを考えてみます。
防災教育の背景と変化
兵庫県立舞子高校の環境防災科は、2002年に設立されました。この背景には、震災の経験を踏まえ、新たな防災教育の必要性がありました。「命の大切さ」や「助け合い」を学ぶ機会として、多様化する教育の一環で誕生したのです。従来の避難訓練だけでは命を守ることができないという認識から、実地訓練を取り入れたカリキュラムが組まれました。このような実践的な教育を通して、学生たちは主体的に学び、対話を重視した授業が展開されています。
語り継ぐことの意味と重要性
より重要なのは、「語り継ぐ」ことです。舞子高校では、多くの生徒が震災の体験を書き残す活動を行っています。この体験記は、ただの記録ではなく、未来の世代へのメッセージでもあります。過去の教訓を伝えるためには、直接の経験者が語ることが重要ですが、その後を継ぐのは今の子どもたちです。社会について語る責任を持つ彼らが、防災の重要性を理解し、将来へと伝えることが期待されます。
報道において「30年限界説」という言葉があるように、生きた体験を語る世代が減っている中で、今この瞬間を生きる子どもたちが積極的に自身の経験を語ることが新たな風を吹き込むのです。
自分事として考えるために
「防災を自分事として考えることが大切」と言われますが、実際にその要求や意義を理解している人は少ないことでしょう。そこで、具体的な方法論を紹介します。私たちが目指すべきは、自分事として考えられるような防災教育の実践です。
- - 1つ目は「結論だけでなくプロセスを教える」こと。子どもたちが理解できる範囲で現実を提示し、自ら考えさせることが重要です。例えば、震災時の痛ましい真実を共有し、その背後にあるプロセスを理解させることが彼らの思考を育てます。
- - 2つ目は「同世代からの語りを伝える」こと。アクティブラーニングを通じて、実際に震災を経験した世代の生徒たちが伝える体験談を聞くことで、より身近に感じられるのです。
- - 3つ目は「夢と防災を結びつける」こと。例えば、将来の夢を持つ子どもに、その夢が防災にどう役立つのかを問うことで、自分にとっての防災の意義を深めることができるのです。
尾西食品の取り組み
尾西食品は、防災食のリーディングカンパニーとして、避難時にもおいしいものを食べたいという思いから、非常食の開発を行っています。災害時にこそ美味しい食事が必要だという理念のもと、日常食を基にした長期保存可能な食品を提供しています。
「避難所での食事に頼るのではなく、日常と同じような食生活を維持すること」が理想だと考えています。
未来へつなぐ教育
理想的な防災教育は、学校での授業として位置付けられるべきだと思います。生徒たちが学べば学ぶほど、行動につながることが実証されています。行動を促す教育の場を設けることで、社会全体の防災力も高められるのではないでしょうか。このような取り組みを通じて、次世代が防災を自分事として考え、より安全な社会を築く一助となることを期待しています。
詳しい情報や活動については 尾西食品の公式サイト をご覧ください。
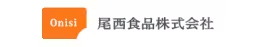
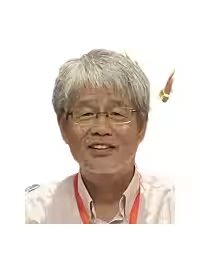


トピックス(その他)
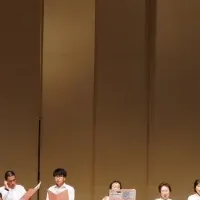
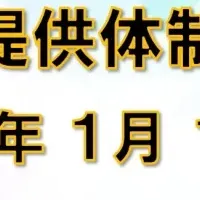




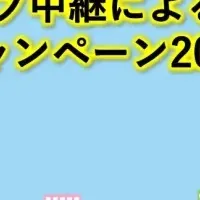
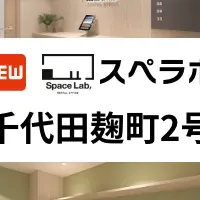
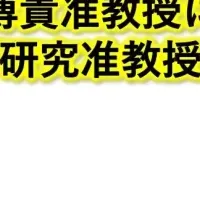
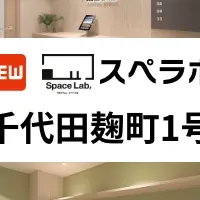
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。