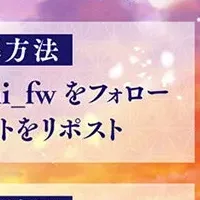
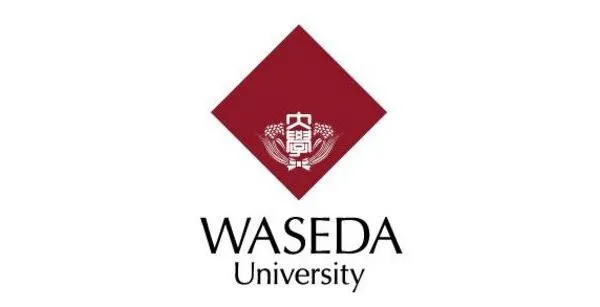
日本のファンタジーに息づくデュラハンの謎と変容の歴史
日本のファンタジーに息づくデュラハンの謎と変容の歴史
アイルランドの民話に登場する首なし妖精「デュラハン」が、日本のファンタジー作品でどのように変貌したのか、その過程を探る研究が行われました。デュラハンは、本来は死を告げる妖精として知られていますが、日本ではゾンビやアンデッドのキャラクターとして認識されています。この現象は、1980〜1990年代のケルト・ブームを背景に、異文化からの影響を受けた日本独自の捉え方が形成されたことによります。
研究の枠組みとアプローチ
この研究は、大阪公立大学のエスカンド・ジェシ准教授によって進められ、民俗学と情報メディア学を横断する手法が採用されています。デュラハンの日本での変容を解明するため、豊富な図像分析や文献調査が行われ、具体的には1985年から2019年に発売された日本のゲーム作品に登場するデュラハンの事例を分析しました。
アイルランドの詩人W. B.イェイツの著作は、デュラハンの日本への導入にあたって大きな役割を果たしました。彼の作品は、翻訳の過程で「幻影」と「生気」の違いが生じ、結果としてデュラハンは妖精ではなくアンデッドとして再解釈されることになったのです。
文化的ハイブリッド化
デュラハンが日本においてどのように受容され、その姿が変化したのかを考察する中で、「文化的ハイブリッド化」という概念が浮かび上がります。異なる文化が交差し、新たな形態を生み出す過程がこの事例には色濃く反映されています。デュラハンは、国内のファンタジー作品だけでなく、韓国や中国のゲームや小説にも影響を与え、国際的な文化循環の重要な一翼を担っています。
日本のファンタジー界における誤訳と創造性
誤訳や解釈のずれが、日本でのデュラハンの再想像にとって重要な役割を果たしました。誤った認識が新たなモンスター像を生み出し、ファンタジー事典やRPGに登場することで、その影響は大きく広がりました。エスカンド准教授は、これが単なる誤訳に終わらず、創造的な再想像を促す契機として機能したことを指摘しています。
国際的な影響と今後の展開
デュラハンの日本的再創造は、やがて韓国のゲーム『マビノギ』や小説『月光彫刻師』などに広まり、逆に中国の作品からも新たな解釈が生まれるなど、文化の国境を越える力強さを持っています。このように、多国籍のメディアを介して発展するデュラハンは、国際的にも重要な文化的アイコンとなっているのです。
今後の研究においても、デュラハンに関連する文化的定型についての更なる分析が期待されます。特に女性キャラクターの描かれ方や、異文化にルーツを持つモンスターが日本社会の中でどのように受け入れられているのかを探ることは、現在のファンタジー作品の多様性を理解する上でも重要な課題です。
研究の意義
本研究は、グローバル化が進む今、異文化の受容や再編成がどのように行われるかを示す具体的な事例として位置づけられます。日本のファンタジー作品が持つ独自の視点が、世界に通じる新たな神話を生み出していることを考えると、この研究は今後ますます重要性を帯びていくことでしょう。デュラハンの物語が示すように、異文化のモチーフは新たな創造の力を秘めているのです。
トピックス(エンタメ)
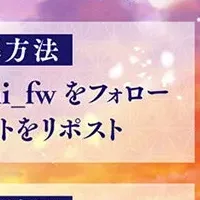
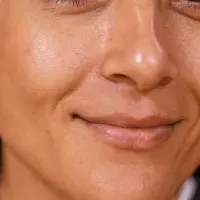



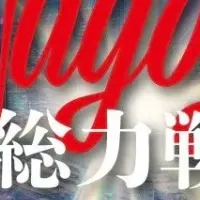
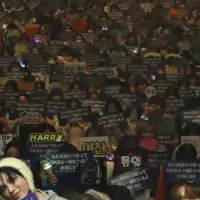



【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。