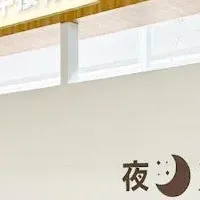
過疎地域の現状を見つめる新たな調査結果が発表!
過疎地域の現状を見つめる新たな調査結果が発表!
国土交通省と総務省は、過疎地域などの条件不利地域における集落の状況を把握するための調査を、5年ぶりに実施しました。この調査は、令和元年度の前回から5年間の変化を捉えることを目的にしており、最新の集落現況が明らかになりました。
調査概要
調査対象となるのは、令和6年4月1日時点での過疎地域等の集落で、全国で78,485集落に及びます。全体の人口は1,432.9万人に達し、1集落あたりの平均人口は184.9人という結果です。特に、65歳以上の高齢者が住民の半数を超える集落が40.2%にのぼり、これは前回調査から約10ポイントの増加を示しています。
過疎地域の定義
本調査での過疎地域とは、特別措置法や各種法令に基づいている市町村のことを指し、条件不利地域に該当します。調査方法として、各市町村に調査票を配布し、結果を回収する形で進められました。調査期間は令和6年10月3日から12月24日までです。
主な調査結果
1. 人口動向
- 過疎地域に存在する集落の数は478減少し、以前の集落数7615から7578に減少。また、集落人口も減少し、1,339.7万人と報告されています。
- 無人化した集落の数が296に達し、さらに集落の再編により617集落が減少しています。新たに誕生した集落は219集落に過ぎず、全体としては厳しい状況が続いています。
2. 将来の見通し
- 調査をもとにした市町村の報告では、当面存続するとされる集落は73.8%であり、無人化する可能性がある集落も4.2%という結果に。無人化が進行している現状が浮き彫りになりました。
- さらに、実際に無人化した集落は63あり、無人化が懸念される集落では主な交通手段として、デマンドバスや乗合タクシーの利用が多いことも調査結果から分かりました。
3. 生活サービスの立地状況
- 調査によると、無人化が危惧される集落では、商店、飲食店、病院などの生活サービスの立地率が非常に低くなっています。商店の割合は3.6%、飲食店は5.8%など、生活基盤が脆弱な状態です。
4. サポート人材の活動状況
- 集落支援のために活動している人の割合が増加しており、集落支援員は28.8%に達し、地域おこし協力隊も22.0%と、地域活性化を目的とした取り組みが進んでいることが報告されています。
まとめ
今回の調査結果は、過疎地域の実情を示す重要なデータであり、これからの地域活性化に向けた取り組みがどのように進められるのかが焦点となります。孤立した地域が再生するためには、多様な施策や人材の活用が一層求められるでしょう。今後の変化に注目していきたいと思います。
トピックス(その他)
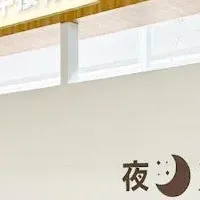
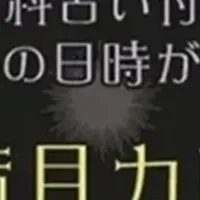
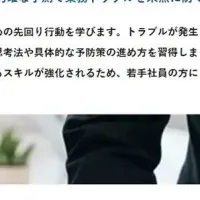
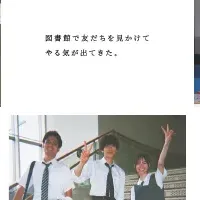

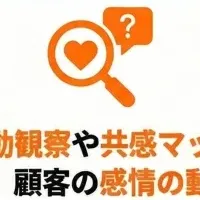

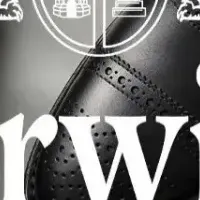

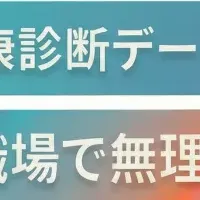
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。