

九州大学生と地域住民の協力でサンショウウオの生息地を保全
九州大学生と地域住民が挑んだサンショウウオの生息地保全活動
2025年7月13日、佐賀県唐津市相知町の横枕地区にて、九州大学の学生たちと地元住民による特別な保全活動が行われました。これは、地域資源と暮らしを守るための実践の場として設定されたもので、環境省にOECM認定を受けた自然共生サイトで実施されました。これに先立ち、地域交流の一環としてウクライナ料理の試食会が開催されたため、参加者たちはこの日を地域とのつながりを強化する機会としても捉えていました。
倒木撤去の意義と目的
今回の活動で主に行われた作業は、沢沿いに倒れている杉や竹などの「倒木の撤去」でした。この地域は、九州北部にしか生息しない希少なサンショウウオを始めとする多様な生き物たちが暮らす貴重な生態系です。倒木の撤去は、以下の2つの大きな目的があります:
1. 住宅被害の防止:大雨の際に、倒木や土砂が流出することで住宅やインフラに影響を及ぼすことを防ぐこと。
2. 生物多様性の保全:希少な生物が生息する環境を保護し、地域の生態系を守ること。
これまでも地域の住民からは倒木問題への懸念が上がっていましたが、高齢化や労力不足から、手を付けることができずにいたのが現状でした。そんな中、地域交流を目的に訪れていた九州大学の学生たちが連携し、この保全活動が実現したことは、地域にとって非常に重要な一歩でした。
伝統行事への活用
今回撤去された倒木は、地域の伝統行事「鬼火焚き」の燃料として再利用される予定です。こうして、環境保全活動が実社会に役立つ形で地域の文化にも寄与していくのです。
ウクライナ料理を通じた交流
作業が終了した後、参加者たちは九州大学の学生たちが用意した「ウクライナの冷製ボルシチ(ホロドヌイク)」を一緒に味わう時間を持ちました。汗を流して働いた後の一皿は、食を通じて交流するかけがえのない瞬間となり、地域の住民と留学生たちの心が繋がる交流の場となりました。このように、食と環境保全を通じて、新たな結びつきが生まれていくのです。
この活動では、地域の自然共生に対する理解を深めながら、国際交流も促進していくことが期待されています。九州大学の公式アカウント (@kyudaisai_borsch) では、ウクライナの文化と味を伝える情報が発信されており、横枕農園でもビーツなどの地域資源が販売されています。
今後の展望
本活動は、地域住民と学生たちの力を結集して行われる「里山保全」の新たな形として、今後も継続される計画です。地域の環境と文化を守りながら、一緒に育む活動が、地域全体にとっての持続可能な未来を切り拓く一助となることを期待しています。環境保全活動と国際交流が交わる場として、九州大学と地域との関係は今後さらに深化していくことでしょう。








トピックス(その他)

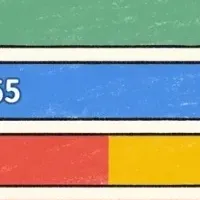
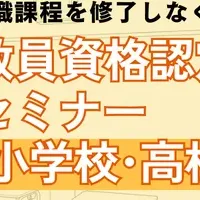


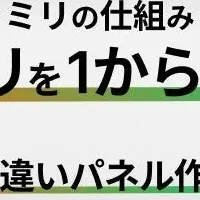


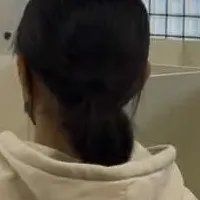
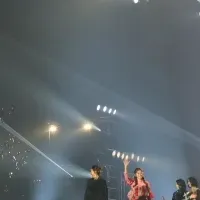
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。