
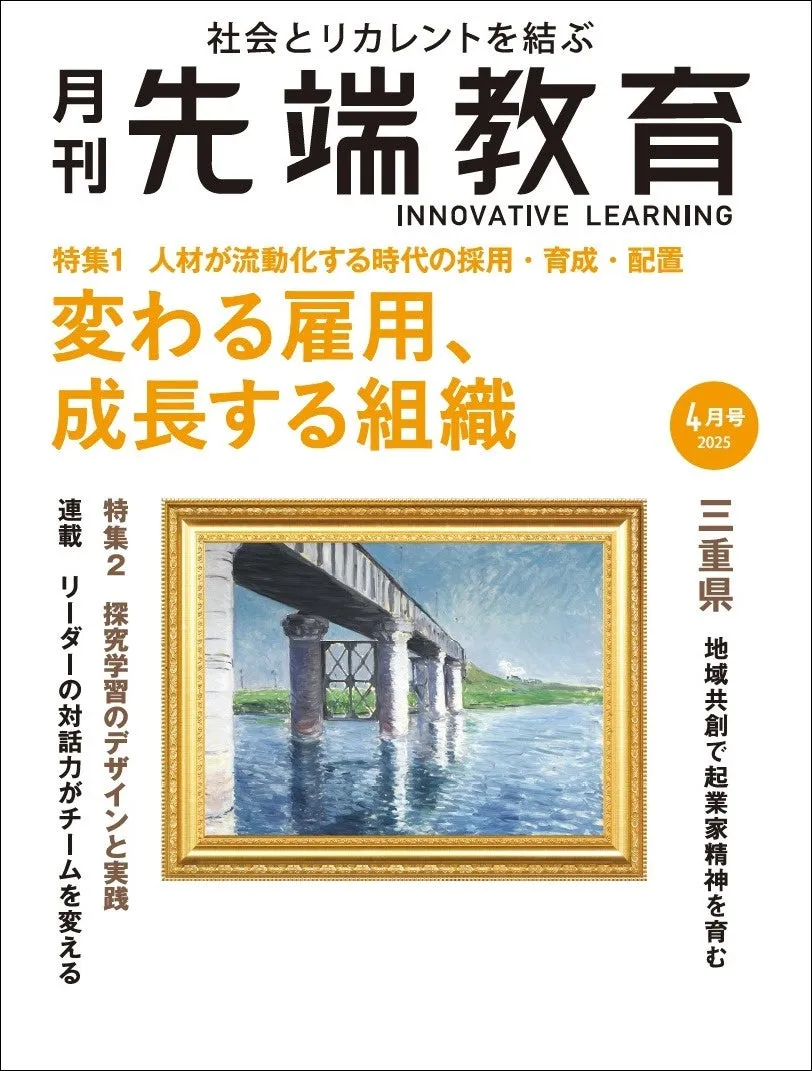
雇用の流動化と教育の未来を探る『月刊先端教育』2025年4月号
読みどころ
2025年4月号の『月刊先端教育』は、雇用が流動化する現代における組織の在り方や、教育に関する新しい視点を提案する内容が盛りだくさんです。今回特集されるのは、「変わる雇用、成長する組織」です。このテーマでは、昨今の社会人に求められるスキルや、企業がどのように多様な人材を受け入れ、育成していくかに焦点を当てています。
雇用の流動化とその影響
雇用システムの見直しや働き方の多様化が進む中で、労働移動が活発化しているのは周知の事実です。経済産業省が提唱した「人材版伊藤レポート」によれば、雇用コミュニティの変革が求められています。この特集では、企業と個人の関係性がどのように変わっていくのか、人的資本経営の観点から詳しく考察されています。
名古屋大学の鈴木智之准教授は、雇用の流動化が進んでいる現在、社員の心理的安全性やエンゲージメントがますます重要になっていると指摘しています。これにより、社員一人ひとりの理解が求められる時代が到来しているのです。
一方、産業能率大学の佐藤雄一郎副所長は、組織と個人の関係が以前より長期を前提としない中で、スキルを育む環境の整備が重要だと訴えています。企業はただ人材を囲い込むのではなく、個人が能力を発揮できるフィールドを提供する必要があると強調しています。
探究学習の新たな潮流
特集2では、「探究学習のデザインと実践」と題した内容が展開され、外部リソースの活用や学校組織の持続可能な作り方についての具体的な提案がされています。特に、日本全国の学校で探究的な学びが進む中で、現場の声として「主体的にならない」や「教材開発の負荷が大きい」という課題も浮き彫りになっています。日立財団の内藤理事長や教育学の登本准教授など、多様な専門家がそれぞれの視点から探究学習の推進方法を語っています。
また、三重県のプロジェクトでは、地域の教育と人材育成に焦点をあて、自己肯定感を重視した教育や、共同創造による新たな取り組みが進められています。これにより、地元学生たちの成長を支援し、社会と連携した教育の重要性が再認識されています。
まとめと今後の展望
『月刊先端教育』では、変化する雇用環境や教育の現場が直面している課題をしっかりと掘り下げ、現実に即した解決策を模索しています。これらの取り組みが、今後の組織の成長と個人のキャリア形成にどのように寄与していくのか、注目が集まります。この号を通じて、自らのキャリア形成について考え直す良い機会となるでしょう。
ぜひ書店で手に取ってみてください。ただいま、全国書店やAmazonでも販売中です。
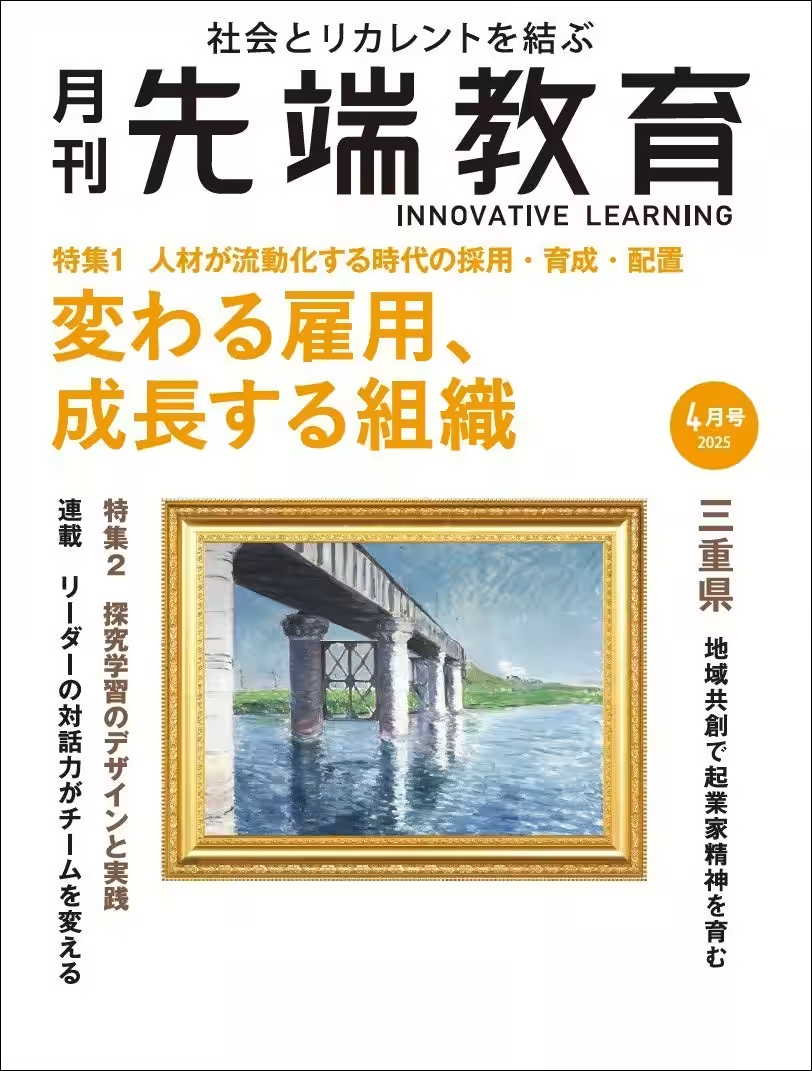






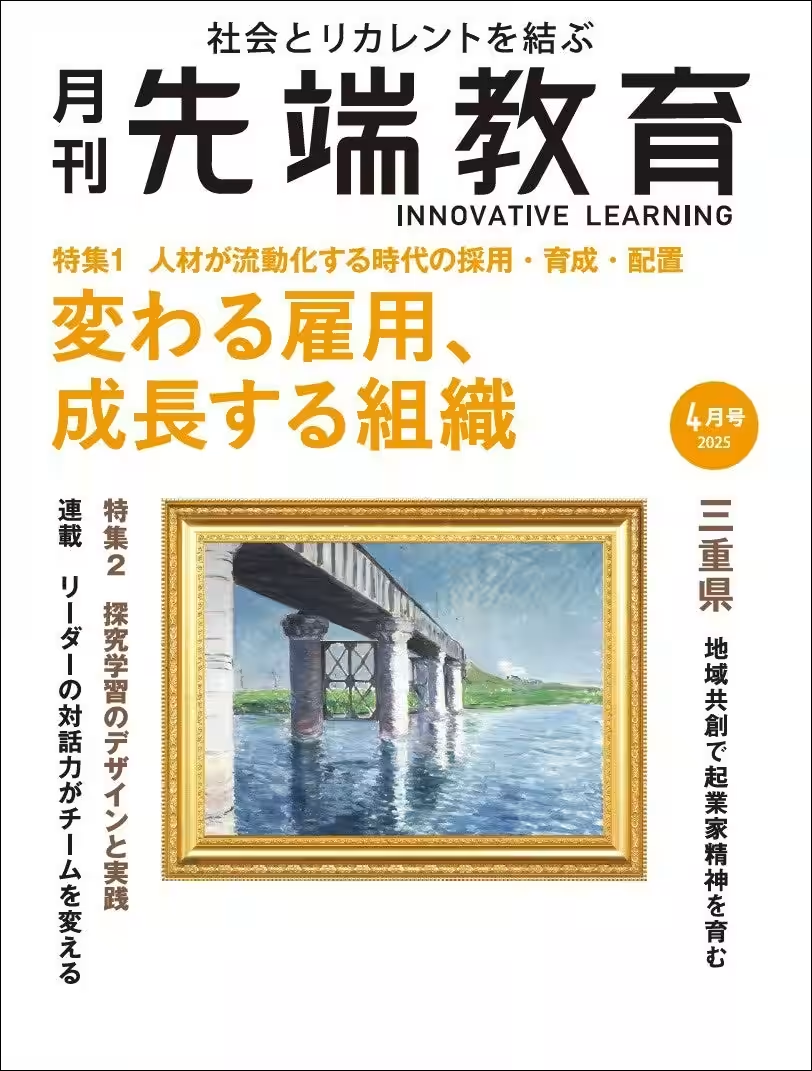
トピックス(その他)

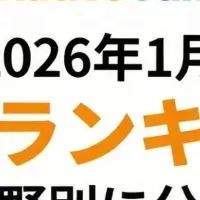




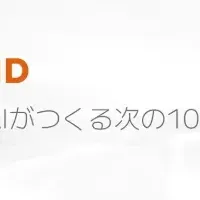



【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。