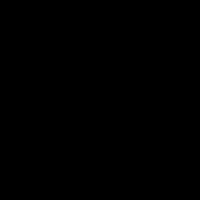

冨永愛が高知のいざなぎ流を体験し伝統文化を未来に紡ぐ
冨永愛が高知のいざなぎ流を体験
10月8日と15日の夜10時から放送される「冨永愛の伝統to未来~ニッポンの伝統文化を未来へ紡ぐ~」では、モデルで女優の冨永愛が高知県香美市の物部町を訪れ、古くからの民間信仰「いざなぎ流」の魅力を探ります。この地に脈々と受け継がれてきた文化と信仰の秘密に迫る彼女の姿は、視聴者に新しい視点を提供してくれることでしょう。
冨永が向かったのは、一棟貸しの宿「まきの宿」。この宿は、物部町の伝統であるいざなぎ流を体験する場所で、御祈祷の際に使用する御幣(ごへい)の切り方や、伝統的な舞神楽も学ぶことができます。いざなぎ流は、陰陽道や神道、密教などが融合して形成された、奥深い民間信仰のひとつです。「いざなぎ」という名称は、いざなぎ流の起源を伝える「いざなぎ祭文」に登場する神様に由来しています。
この祭文では、天中姫宮という占いの名手が人々を救うべく、天竺に渡り、いざなぎ大神から祈祷の技術を学びました。この技術は代々太夫と呼ばれる人々によって口伝で継承されてきたのです。昭和55年には、国の重要無形民俗文化財に指定され、その文化的価値が評価されています。
いざなぎ流では、太夫が地域の家庭を訪れて神を祀り、病気を治すための祈祷を行ってきましたが、現在は太夫の高齢化が進み、後継者不足が深刻な問題となっています。物部いざなぎ流神楽保存会の会長、佐竹美保氏は、この伝統を絶やさぬよう、子どもたちに舞神楽を教える活動を行っています。
冨永愛が体験したのは「御幣切り」です。御幣とは祈祷の際に使う切り紙で、祈祷の種類や実施場所によって形が異なります。その種類はなんと200以上にも及びます。冨永は「天神の払い幡」を切り、その出来栄えによって「生き幣」と「死に幣」に区分されるという神秘的な体験をしました。果たして彼女が切った御幣は、如何に?
また、4人の太夫によるいざなぎ流舞神楽の披露も行われ、冨永はその神秘的な舞の美しさに感銘を受けました。「とても不思議で神秘的で、言葉にできない気持ちになりました」と語っています。この舞神楽は、太鼓の音に合わせて、様々な舞いが繰り広げられます。
2025年1月3日には、高知県立美術館ホールで略式御祈祷神楽の公演も予定されています。ここでも、舞台周辺にしめ縄で結界を設け、御幣を飾ります。通常は1週間かけて行う御祈祷を、この日は一日で行うため、特に緊張感が漂います。この公演には練習を重ねた子どもたちも参加し、会場は立ち見が出るほどの賑わいを見せました。しかし、太夫の高齢化が影響し、これが最後の公演になる可能性もあると話す佐竹氏に、冨永は「いざなぎ流は日本の原風景ともいえる民間信仰。実際に体験することで、未来へ繋ぐべき地域の大切な宝だと感じました」と述べています。
「冨永愛の伝統to未来」では、全国各地の伝統文化を紹介し、後継者問題などに焦点を当て、その現状を描いています。是非、公式SNSやYouTubeで冨永の味わい深いオフショットや、リアルな体験をチェックしてください。



トピックス(その他)
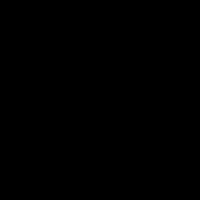
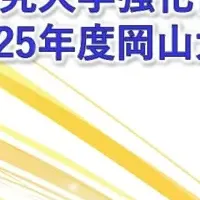

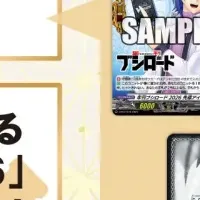
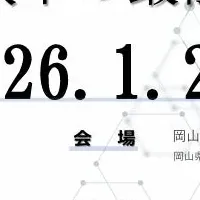
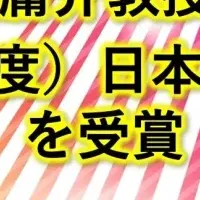




【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。