

涸沼の生物多様性を体感!ウナギモニタリング調査のご案内
夏休みの涸沼でのウナギモニタリング調査
今年の夏休み、茨城の涸沼で行われる「ウナギモニタリング調査」への参加者を募集します。このイベントは、ニホンウナギの資源回復と生物多様性の理解を目的にしたものです。日時は8月23日(土)の10時30分から15時まで。場所は親沢公園キャンプ場と涸沼水鳥・湿地センターです。
モニタリング調査とは?
このモニタリング調査では、特に石倉カゴと呼ばれる人工的なウナギの増殖礁を使用します。これは石を詰めた網カゴで、河川内に設置されています。九州大学農学研究院の特任教授、望岡典隆氏の指導のもと、地域の漁協や行政と連携して行われており、2024年からスタートしました。これまでに2回の調査を行い、今回で3回目となります。
参加者は親子連れを含む約50名。彼らは望岡教授と共に石倉カゴを引き上げ、その中にいる生き物の種類や数を記録します。もしニホンウナギが見つかれば、その長さや太さ、重量を測定し、前回調査で埋め込んだ個体識別タグを確認します。これにより、同一個体の健康状態や成長過程を追跡できるのです。
涸沼水鳥・湿地センターで学ぶ
午後には涸沼水鳥・湿地センターに場所を移し、望岡教授による「ニホンウナギの生態と生息水域」についての講演があります。センター内では涸沼の自然環境との関わりを学べる展示が行われ、生物模型やミニ水族館を通じて、生物多様性について楽しみながら学ぶことができます。
環境保護と地域の取り組み
業界団体や漁業組合と連携しているパルシステムは、2013年にニホンウナギが絶滅危惧種に指定されたことを受けて、大隅地区養まん漁業協同組合と共に「大隅うなぎ資源回復協議会」を立ち上げました。そこで資源回復活動の一環として、ニホンウナギの生息環境の保全と再生に向けた研究やワークショップを重ねてきました。
今後も、涸沼の石倉カゴでのモニタリング調査を通じて、様々な生物の生息を守り、地域の自然環境を次世代へと引き継いていきます。
参加方法
参加希望の方は、事前に申し込みが必要です。詳細はパルシステム茨城・栃木の公式ホームページをご覧ください。生物多様性の保全について学び、楽しむこの素晴らしい機会をぜひお見逃しなく。
まとめ
涸沼のモニタリング調査は、地元の自然を見つめ直し、未来に繋げるための大切な取り組みです。ウナギを通して地域の生態系の重要性を学び、楽しむことができるこのイベントに、ぜひご参加ください。環境を守るためには、皆さんの参加が不可欠です。






トピックス(イベント)

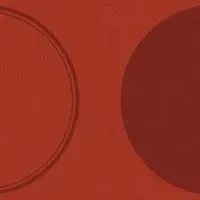






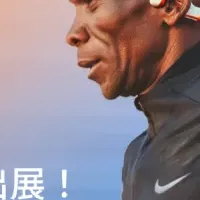

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。