

デフリンピックを見据えた手話教室が福島で開催されました
医療従事者向け手話教室、福島で成功裏に開催
2025年、福島でのデフリンピック開催を前に、TCB東京中央美容外科が特別な手話教室を実施しました。9月23日の「手話の日」に行われたこの教室は、医療従事者を対象としたもので、福島赤十字病院の多目的ホールで開催されました。約20名の参加者と共に、手話の重要性と医療現場における活用方法について深く学ぶことができました。
手話教室の内容
この手話教室では、TCBの耳鼻咽喉科専門医である中園医師が講師をつとめました。医療現場での手話活用に関する講義が行われ、医療従事者が実際にろう者や難聴者の患者様とどのようにコミュニケーションを取るべきかについて具体的な経験談を交えながら説明しました。
中園医師は、「手話も英語と同様に、完璧を目指すのではなく、コミュニケーションを大切にすべきだ」と強調。参加者はこの言葉に共感し、手話の学びを楽しむことができました。
基礎から学ぶ手話
続いて、福島県聴覚障害者情報支援センターの山田尚人所長が基礎手話講座を開催しました。「こんにちは」や「おはよう」といった基本的な挨拶から始まり、病院で頻繁に使われる用語の手話も学びました。これにより、医療従事者たちは実際に患者と対面したときのコミュニケーションが一層スムーズになることが期待されます。
聴覚障害者の現状と課題
山田所長は福島県内の聴覚障害者の現状についても触れました。2024年の統計では、聴覚・平衡機能障害者は6682人いたものの、そのうち手話を使うのは約700人しかおらず、コミュニケーション手段に乏しい中で様々な困難を強いられています。これに対し、医療機関での情報提供や公共交通機関でのアナウンスの改善が求められています。
特に、災害時においては聴覚障害者は非常ベルや防災無線から情報を得ることができず、大きなリスクを抱えています。さらに、コロナ禍ではマスクの着用がコミュニケーションを難しくし、聴覚障害者にとっては非常に深刻な問題でした。これらの問題を通じて、より良い医療環境の整備が必要であることが再認識されました。
グループによるロールプレイ
講座の後は、参加者が4人1組になり、医師役、看護師役、患者役に分かれてロールプレイを行いました。実際の医療シーンをシミュレーションすることで、どのような課題があるのか、また合理的配慮が必要な場面について話し合いました。この実践を通じて、多くの気づきを得ることができました。
手話の普及と意識啓発
手話教室の最後は、全員で手話で拍手を行い、無事に終了しました。このような活動は、デフリンピックに向けた聴覚障害者との共生社会の実現に向けた重要な一歩となるでしょう。
TCBは今後も様々な手話教育を通じて、医療従事者や地域社会の障害理解を深め、共生社会の実現に向けた取り組みを続けていく予定です。福島県内での手話の普及とともに、医療分野での格差解消を目指し、さらなる活動が期待されます。
この教室を通じて、聴覚障害者と医療従事者とのコミュニケーションが円滑になり、多くの患者がより良い医療を受けられるようになることが望まれます。

















トピックス(その他)

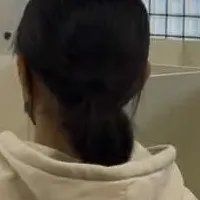
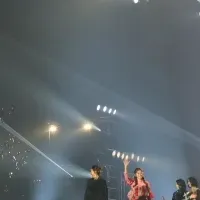
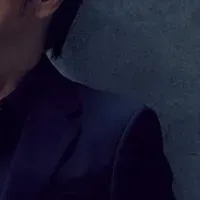
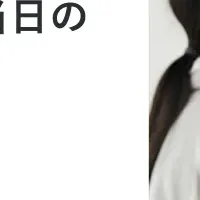
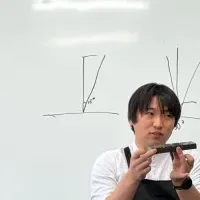
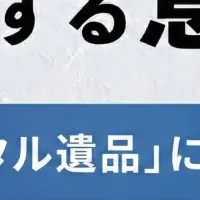



【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。