

岡山大学SDGs推進表彰で地域活性化プログラムを発表した吉川准教授の取り組み
岡山大学のSDGs推進表彰に見る地域活性化への取り組み
国立大学法人岡山大学が2024年度SDGs推進表彰を受賞しました。その中でも特に注目を集めたのが、吉川幸准教授による「地域の未来デザイン(実践編)」の取り組みです。この授業は、学生がフィールドワークを通じて地域の課題に取り組むにもかかわらず、ただ単に教えられるだけの学問とは一線を画す体験型のプログラムです。
SDGs推進表彰の受賞内容
2025年8月3日、岡山大学ではSDGs推進表彰の受賞者が集まり、その取り組みを発表するイベントが開催されました。吉川教授は、今回の表彰で優秀賞を受賞した「教育分野」の代表として、プログラムの詳細を報告しました。彼の取り組みは、ただの知識の習得に終わらず、地域活性化に向けた実践を通じて学ぶものであることが特徴です。
プログラムの具体的内容
このプログラムでは、参加する学生が地域を「観光客目線」で見つめなおす機会が与えられます。また、「温故知新」というキーワードのもと、地域の年配者からのヒアリングを行ったり、岡山県立井原高校の生徒との合同で行われるワークショップも盛り込まれています。これらの活動は、地域固有の文化や歴史を学ぶ非常に貴重な体験となっており、学生たちの意識に変化をもたらしています。
疑問を深めるプロセス
「地域の未来デザイン(実践編)」では、学生たちが調査や討論を通じ、自ら問いを立てその深層に迫ります。このようなプロセスを経ることで、単なる知識として留まらない、地域の現実を理解するための具体的な視点を得られるのです。活動の振り返りを通じて、学びの成果を確実なものにします。
地域とのつながりを意識する
吉川准教授は、授業を通じて実感する地域の課題や学生自身の目指す未来に対して、個々がどのように行動するかを重要視しています。実践的な活動を重ねることで、学生は地域活性化の担い手となる自覚が芽生え、それがいずれ地域の未来にもつながるのです。このような教育の質こそが、岡山大学を特色ある研究大学へと導いています。
学長の期待
岡山大学の那須保友学長は、吉川准教授の活動を高く評価し、参加した学生たちの今後の活躍に期待を寄せました。彼は「地域でどのように社会に貢献していくのか、非常に興味があります」と述べ、今後の更なる活動へのエールを贈りました。地域の発展には大学や学生の役割が不可欠であることを改めて示す瞬間でした。
終わりに
今回のSDGs推進表彰を通じて、岡山大学が地域貢献を視野に入れた教育を行っていることが広く知られることとなりました。吉川教授の「地域の未来デザイン(実践編)」のような取り組みが、今後も学生たちにとっての貴重な教育の場であることを期待しています。地域社会の持続可能な発展を目指し、岡山大学の挑戦にぜひ注目してみてください。





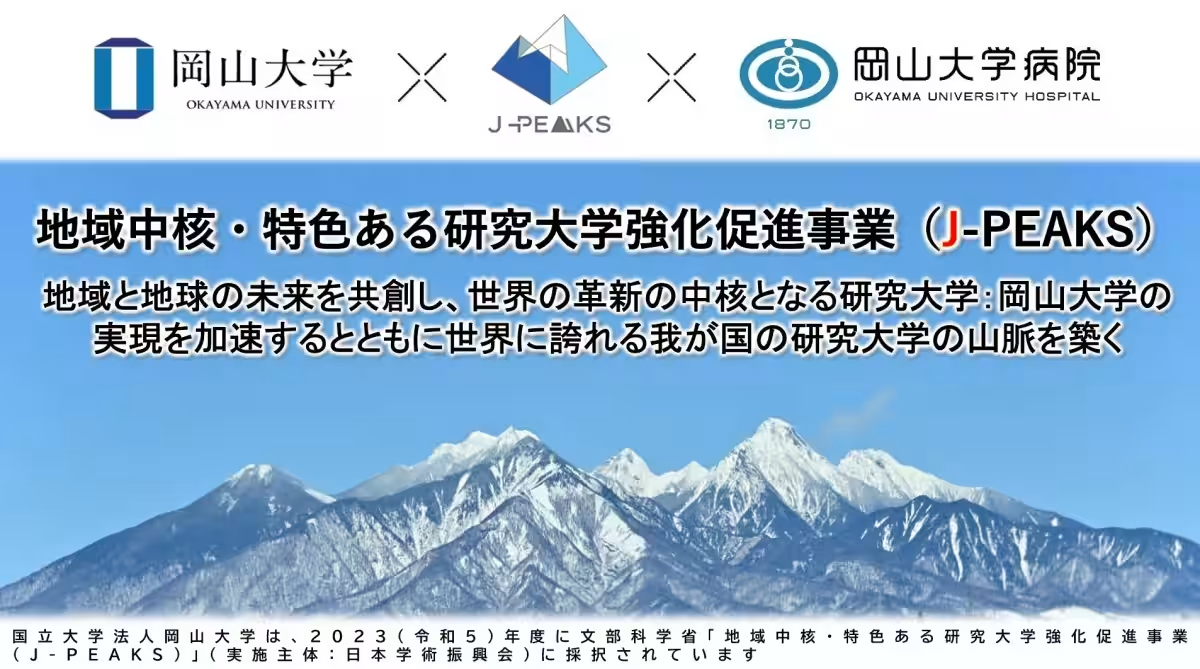


トピックス(イベント)


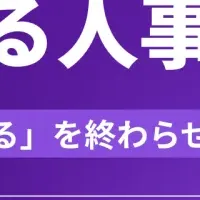
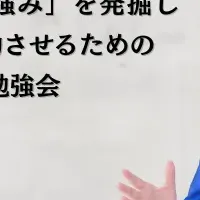
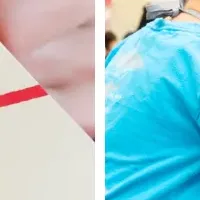

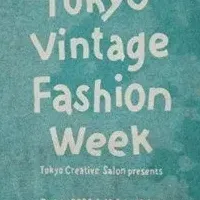



【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。