

日本テトラパックが描く資源循環の未来とその実現に向けた取り組み
日本テトラパックが描く資源循環の未来
2025年6月17日、日本テトラパック株式会社は大阪・関西万博の北欧パビリオンにて、資源循環をテーマにした特別なイベント「資源循環の未来:共創が生み出す新たな価値と可能性」を開催しました。このイベントは、食品加工業界で重要な役割を果たすテトラパックが資源循環の促進に寄与するための魅力的な場となりました。
産官学民の連携の必要性
このイベントでは、約40名の業界関係者が招待され、日本テトラパックの代表取締役社長であるニルス・ホウゴー氏が冒頭にオープニングメッセージを発表しました。彼は、2050年までのカーボンニュートラルの達成には、循環型経済の推進が不可欠であると強調し、さまざまなセクターとの連携を呼びかけました。「欧州の成功事例や国内の展望を通じて、協働の可能性を探求していきたい」との言葉が印象的でした。
各分野の専門家による現状分析
続いて、欧州製紙連合会の事務局長ヨリ・リングマン氏が基調講演を行い、欧州における資源循環の取り組み事例を紹介しました。特に、「4evergreen」のイニシアチブについて説明し、2030年までに紙の包装材料の90%をリサイクル対象とする動きなどが示されました。彼は、「循環性を改善するためには製紙業者とリサイクル業者の連携が必須」と訴え、システム全体を最適化する重要性に触れました。
テトラパックのサステナビリティ部門の副社長であるキンガ・シェラゾン氏は、食品産業が温室効果ガス排出量の大部分を占めている現状を解説し、循環型経済への移行が急務であることを訴えました。彼は特に「デザイン・フォー・リサイクリング」の取り組みを強調し、業界全体での連携の重要性を再確認しました。
島谷啓二氏(王子ホールディングス株式会社)も登壇し、日本の古紙リサイクル率が横ばいである現状を述べ、未利用古紙をすべてリサイクル可能にする取り組みが必要だと訴えました。共同で開発したアルミ付き紙容器の再資源化の取り組みについても触れ、リサイクルの促進は技術革新と広範な連携によって実現可能であるとしました。
パネルディスカッションでの活発な議論
イベント後半では、パネルディスカッションが行われ、「官民連携を通した紙製容器包装の循環型社会の実現」をテーマに、多様な視点から議論が交わされました。パネリストには、イクレイ日本の事務局長内田東吾氏、及び大本紙料株式会社の代表大本知昭氏、島谷啓二氏、そして日本テトラパックのサステナビリティディレクター大森悠子氏が参加し、それぞれ異なる立場から意見を述べました。ディスカッションでは、現場の課題や実践例が多角的に掘り下げられ、持続可能な資源循環に向けた具体的な行動の必要性が強調されました。
現状の理解として、内田氏は「自治体ごとにリサイクルが進みにくい状況」を指摘し、島谷氏は「技術革新が求められている」と述べました。また、大森氏は「市民の啓発と新たな再生品開発がカギ」とし、リサイクルの意識改革が必要であると強調しました。
結論と今後の取り組み
最後に、テトラパックの大森氏は、持続可能な社会の実現には、コミュニケーションの強化と技術革新、業界全体の柔軟な連携が不可欠であると締めくくりました。私たちが持続可能な未来を築くためには、共創を通じて、全てのステークホルダーが協力する必要があります。
このように、日本テトラパックの取り組みは、循環型社会の実現に向けて新たな可能性を開くものであり、今後の活動に注目が集まります。持続可能な資源利用やリサイクルの推進は、私たちの未来を守る重要なステップとなるでしょう。




トピックス(その他)

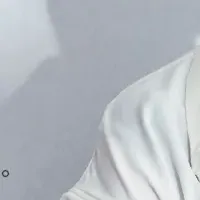
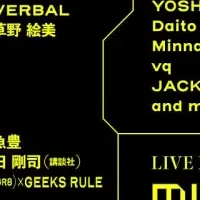







【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。