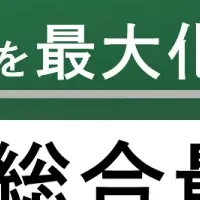
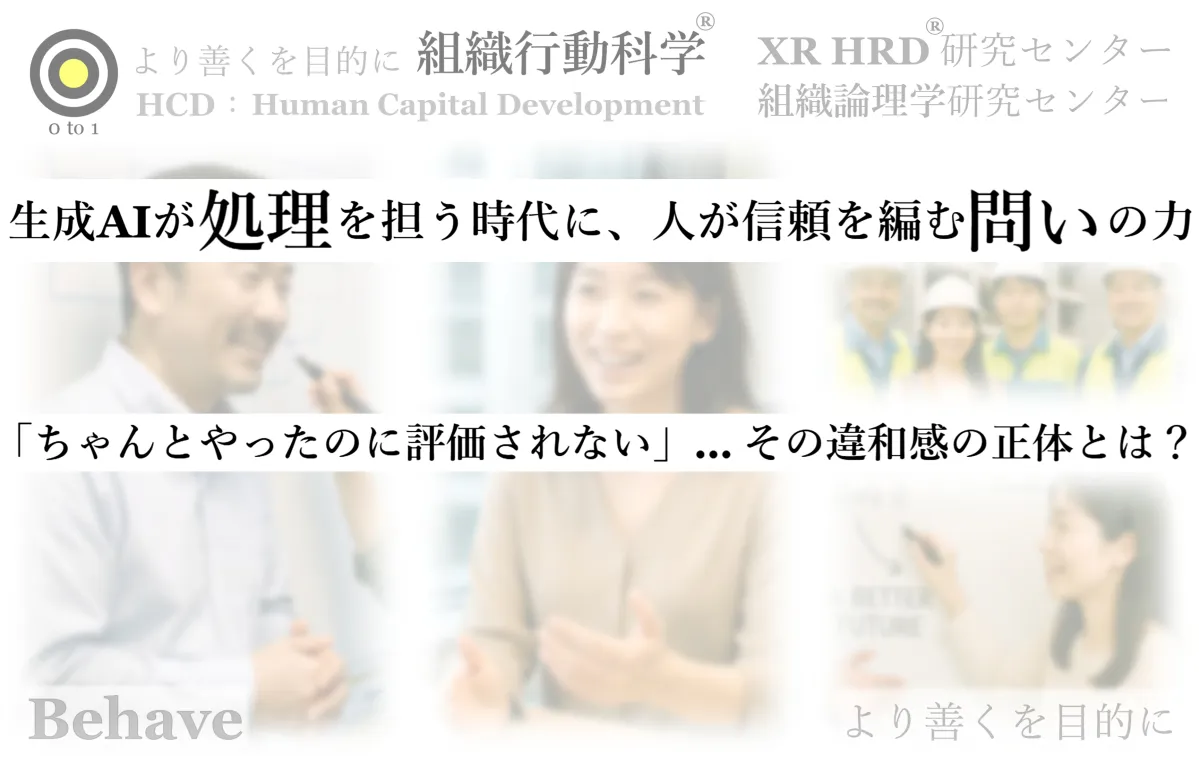
AI時代における評価の見直しと問いの力の重要性
AI時代における評価と問いの力
近年、ビジネス界でよく耳にするフレーズの一つが「ちゃんとやったのに評価されない」です。この評価されないという感覚は、果たして個々の能力に起因するものなのでしょうか。それとも、もっと深い要因が隠れているのでしょうか。リクエスト株式会社の提言書によれば、評価されない理由は「問いの主語」の未成熟にあるとされています。この観点から、生成AIが台頭する現代における人間の役割を考察してみましょう。
評価されない感覚の正体
「計画通りに終えたのに、なぜ評価が得られないのか?」
「丁寧さを持って対応したのに、なぜ取引が拡大しないのか?」
このような疑問は、私たちの行動そのものに対する大きな違和感を生み出します。この提言書では、まずこの評価されない感覚を解明することから始まります。ここで示唆されるのは、表面的な行動の結果ではなく、信頼を育む「問いの力」が重要であるという点です。
問いの主語の未成熟
信頼関係を構築するためには、自分だけでなく相手、さらには関係性や社会全体にまで視点を広げて問い直すことが求められます。具体的には、評価が得られない背景には「問いの主語の未成熟」が潜んでいます。まずは自己中心的な「自分」から出発し、その後に相手や関係性、さらには社会全体へと進む必要があります。このような問いを通じて、私たちはより広範な信頼を構築できるのです。
信頼は問いから生まれる
評価の制度が“何をしたか”といった行為や結果を重視するのに対し、実は“誰を善くしようとしたか”という問いの意図こそが、信頼を生む源泉であるとしています。この視点の逆転が、現代の組織に求められています。単に業務の遂行能力を向上させるだけではなく、信頼関係を育む「問いの文化」を育むことが不可欠です。
生成AIと人間の役割分担
さらに、生成AIが進化する今、人間と機械の役割分担も再考されてきています。AIはデータ処理やタスクの効率化に優れていますが、意味を考えたり、信頼関係を築いたりするのは依然として人間の役割です。このように、人間とAIの相互作用を知ることで、組織内の役割分担を見直すことができるでしょう。
組織に必要な問いの文化
リクエスト株式会社の提案するモデルでは、評価のプロセスに問いを取り入れることが推奨されています。しかし、これを如何に実行に移すのか。面談の問いや評価制度の接続ガイドなどを参考にしながら、具体的方法を探ることが重要です。
結論:あなたの問いが未来を切り拓く
最終的に、「あなたが大切にしてきた“正しさ”は、誰の善さにつながっていますか?」という問いを持ち続けることが、「信頼を編み直す」一歩となります。この問いが信頼を育む土壌となり、時代が求める「人にしかできない仕事」を見つけ出す手助けをしてくれるのです。また、この提言書は、業種を問わず「ちゃんとやってきたけれども報われていない」と感じている方々や、マネジメントに悩む方々にとっても価値のあるものとなっています。
このように、AI時代における信頼構築の方法を再考することで、新たな評価制度の可能性を見出し、明るい未来を築くことができるのです。
無料PDFダウンロードはこちらからできます。
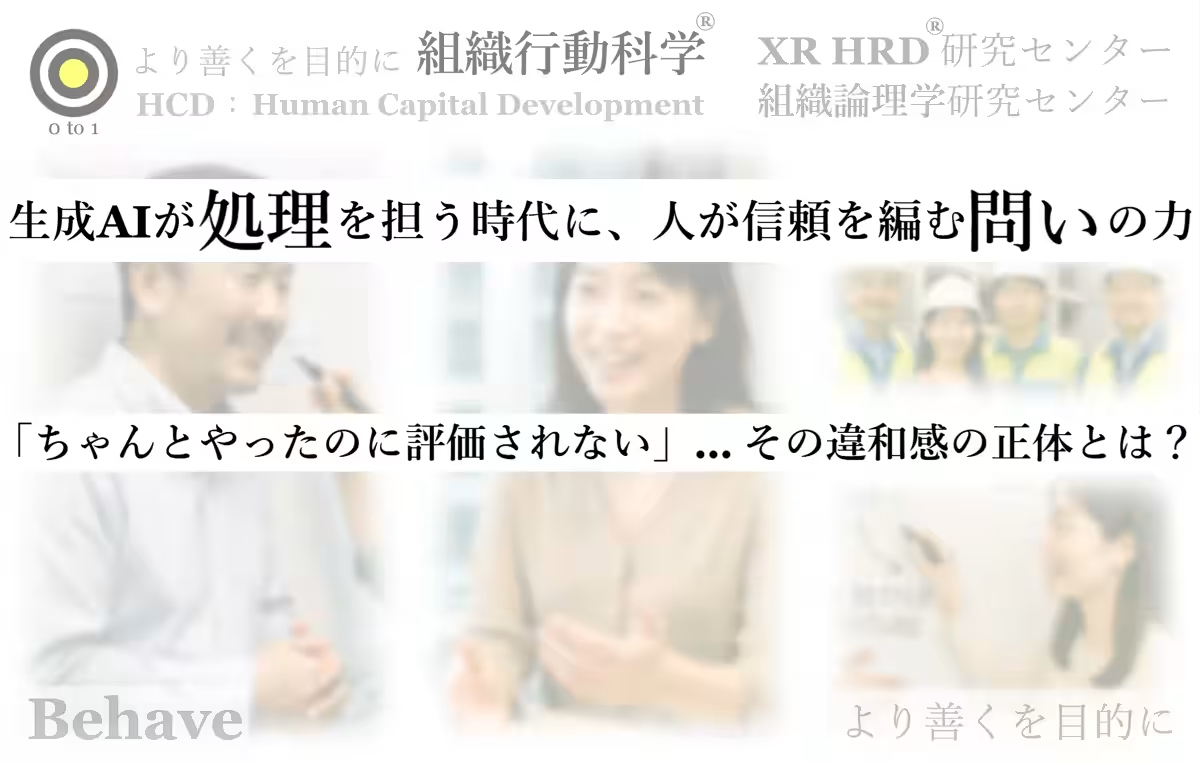

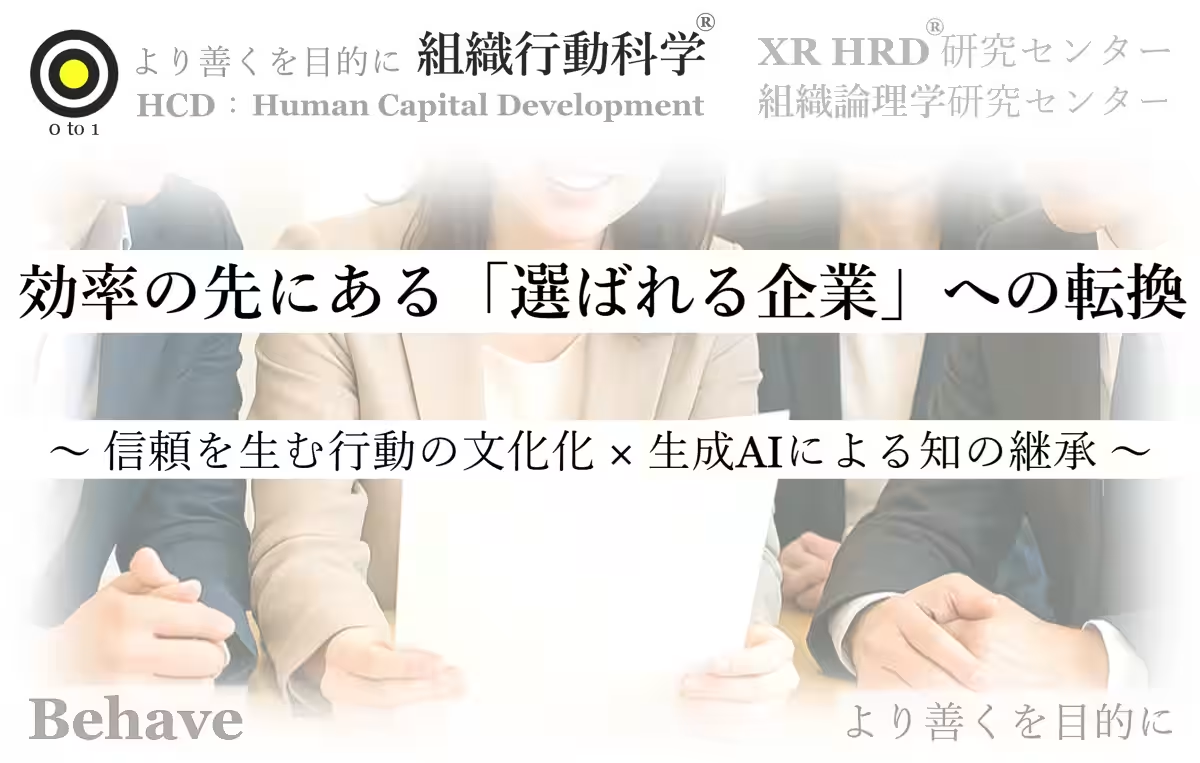
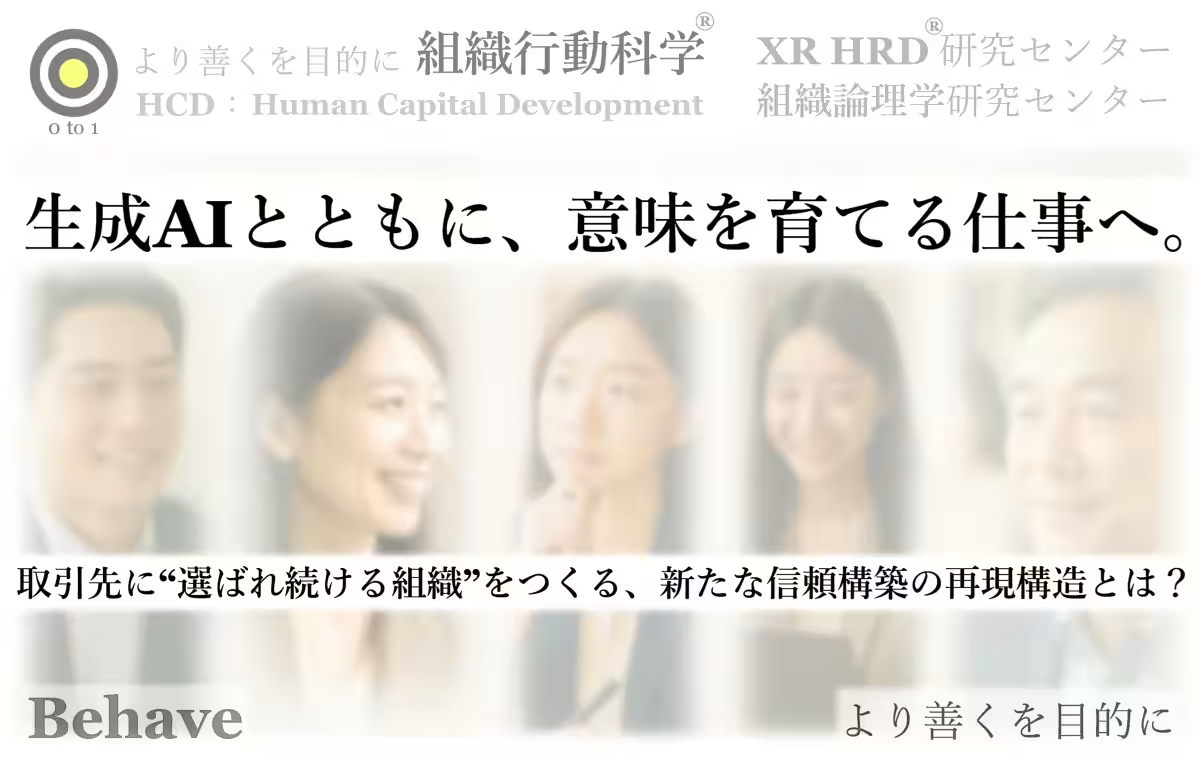
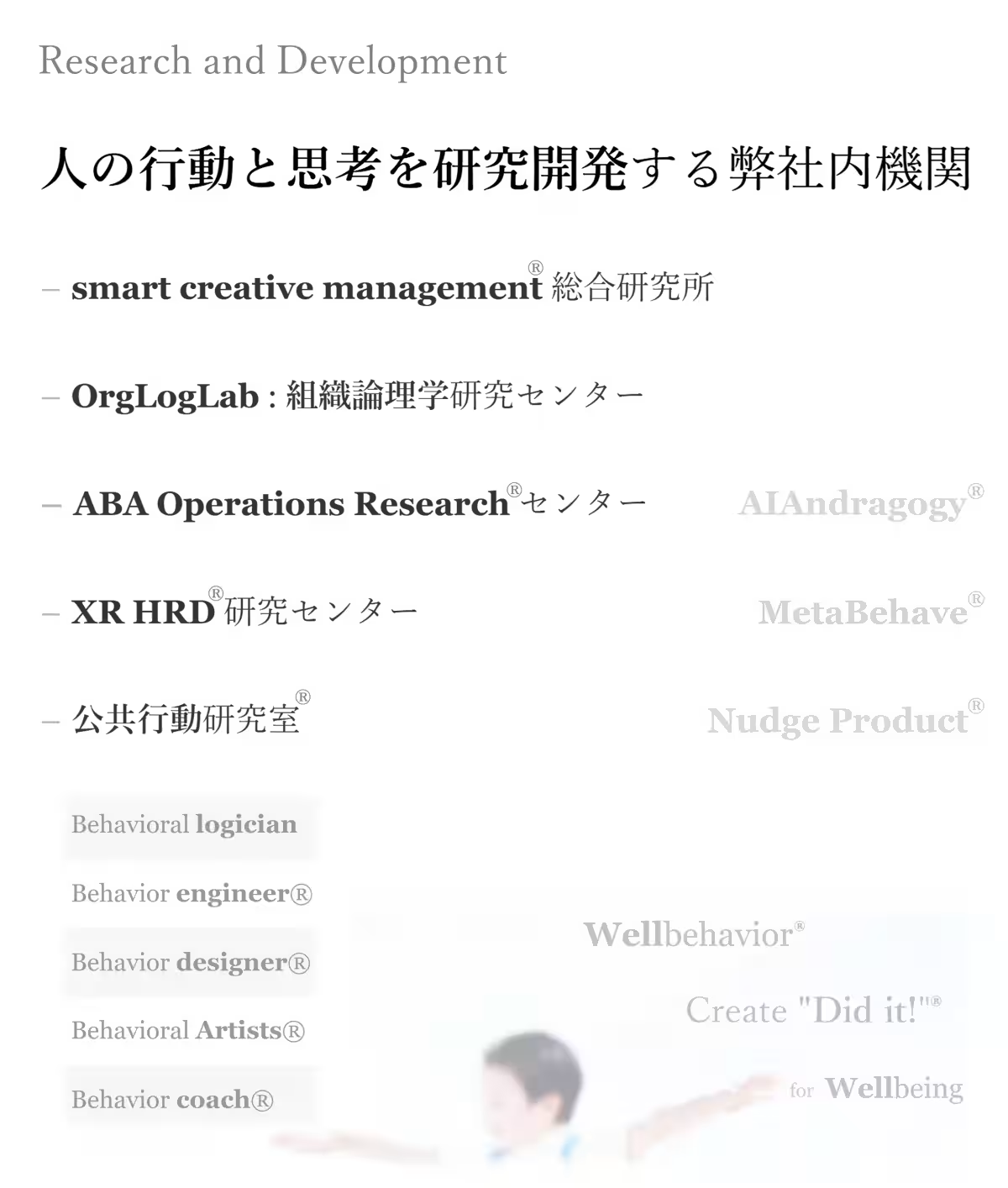




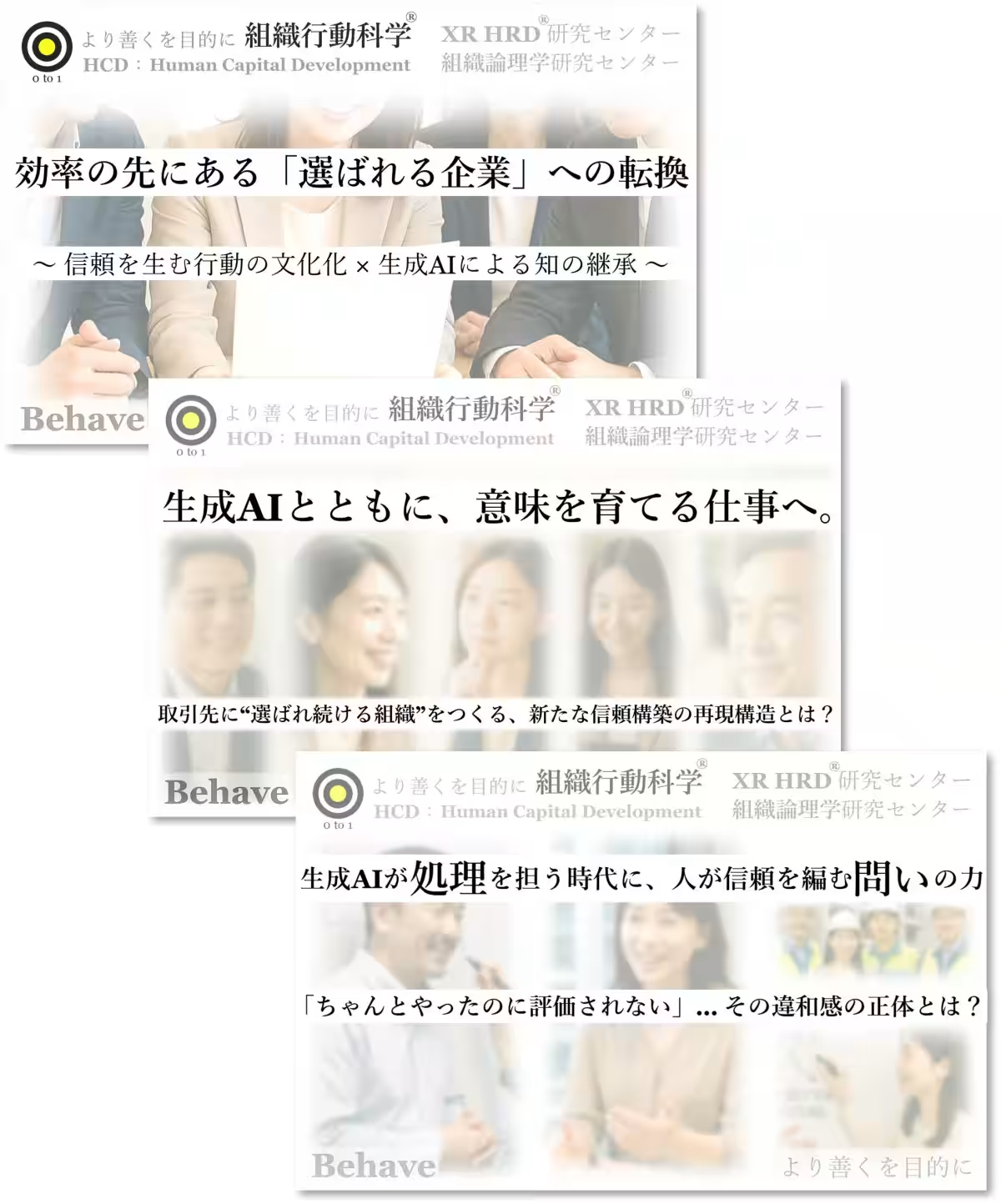
トピックス(その他)
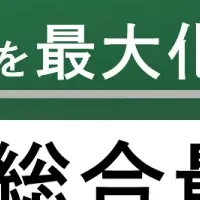
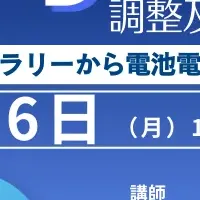




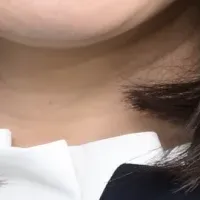



【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。