

「静かな退職」がもたらす新たな働き方とは?ディスコの取り組みを探る
「静かな退職」がもたらす新たな働き方とは?
「静かな退職」という言葉が近年注目されています。この現象は、社員が仕事に対する意欲を失い、表面上は働いているものの実質的には退職すると同様の行動を取る状態を指します。働き方の多様化に伴い、この現象の実践者が増えていると言われています。最近、Great Place To Work® Institute Japan(GPTW Japan)による「働きがいのある会社」ランキング発表の際、ディスコの赤瀬勝彦氏とGPTW Japanの荒川陽子によるトークセッションが開催されました。ここでは「静かな退職」に関する意識の乖離や、企業がどのように対応すべきかが話し合われました。
静かな退職の実態と意識の乖離
セッションが始まり、まず荒川氏は「『静かな退職』の実践者が増加しており、企業側はこの状況に対し何らかの対応策を講じなければならない」と強調しました。特に彼は、上司と現場社員の間に存在する意識の違いについても触れ、「両者間での連帯感や一体感に対する考え方にギャップがあり、これが静かな退職を引き起こしているのではないか」と指摘しました。
中でも、孤立を感じる社員が増える中で自分には関係ないと考えることで「静かな退職」を選ぶ人々が増えている点が、企業にとっての危機要因であるとされています。社員が自分自身の役割を見出し、職場での連帯感を感じられる環境が必要であるとの見解が示されました。
ディスコの取り組み
トークは続き、赤瀬氏からディスコの具体的な取り組みについて伺いました。ディスコでは社員が自ら部門や業務を選択できる「自由と信頼」の文化を推進し、さらに「個人Will制度」を導入しています。この制度では、社員は自分の意志で仕事に取り組み、その結果に基づいて評価される仕組みが整えられています。このように、自分の意志と能力を最大限に活かすことができる仕事環境が整備されていることで、社員の働きがいが向上しているのです。
具体的には、社員同士での合意によって業務が成り立つため、信頼関係の構築にもつながります。この文化が定着することで、自然と社員の間で期待をかけ合う好循環が生まれていることが、赤瀬氏の説明からわかりました。
今後の企業の対応策
最後に将来的な展望についても意見が交わされました。赤瀬氏は「今後は社内制度を見直し、静かな退職を避ける仕組み作りが求められる」とし、荒川氏も「企業と社員、互いに期待をかけあう関係性を築くことが重要だ」とまとめました。
このように「静かな退職」という現象が今後どのように展開していくのか、企業はどのように対応していくべきなのかを考えることが求められています。ディスコの取り組みは、社員が生き生きと働ける環境の一つのモデルケースとして注目を集めそうです。
トピックス(その他)

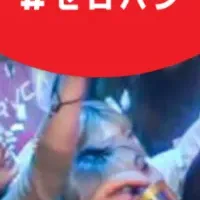




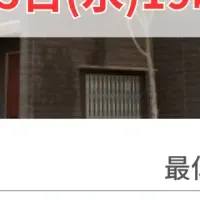



【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。