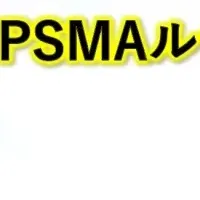

サステナビリティの未来を見据えたカンファレンス開催レポート
Booost サステナビリティカンファレンス開催レポート
2025年4月15日、品川にあるグロービス経営大学院で「Booost サステナビリティカンファレンス」が開催されました。このカンファレンスは、企業のサステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)における最新の議論を集約する重要な場となりました。特に、世界的なESG政策転換の流れや新たな開示制度の導入がもたらす影響についての考察が行われました。
カンファレンスの目的と背景
Booost株式会社(旧社名booost technologies)は、サステナビリティ経営の促進を目指し、企業が直面する課題や求められる対応策について情報を共有しました。特に、2026年4月に義務化される開示制度については、日本企業にとっての重要な転機であると強調されました。代表取締役の青井宏憲氏は、企業経営の変革が不可欠であるとし、SXを企業価値の向上につなげるドライバーとして捉えるべきだと述べました。
オープニングセッション
オープニングでは、青井氏が「経営そのものの変革が求められている」との見解を示しました。彼は、単なる制度対応にとどまらず、経営者が積極的にリードする重要性を訴えました。また、この日をもって社名および製品名を変える決定とも相まって、企業の新たなスタートを告げました。
トークセッション
トークセッションでは、グッドスチュワードパートナーズの水野弘道氏と大我猛氏による議論が展開されました。彼らは、米国のESG逆風と欧州の規制緩和の状況を踏まえ、日本企業が何をすべきかを詳しく分析しました。水野氏は、「ESGはリスクへの対応であり、短期的コストではない」と述べるとともに、日本企業が今こそESGへの取り組みを強化するチャンスであると強調しました。
基調講演
続いて、公認会計士の森洋一氏による基調講演が行われました。森氏は、「開示は目的ではなく、企業戦略に統合されるべきだ」とし、財務と非財務の統合的理解の重要性を訴えました。企業はサステナビリティのリスクを経営にどう組み込むかを学び、実践していく必要があると強調されました。
実務セッション
実務セッションでは、大我猛氏が具体的な現場の課題と、サステナビリティに関するテクノロジーの活用例について紹介しました。特に、企業が直面する開示関連の負担を軽減し、効率化を図る方法が示され、実際に成功した事例も紹介されました。
パネルディスカッション
パネルディスカッションでは、牛島慶一氏をモデレーターに、森氏と青井氏が再度議論を深め、「情報開示を超えた企業価値向上の実践」がテーマとなりました。彼らは、企業が差別化された開示を行うことで、長期的に価値を生み出すための独自性の確保が必要であると語りました。
まとめ
カンファレンスを通じて、制度対応にとどまらず、サステナビリティを未来の成長につなげるための積極的な戦略が求められているというメッセージが強く印象付けられました。各企業が持続可能性に向けた真剣な取り組みを行うことで、経営者の姿勢が企業価値の向上に直結することが強調されました。この重要な議論の場は、今後のサステナビリティ経営における指針となることでしょう。



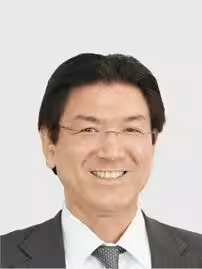






トピックス(その他)
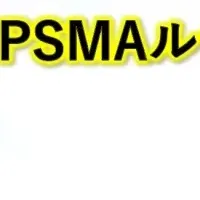

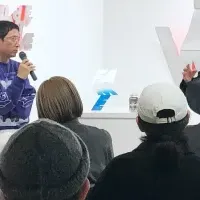
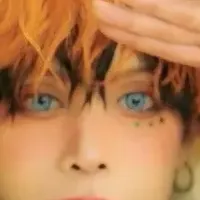

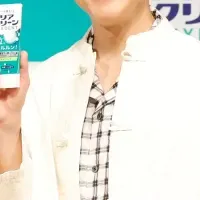


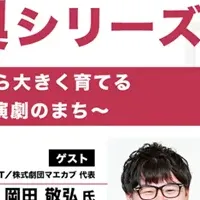

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。