
令和の新たな脅威!人名型ハラスメントの実態と対策
令和の新たな脅威!人名型ハラスメントの実態と対策
近年、ハラスメントという言葉が一般的に浸透してきましたが、その形態は多様化しています。特に最近、注目を集めているのが「人名型ハラスメント」です。この現象は、特に若者を中心に流行しており、「ウエハラ」、「エビハラ」、「タメハラ」といった名称が次々と生まれています。これらの言葉は、従来のハラスメントの概念を軽やかに、かつ分かりやすく表現する手段として具現化されています。
新たなハラスメントの形
一般社団法人クレア人財育英協会によると、職場や日常生活でこの「人名型ハラスメント」が増加しているという報告があります。たとえば、ある発言が「エビハラ」によって議論されることで、共感を得たり、逆に軽く処理されることがあります。 具体的には、「タメ口で距離を詰められるのが辛い」と感じた人が「それ、タメハラだよね」と言った瞬間に、共感が生まれるという事例が報告されています。
このように、「名前を付ける」ことで、言いづらい問題でも話しやすくなり、人間関係を保つ役割を果たしています。
ハラスメントの種類
クレア人財育英協会によると、主に以下の3つのタイプに分類されます:
1. ウエハラ: 自分の経験を通じて相手に助言をする際、上下関係を意識させる言動が特徴です。例として、「私も若い時にしたけど、お前にはまだ早いかも」といった発言が挙げられます。
2. エビハラ: 相手の感情に対して論理で攻め、気持ちを無視するような圧力をかけるスタンスです。「その例えにはデータが必要」「ちゃんとした根拠を出してから意見して」といった言葉遣いが見受けられます。
3. タメハラ: フレンドリーさを強調するあまり、関係を急に近づけることで、相手を戸惑わせる行為です。「もっとタメ口で話そう?」というアプローチが該当します。
言語化の有効性
これらの言葉が流行する理由は、彼らが人名のように使われることで、重くなりすぎず、軽妙にコミュニケーションを図れるからです。 たとえば、「またウエハラが発生した」と冗談として扱われることで、相手の行動について笑い合うことができるようになります。これにより、加害と被害を明確に区分せず、関係性における違和感を共感し合うことが可能になります。
取り組みと教育
これに伴い、クレア人財育英協会は「雇用クリーンプランナー」というハラスメント対策資格を設立しました。この資格は、パワハラやセクハラなど基本的な知識だけでなく、日常的な人間関係の違和感を捉えそれに対処する力を養成します。受講や試験は全てオンラインで行われ、すでに500名以上の修了者が、全国各地で活躍しています。
まとめ
「人名型ハラスメント」は単なる言葉遊びではなく、職場や日常での関係性を円滑にする新たなコミュニケーションの形でもあります。今後、この考え方が職場内でのコミュニケーションをより良いものにする手助けになることでしょう。詳細な情報や資格取得に興味がある方は、こちらのリンクをご覧ください。
トピックス(その他)

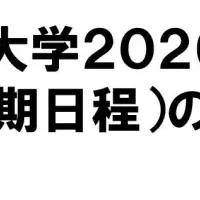
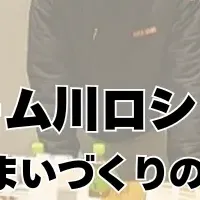
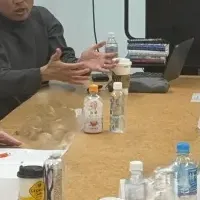
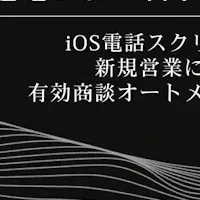

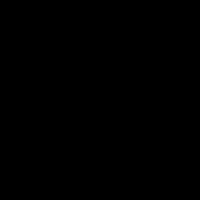



【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。