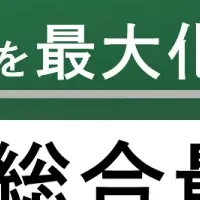

正解依存を超え、未知の問いに挑む力を育む新たな指針
正解依存を超えた新しい思考様式の提案
最近、リクエスト株式会社が発表した最新レポート『なぜ、正解を求めるのか?』では、組織内の95%以上が正解依存に陥っている現実を浮き彫りにしました。人々が「唯一の正解」を求める傾向は、教育や社会環境によって培われたものであり、結果として未知の問いに挑戦する力が失われつつあると言われています。
正解依存の根幹とは
人は「不確実性」に対する不安回避の心理から、未知の問いを避け、明確な答えを求めるという傾向があります。例えば、学校での試験や評価の多くは「正解」が存在することを前提にしているため、学習者は「考える」というプロセスよりも、目先の正解を当てることに重きを置いてしまいます。このようにして形成された思考の癖は、大人になってからも影響を及ぼし、職場環境でも同じことが繰り返されるのです。
一方で、正解にたどり着くことによって得られる快感は、一時的ではあるものの非常に強力です。正解を得ることで「当たった!」という感覚がもたらされ、これが習慣化していくわけです。しかし、正解のない問いに対しては、報酬を得るための道のりが不透明であり、努力が実を結ぶかどうかも分からないため、多くの人が敬遠してしまいます。
正解依存が引き起こす問題
リクエスト社の研究によると、組織の95%以上が正解依存に分類され、その内訳は制度依存型が約50%、日和見型が25〜30%、役割未定型が17〜20%を占めています。このような状況下で、真に「正解のない問い」に挑める人材はわずか5%未満であるという現実は、企業の成長戦略にも大きな影響を与えるでしょう。
特に、競争の激しい環境下では、チャレンジャー企業やリーダー企業においては非定型的な課題に挑む人材育成が不可欠です。正解依存のままでは、新たな市場のリーダーになることは難しいでしょう。すると、どのようにして「正解のない問い」に向き合える人材を育てることができるのでしょうか?
組織行動科学®に基づく実践指針
レポートでは「定型業務」と「非定型業務」の比率の重視が提唱されています。日常業務の70〜90%を定型タスク、10〜30%を非定型課題として設計することで、未知の問いへの挑戦が促進されるというのです。さらに、フィードバックは「間違いの指摘」ではなく、「問いを深める対話」が重要です。上司や人事部門の関与が不可欠であり、彼らのサポートを通じて、社員が自身の意思で挑戦する環境を整えることがカギとなります。
未来を切り開くために
組織における正解依存の弊害を理解し、正解のない問いに挑む習慣を根付かせることで、より強いリーダーシップが生まれるとリクエスト社は示しています。「正解依存が大多数を占める現実」の中で、如何にして未知の問いへの挑戦を行う人材を育むのか。このプロセスこそが、未来を切り開く人的資本開発の根幹であり、今後の企業競争に不可欠な要素となるでしょう。
詳細な内容に関しては、リクエスト社の公式ウェブサイトにてご確認ください。


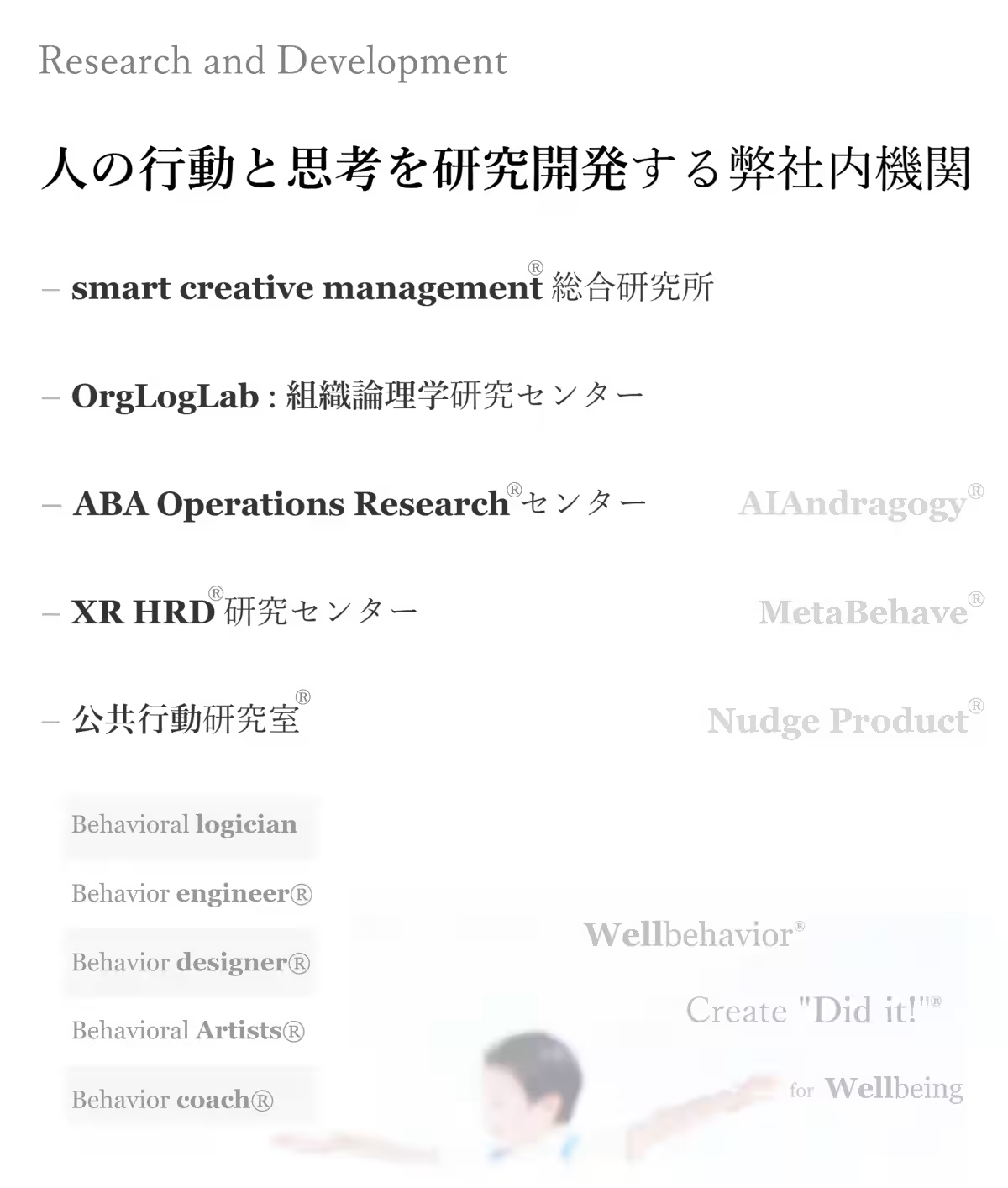
トピックス(その他)
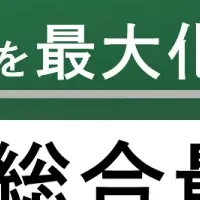
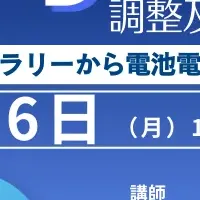




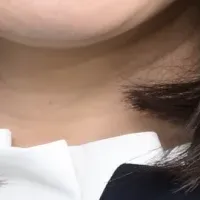



【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。