

理系専門人材の未来を展望する産官学ラウンドテーブルが開催されました
理系専門人材の未来を展望する産官学ラウンドテーブルが開催
理系専門人材は、AIやデジタル社会の進展、そして環境問題の解決において重要な役割を果たす存在です。しかしその一方、日本における理系人材の就職環境は依然、厳しい現実に直面しています。2025年8月27日(水)、株式会社LabBaseが主催した『理系専門人材の活躍について考える、産官学ラウンドテーブル』は、そのような現状に対し、産業界とアカデミアが協力し、共通の課題を解決するための場を提供しました。
ラウンドテーブルの概要
今回のイベントでは、理系人材の採用・育成について多角的な視点から議論が行われました。主催のLabBaseは、「研究の力を、人類の力に。」という壮大なパーパスを掲げ、研究を支えるプラットフォームの重要性を強調。理系人材がいかにして社会と結びつくかが焦点となりました。
さまざまな分野から専門家が集まり、それぞれの視点での議論が行われました。特に、博士人材のキャリアパスや研究と就職活動の両立については、現場からの実体験を交えながら活発に意見交換が行われました。
講演者の声
基調講演を行った山中直明氏(慶應義塾大学教授)は、日本の就職活動が抱える問題について厳しく指摘。「卒業論文や修士論文は、単なる成果物ではなく、思考力を養うための貴重な教育の機会です」と述べ、日本特有の初任給制度には柔軟な見直しが必要であると提言しました。また、留学生の就職率の低下に触れ、日本の人材活用の不十分さを考える新たな視点を提供しました。
企業側の取り組み
富士通の天谷氏は、自社のジョブ型人材マネジメントについて説明しました。年功序列からジョブレベル基準の報酬制度への移行を果たし、博士人材の育成へも力を入れているとのこと。採用においても人員計画に依存せず、必要なジョブを前提にした逆算採用を強調しました。
資生堂の山本氏は、社員が主体的にキャリアを形成できる「セルフリーダーシップ」の重要性を語り、完全な職種別採用を導入している旨を伝えました。特に理系学生への柔軟なスケジュール設定が評価され、学生が研究に専念できる環境を整えていることが印象的です。
リコーの深瀬氏はスカウト型採用を通じてマッチングを深める取り組みを紹介。実際に学生と企業双方が納得の上でご縁を結ぶことが大切だと強調しました。
未来へ向けて
最後にLabBaseの加茂氏は、理系人材がキャリアと研究を両立できる社会の実現に向けて、産官学が連携することの重要性を語りました。何より、学生を取り巻く環境を改善し、理系人材が日本のイノベーションを支える未来を切り拓くための協力が現在求められています。
このラウンドテーブルは、理系人材の未来を考える啓発の場となり、さまざまな視点からの意見交流によって、新たな道筋が見つかる一歩となったことでしょう。今後も理系人材の就職・採用・育成における変革が期待されます。











トピックス(その他)









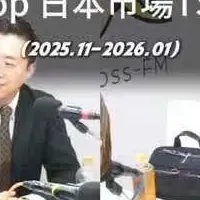
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。