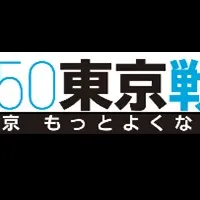

防災食品の循環モデルを築くフードバンク愛知の取り組み
防災食品の循環モデルを築くフードバンク愛知の取り組み
防災対策がますます重視される今日、企業や自治体が備蓄する非常食の管理は大きな課題となっています。賞味期限を迎えた防災食品の入れ替えに伴い、数百食から数千食もの非常食が廃棄されるケースが多く見られます。この課題に取り組む非営利団体、フードバンク愛知は、廃棄される食品を地域社会に役立てる循環モデルを提案しています。
防災フォーラム2025への出展
フードバンク愛知は、2025年10月10日(金)に東京・千代田区で開催される「防災フォーラム2025」に出展します。このイベントは、防災用具や備蓄品の整備からBCP(事業継続計画)の策定まで、企業や自治体が非常時の準備を万全に整えるための情報交換の場を提供しています。
フードバンク愛知は、賞味期限を迎えつつある非常食の廃棄を防ぐ方法として、リユースの仕組みを紹介し、参加企業や自治体に貢献する方法を提案します。
企業と自治体が直面する課題
備蓄されている非常食の中には、入れ替えの際にまだ食べられる食品が多く含まれていますが、これらが廃棄されることは、企業や自治体にとって大きな負担となります。以下に主な課題を挙げてみましょう。
1. 廃棄コスト
大量の食品廃棄には、処理費用や運搬費用が必要で、これが数十万円から数百万に達することもあります。
2. 環境負荷
食品が廃棄されることは、二酸化炭素の排出を伴い、SDGsやCSRの観点からも問題視されています。
3. 社会的イメージ
食べられる食品を廃棄することが引き起こす批判や、担当者にかかる心理的負担は無視できません。
4. 調整の手間
少量の商品を寄贈したい団体が多く、調整に手間がかかり、その調査にも時間が必要です。
このような課題から、防災フォーラムでのフードバンク愛知の出展が注目されています。フードバンクは、独自のネットワークを通じて、大量の食品を一括で受け入れるシステムを構築できます。これにより、企業や自治体は廃棄を防ぎ、必要とされている場所に支援を届けることが可能です。
フードバンク愛知の特徴
フードバンク愛知は、愛知県を拠点として食品ロスの削減と生活困窮者支援を両立させるために活動しています。その特色を以下に示します。
- - 全国ネットワーク
- - 支援先の多様性
- - 柔軟な対応
この体制が、企業や自治体の防災備蓄食品の寄付を支えています。安全で高品質な食品のみを受け入れており、事前に確認を行いますが、期限が迫っているものの受け入れも応相談です。
フードバンク愛知のブースでの紹介内容
「防災フォーラム2025」では、フードバンク愛知の情報ブースで以下の内容を紹介します。
- - 防災食の寄贈の流れ(企業・自治体 → フードバンク → 地域支援)
- - 備蓄品のバリエーション増を実現するローリングストックの提案
- - フードロスを減らし支援を両立させる方法
- - 実際の支援事例と感謝の声
- - 寄贈先を報告する活動報告書のサンプル
訪れる方々は、廃棄されるつもりだった非常食がどのように地域に役立つのかを学ぶことができる内容になっています。
最後に
フードバンク愛知の取り組みは、廃棄を避け、支援に結びつく循環効果を生むものです。今年の防災フォーラムでは、参加者とともにこのモデルをより具体化し、社会に貢献する方法を探ります。ぜひ、実創の現場を一緒に体験し、今後の防災のあり方を考えてみませんか。


関連リンク
サードペディア百科事典: 食品ロス削減 防災フォーラム2025 フードバンク愛知
トピックス(イベント)
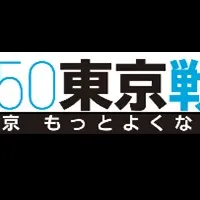


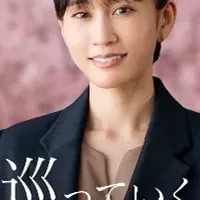






【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。