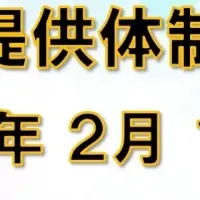

食料システム法による持続可能な食料供給を目指す新制度の開始
食料システム法による新たな支援制度がスタート
令和7年10月1日より、農林水産省は新しい「食料システム法」に基づく計画認定制度の運用を開始します。この制度は、持続可能な食料供給の確保を目指して、食品事業者の各種取り組みを幅広く支援するためのものです。これを契機に、農林漁業者と食品産業との連携を強化し、地域全体で持続可能な食料システムを構築していくことが求められています。
1. 食品事業者の取り組みの認定
食料システム法では、安定した取引関係の確立や流通の合理化、環境への負荷軽減、消費者の理解促進など、持続可能な食料供給に寄与する施策を幅広く認定する制度が設けられています。この認定を受けると、株式会社日本政策金融公庫からの低利融資や、農業・食品産業技術総合研究機構からの設備供用、さらには税制特例など多岐にわたる支援を受けられます。
持続可能性を重視した取り組みを行う食品事業者には、ぜひこの計画認定制度の活用を検討してもらいたいと思います。詳細な情報は、農林水産省の公式ホームページに掲載されています。
計画認定制度の詳細はこちら
2. 地域との連携支援
持続可能な食料システムの構築には関係者の連携が不可欠であり、食料システム法においても、地方自治体などの支援機関がコンソーシアムを形成し連携して支援する取り組みを認定しています。食品事業者を支援する団体や機関の皆さまには、連携支援事業の認定をぜひご検討いただきたいです。
連携支援の詳細はこちら
新たに設立される「地域食料システム構築・連携推進プラットフォーム」では、関係者の協力を通じて持続可能な食料システムの構築を推進します。
プラットフォームに参加したい方はこちら
3. 消費者理解を深める広報活動
農林水産省は、消費者や食料システム関係者が「フェアな値段」の考え方を理解できるよう、広報活動「フェアプライスプロジェクト」を展開しています。動画コンテンツやイベントを通じて、消費者が生産者の声を聞き、理解を深める機会を提供しています。
さらに、「値段のないスーパーマーケット」といった消費者参加型イベントのWeb版も用意されており、直感的に消費者が「フェアな値段」を考えることができる体験が可能です。
フェアプライスプロジェクトの詳細はこちら
4. 今後の取り組み
令和8年4月から施行される合理的な費用を考慮した価格形成に向けて、全国の地方農政局ではフードGメンを配置し、取引実態調査を行う予定です。これは、農林漁業者や食品事業者の方々にとってリアルな取引実態を把握し、協力をお願いするためのものです。
フードGメンについての詳細はこちら
地域を越えたネットワークの強化と、持続可能な食料供給の取り組みがこれからの社会にとって新たなスタンダードとなるよう、農林水産省は引き続き尽力していきます。興味のある方は、ぜひ公式サイトをご覧いただき、一緒にこの取り組みを盛り上げていきましょう。
関連リンク
サードペディア百科事典: 持続可能な食料 食料システム法 フェアプライスプロジェクト
トピックス(その他)
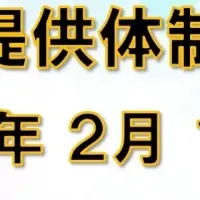
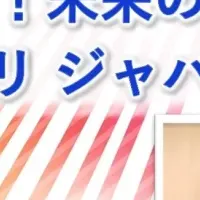
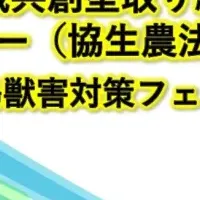
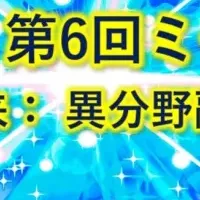
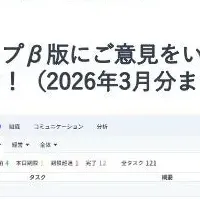

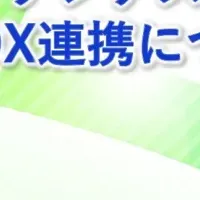

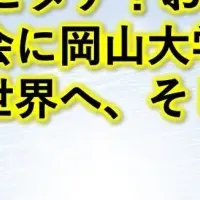
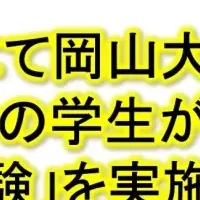
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。