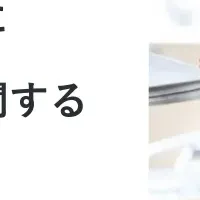
建設業の動向を探る:令和7年5月の受注状況を徹底解説
建設業の動向を探る
令和7年7月10日、国土交通省は「建設工事受注動態統計調査報告」の最新データを公開しました。この報告では、建設業界の受注状況を総括し、公共及び民間からの受注額を業種や地域別に整理しています。本記事では、この報告内容を詳しく解説し、建設業業者や関係者が知っておくべきポイントを紹介します。
受注動向の意義
建設工事受注動態統計調査は、我が国の建設業者にとって極めて重要な報告です。調査対象には約48万業者が登録されていますが、その中から毎月1万2千社が選ばれ、受注状況が詳しく把握されます。この情報は、建設行政や経済政策を検討する上での基礎データとして重要な役割を果たしています。
令和7年5月の受注状況
令和7年5月の調査報告によれば、受注高は地域や業種に応じて異なる動きを見せています。特に公共工事の発注については、各地方自治体が予算を投じることで一定の需要が保たれています。一方で、民間の受注に関しては慎重な動きが見られ、投資の方向性が注目されています。
地域別の分析
受注高は地域ごとにも異なり、各地方の経済活動や需要に大きく左右されます。特に大都市圏では、再開発や新しいインフラ整備が進んでいることから、受注高が相対的に高い傾向があります。また、地方では公共工事の需要に依存する傾向が強く、地域によっては受注件数が減少しているケースも見受けられます。
業種別の違い
さらに、受注状況は業種ごとにも明確な違いを示しています。例えば、土木工事や建築工事ではそれぞれ異なるマーケットの動きが見られ、業種ごとの特性を理解することが経営判断にも影響を与えます。このため、各業種の専門家にとって、このデータは経営戦略を立てる際の重要な材料となります。
今後の Outlook
新しい推計方法が導入されたことにより、今後の受注動向の予測精度も向上することが期待されます。次回の調査結果には、より詳細な情報が盛り込まれる見込みです。これにより、建設業界全体のトレンドをつかむための貴重な指標となるでしょう。
まとめ
令和7年5月の建設工事受注動態統計調査結果は、建設業者や関係者にとって必見の内容です。受注動向を把握することで、経営戦略をより明確にし、今後の市場を見据えた施策を講じることができるのです。今回の結果を参考に、自社の戦略を見直していくことが求められます。
トピックス(その他)
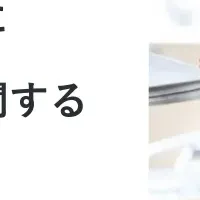


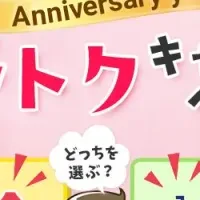
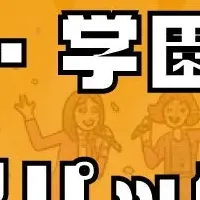
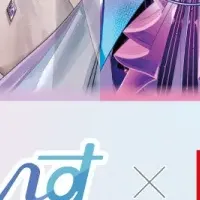
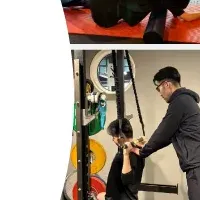
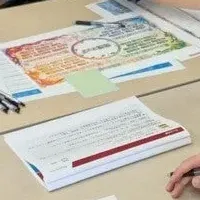
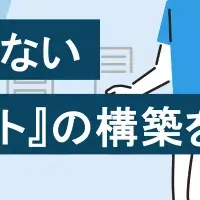

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。