
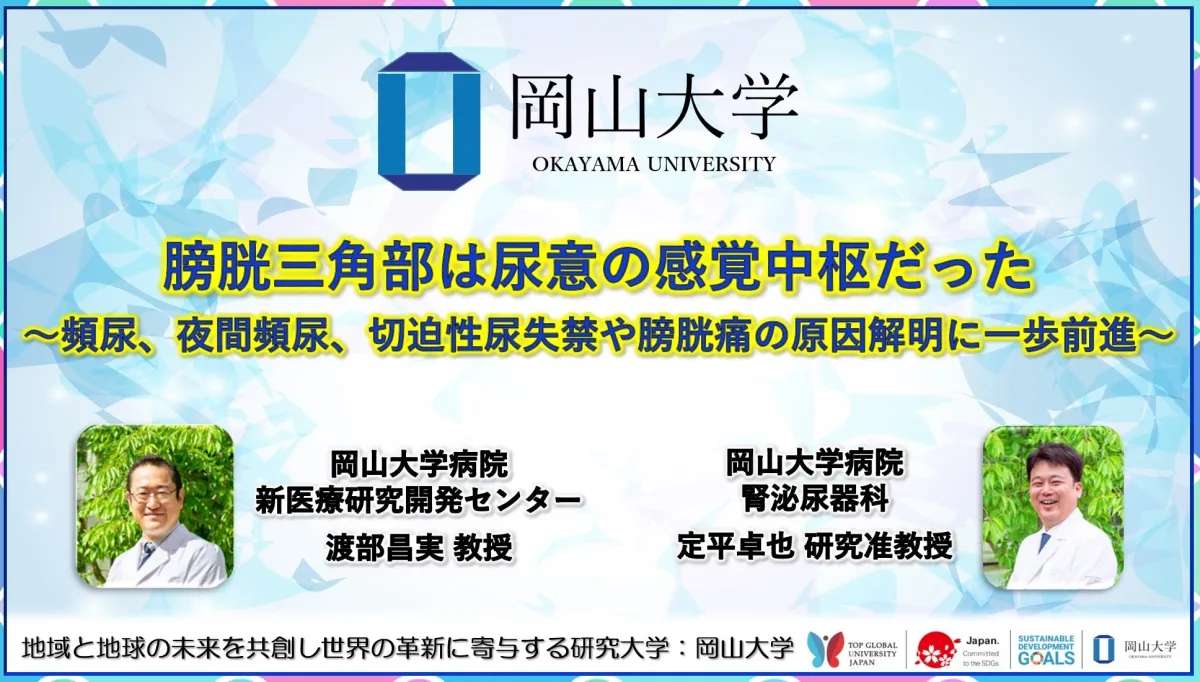
岡山大学が明らかにした膀胱三角部の感覚特性とその治療可能性の研究
膀胱三角部の新しい発見
岡山大学の研究チームが膀胱内での尿意を感知する中心としての膀胱三角部の機能についての重要な発見を発表しました。この研究は2025年11月に、アメリカの医学雑誌「Cureus」で掲載されました。さらに、同研究は膀胱の感覚神経の構造と機能、臨床的意義を網羅的にまとめたレビューであり、学界でも注目されています。
膀胱三角部の重要性とは?
膀胱三角部は、膀胱の出口側に位置する三角形状の領域で、他の部分に比べて特に密集した神経網を持っています。この神経群は、尿意や膀胱痛を中枢神経系に伝達する役割を担っており、そのため、この部位の感覚異常が、頻尿や切迫性尿失禁、さらには間質性膀胱炎の発症と密接に関わっているのです。
神経受容体の役割
研究によれば、膀胱三角部には、尿意に関与するいくつかの重要な神経受容体が高密度に存在することが特定されました。例えば、PIEZO2という機械刺激受容体、P2X3というプリン受容体、TRPV1というカプサイシン受容体の発現が顕著で、これらが過活動膀胱や膀胱痛のメカニズムに大きく寄与しているとされています。
新たな治療法の開発の可能性
本研究では、膀胱三角部の感覚機能を理解することで、新しい治療戦略の開発が期待されると述べられています。その一つとして、岡山大学が取り組む「ETA頻尿治療」などが挙げられ、膀胱における感覚神経の過剰な興奮を抑制する薬剤が有効なアプローチになる可能性があります。
臨床の現場での適用
渡部昌実教授は、長年の臨床経験から、この膀胱三角部の感覚メカニズムの解明が、今後の新しい治療法の基盤になると期待を寄せています。特に頻尿や膀胱痛で悩む患者の生活の質を改善するための治療法が、近い将来に実現する可能性があると考えられています。
膀胱の新しい視点
定平卓也研究准教授によれば、膀胱はただの尿を貯める器官ではなく、非常に精巧な感覚器官であることがわかりました。今後の研究では、膀胱の尿意を感じるメカニズムをさらに解明し、尿意を効果的に管理するための治療法を開発することが目指されています。
まとめ
岡山大学の今回の研究成果は、医療面での新たな道を開くものです。今後の研究や治療の進展により、頻尿や膀胱痛に悩む多くの人々に希望をもたらすことが期待されます。研究の詳細な情報は、岡山大学の公式ウェブサイトでも確認できます。
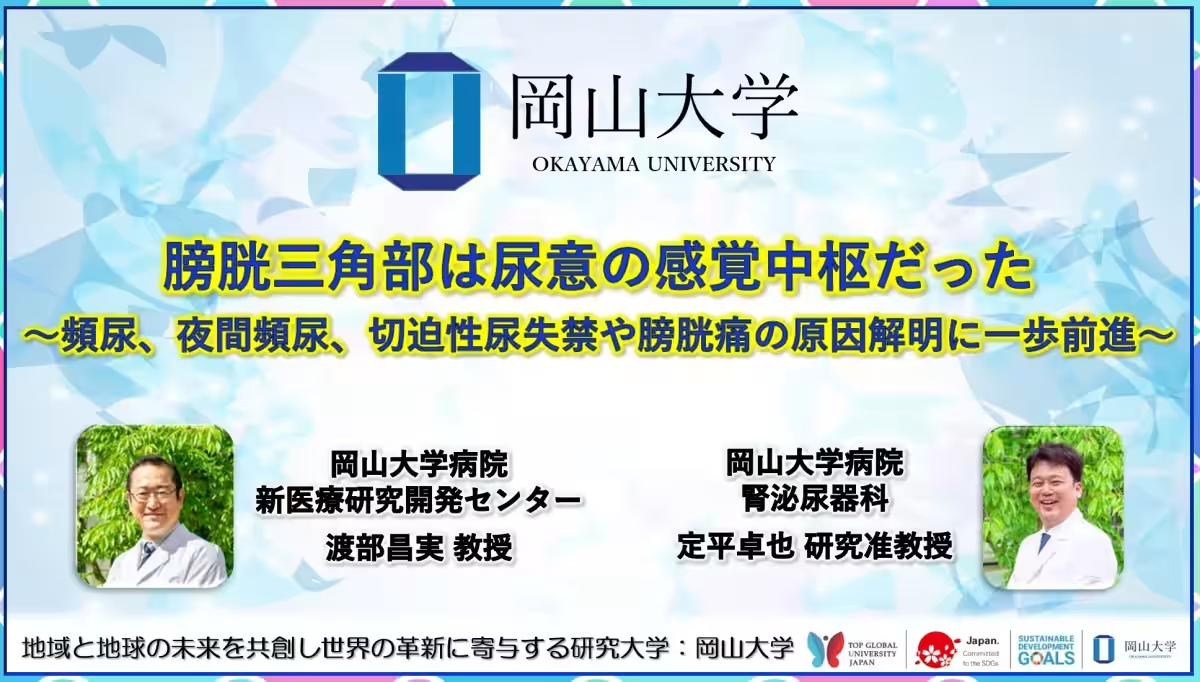








トピックス(その他)

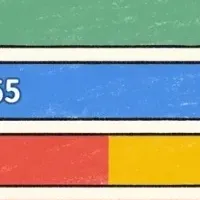
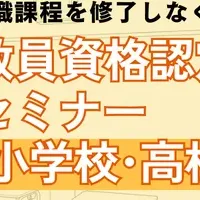


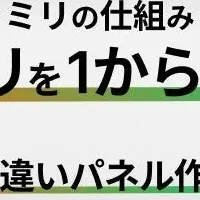


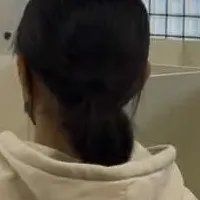
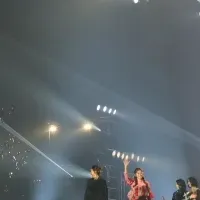
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。