

冨永愛が挑戦!京提灯作りの奥深さと職人技を体験
冨永愛が挑戦!京提灯作りの奥深さと職人技を体験
毎週水曜の夜10時から放送される「冨永愛の伝統to未来」では、日本の伝統文化を未来に引き継ぐ様子が紹介されています。9月24日のこの回では、冨永愛が京都の「京提灯」を専門に製作する工房を訪れ、職人技を体験しました。今回はその驚くべき体験を詳しくお伝えします。
京提灯の魅力と歴史
冨永が訪れたのは、京都市に位置する老舗の提灯工房「小嶋商店」。この店は江戸時代の寛政年間から続く伝統的な工房で、日本最古の劇場・南座の大提灯も手がけてきました。200年以上、町を温かい光で照らしてきた「京提灯」は、海外からの発注も受けており、国際的にも評価されています。
京提灯は、竹を使った「巻骨式」と「地張り式」の二つの作り方がありますが、特に丈夫で長持ちする「地張り式」が京提灯の主流です。しかし、その製作プロセスは非常に手間がかかり、今では数軒の工房でしか作られていない貴重なものです。
職人の技と冨永愛の挑戦
小嶋商店では、九代目の小嶋護さんとその息子の諒さんが職人として提灯を作り続けています。冨永がまず行ったのは、「糸釣り」の作業です。この工程では、竹の骨を糸で繋げていく作業が行われます。冨永は「ずっと糸を緊張させておくのが難しい」と語り、その難しさを実感しました。
続いて、冨永は和紙を張る「紙張り」の作業に挑戦。しかしこの工程では、特に細やかな手作業が求められ、彼女は「全然できない!」と苦戦。カーブに和紙をきれいに張る技術には、卓越した技量が必要です。冨永は職人の技に感心し、改めてその難しさを実感した様子でした。
新たな挑戦と未来への展望
また、小嶋商店では提灯の需要が減少する中で、新しい商品開発にも取り組んでいます。特に「ちび丸」と称されるミニ提灯キットが注目を浴びています。これは気軽に提灯作りを体験できる商品で、オリジナルのミニ提灯を楽しむことができます。
「親父に習得には10年かかると言われたが、私は3年でやった」と語る護さんの言葉は、伝統技術を受け継ぐ苦労と情熱を物語っています。伝統工芸が抱える後継者問題に触れながら、冨永も新しい需要の創出が必要だと強く感じたようです。
まとめ
9月24日の放送では、冨永愛が京提灯の歴史と職人技に触れ、その現状や未来について考えさせられる内容が展開されました。多くの視聴者にとって、京提灯の魅力を再認識するきっかけとなったことでしょう。番組公式SNSではロケ時のオフショットも更新中で、ぜひチェックしてみてください。
この「冨永愛の伝統to未来」は、伝統文化を未来へと繋げる貴重な番組です。毎週水曜、夜10時からの放送を見逃さないようにしましょう!




トピックス(エンタメ)

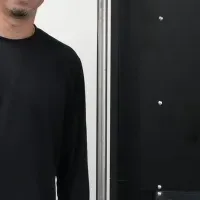
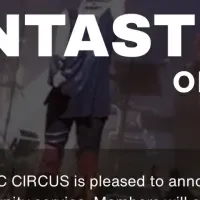
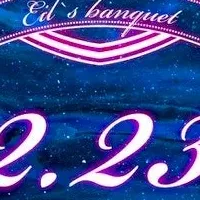
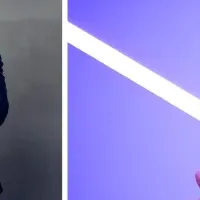

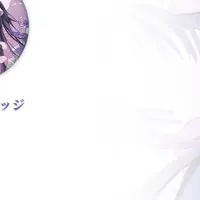



【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。