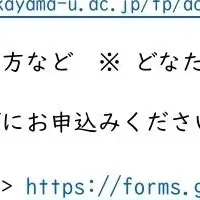
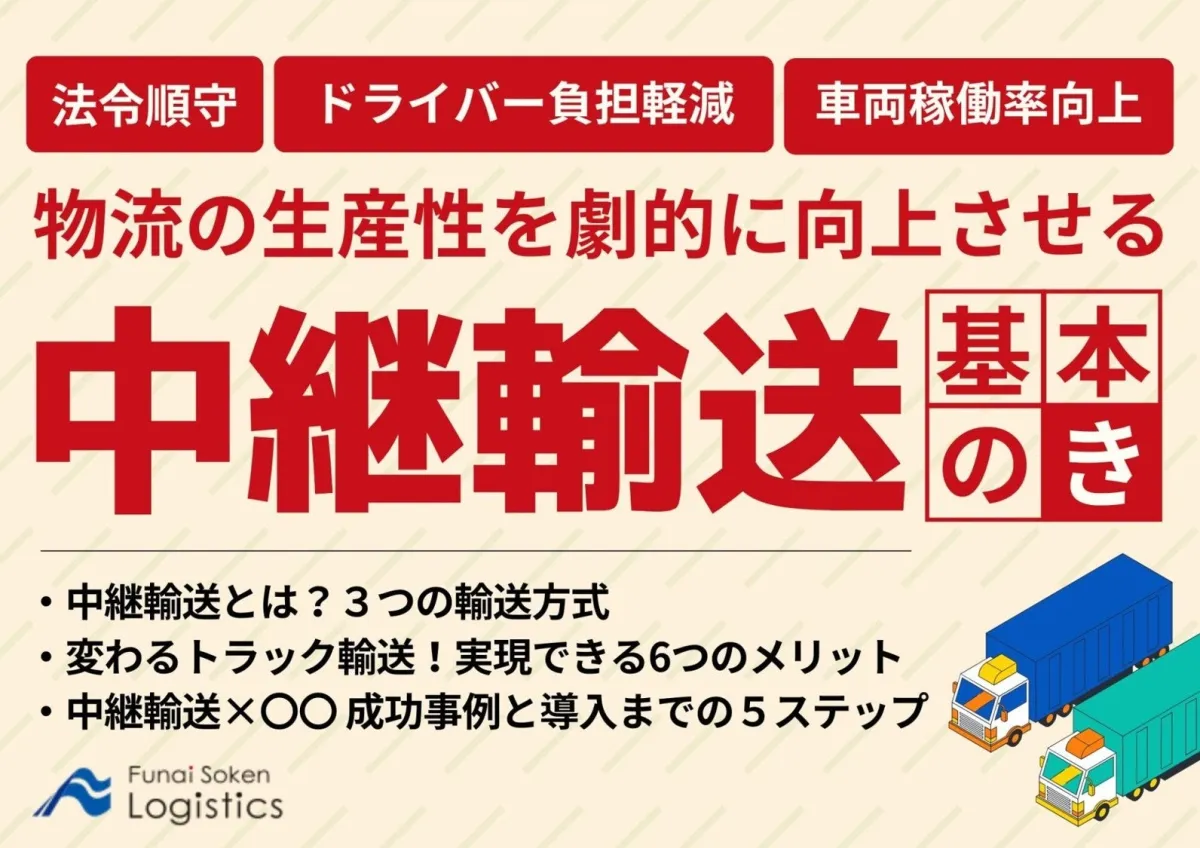
物流の生産性向上を実現する中継輸送の全貌を解説!
中継輸送がもたらす物流改革
近年、日本の物流業界ではさまざまな課題が浮上しています。特に「2024年問題」と呼ばれるドライバー不足に伴う影響や、物流コストの高騰は、荷主企業にとって深刻な問題です。中でも顕著な問題が、過疎地における物流ネットワークの確保です。荷物の量が少なければ、物流会社が採算が合わず、サービスが提供できないケースが増えてきています。
このような背景の中で、注目されているのが「中継輸送」です。中継輸送とは、複数の拠点を介して物品の運搬を行う手法で、荷物の集約と最適化を図ります。これにより、ドライバーの労働時間の短縮や、車両の稼働率の向上といった多くの利点を享受できます。
中継輸送の3つの基本方式
中継輸送には様々な方式がありますが、その中で特に代表的な3つの方式を紹介します。
1. スプリット輸送:最初の地点から中継地点を経由して最終地点に配送する方式で、荷量に応じたコスト削減が可能です。
2. ハブアンドスピーク:中心となる拠点に荷物を集約し、そこから各所に配送する方式。物流の効率化が図れます。
3. ダイレクト輸送:特定のルートを選び、最小限の中継を介して直送する方式。特に密集したエリアで活用されます。
中継輸送による6つのメリット
中継輸送には、多くのメリットがあります。主なものを挙げてみましょう。
1. コスト削減:複雑なルートを最適化することで、無駄な輸送コストを削減できます。
2. 充填率の向上:荷物の集約により、車両の積載効率がアップし、無駄な空車を減らします。
3. 労働時間の短縮:効率的なルートを計画することで、ドライバーにかかる負担が軽減されます。
4. 安定した供給:中継地点を設けることで、過疎地への配送が安定します。
5. 情報管理の効率化:トラッキングが容易になり、荷物の位置を常に把握できます。
6. 環境への配慮:無駄な輸送を減らすことで、CO2排出量も削減されます。
中継輸送の成功事例と導入ステップ
具体的な成功事例をもとに、どう導入すれば良いのかを見ていきましょう。中継輸送の導入は、以下の5つのステップを踏むことが推奨されています。
1. 現状分析:まずは自社の物流状況をしっかりと把握し、課題を明確にします。
2. システム検討:自社にとって最適な中継輸送のモデルを検討します。
3. パートナー選定:信頼できる物流業者を選定し、連携を築きます。
4. 試行運用:小規模から運用を始め、必要な調整を行います。
5. 本格運用:効果が確認できたら、本格的に中継輸送を導入します。
まとめ
「中継輸送」は、急速に変化する物流の世界において、企業が生き残るための一つの手段となり得ます。特殊なケースを除けば、多くの業種で導入可能であり、特に過疎地の物流環境に変革をもたらすことでしょう。ぜひこの機会に、船井総研ロジが提供する無料資料をダウンロードし、詳細をご確認ください。そして、あなたの企業の物流戦略に役立ててください。
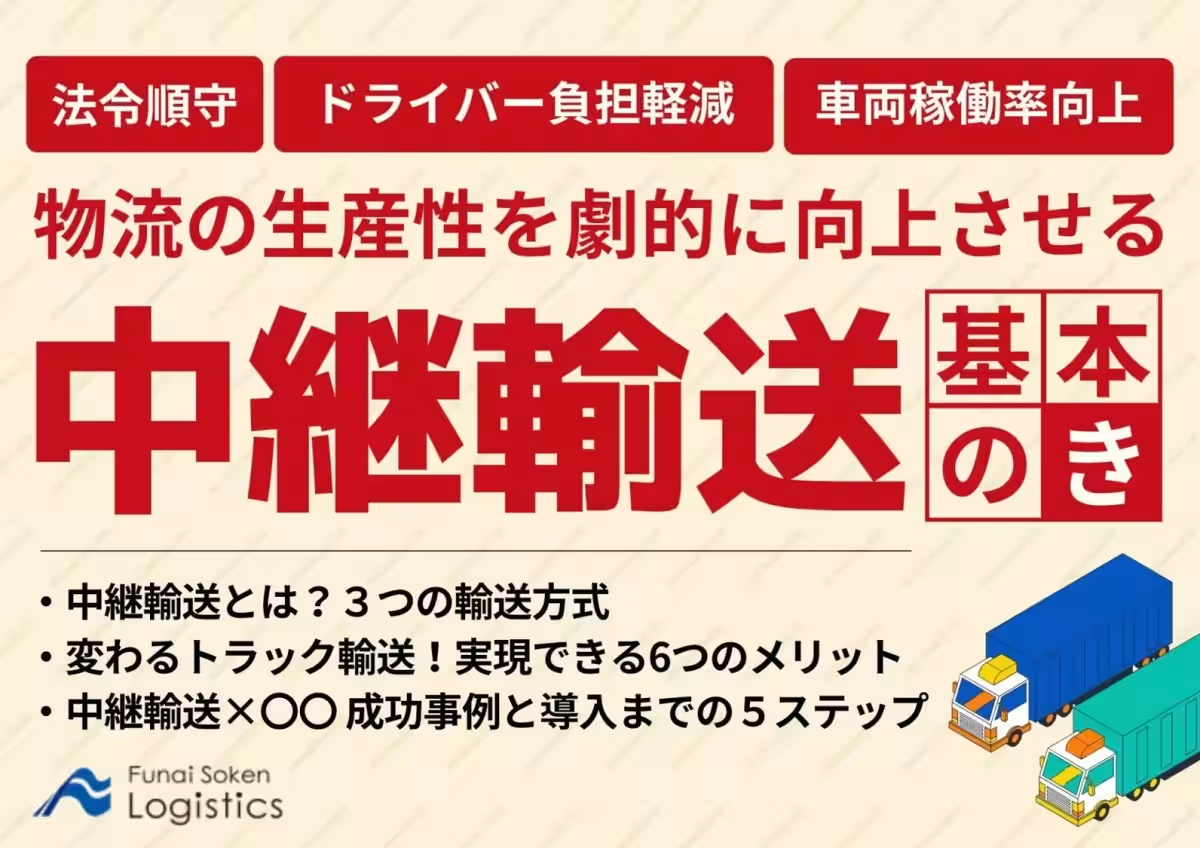
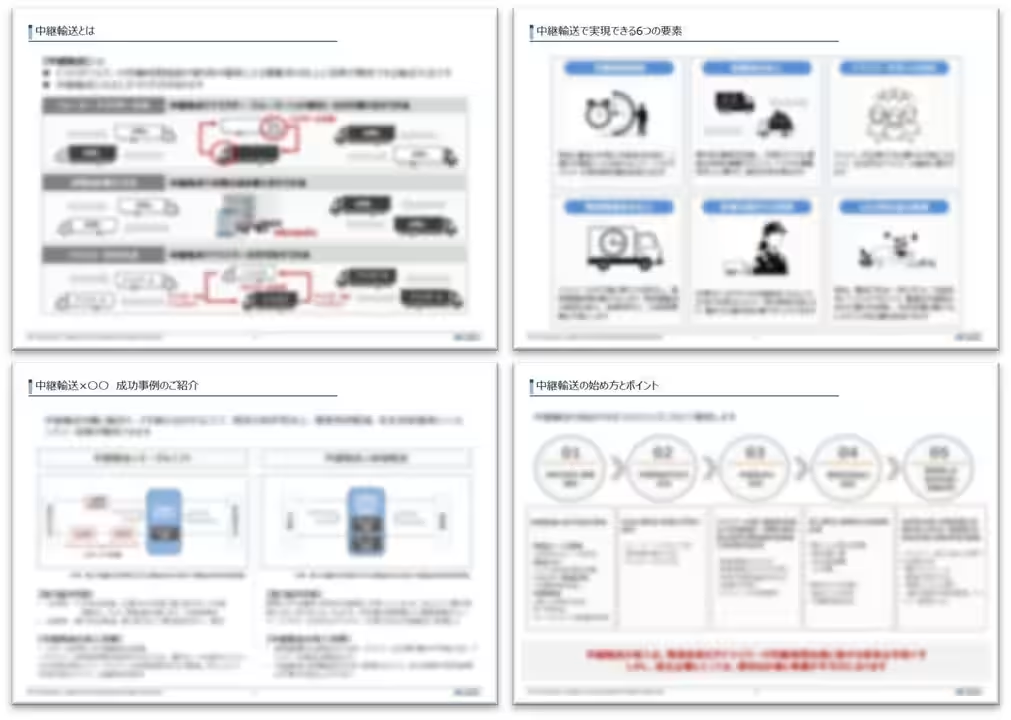
トピックス(その他)
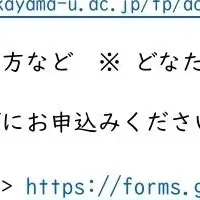
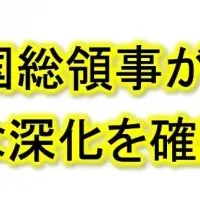


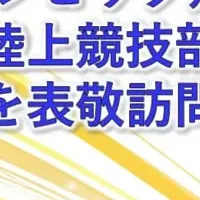


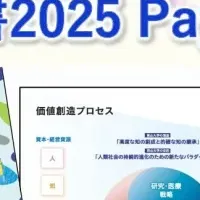


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。