

逆境を乗り越えて発展する岡山の環境ベンチャーが東京・埼玉に新拠点を設立
岡山の環境ベンチャーが新たな挑戦
岡山から発信する環境ベンチャー、次の灯株式会社は、2018年の設立直後に西日本豪雨による大きな困難に直面しました。社屋と商品を失ったものの、地域支援活動を通じて見出した新たな道から、再起を果たしました。彼らは、廃棄物に新たな命を吹き込む事業を展開し、国内外からの注目を集めています。
循環型経済を牽引する
次の灯のミッションは、環境と人間の関係性に関する難題に対し、異なる視点から解決策を見出すことです。特に、これまでの7年間で、環境ビジネスのサーキュラーエコノミー領域で確固たる実績を構築しています。
近年、脱炭素や資源循環のニーズが高まる中、実際には「製造」「物流」「再資源化」を結ぶ「循環インフラ」の整備は遅れています。使用済み部品を回収し再生するプロセスにおいて、地理的距離や業務の切り分けが大きな障壁となっているのです。
次の灯は、これらの課題を克服するために、製造と物流を近接した新しい拠点モデルを構築しました。このたび開設した東京都品川区と埼玉県入間市の新拠点は、時間、コスト、そして環境負荷の3つを同時に改善する仕組みを目指しています。
具体的な目標
今回の拠点開設には、以下のような目標があります。
- - 循環インフラの構築: 使用済み部品のリビルトや素材の再資源化、配送を一体化。
- - 企業間連携の高速化: 首都圏の地理的優位を活かし、迅速なレスポンスを実現。これにより在庫の回転率や輸送効率の向上を図ります。
- - 社会価値と経済価値の両立: CO₂削減量や物流効率などを可視化し、企業との協働によって社会的影響を拡大していきます。
「次の灯」理念の反映した東京オフィス
東京オフィスは、「次の灯」のブランドステートメント「めぐる、つなぐ、地球にイイコト」を空間に反映しています。一部の壁にはこのステートメントを掲示し、社員が自身の仕事の意義を忘れないよう工夫されています。さらに、ガラスパーテーションには企業ロゴを施し、開放的な空間を作ることで、社内外のコミュニケーションを促進しています。色使いにも配慮し、企業の理念である「温かさと挑戦」を強調しています。
未来への展望
次の灯は、今後大学や自治体、地場企業と連携し、環境技術やリサイクル技術の地域実装モデルを構築していく計画です。また、これらの取り組みを通じて、環境負荷の低減と経済循環の2つを同時に実現していくことを目的としています。
代表取締役の黒川聖馬氏は、「壊れたら捨てるという常識を変え、製造現場と物流をつなぐ社会インフラを築く」と述べ、品川・埼玉の新拠点をその第一歩と位置付けています。
次の灯は、日本国内での循環型資源ネットワークを拡大し、持続可能な社会の実現に向けて、地元から世界へとその活動を広げていくことを目指しています。彼らの存在は、環境に配慮した次世代のビジネスモデルを築く一助となることでしょう。




トピックス(その他)

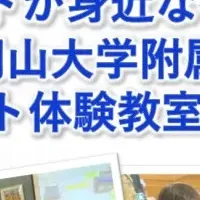


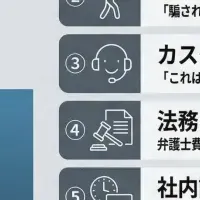



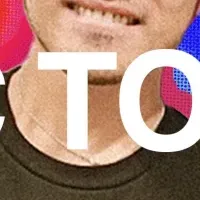

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。