

昆虫が下水処理場の汚泥を資源化、新技術の共同研究がスタート
昆虫と下水処理場の革新
水ing株式会社と株式会社スーパーワームが2025年10月1日から、新たな下水汚泥処理技術の開発に向けた共同研究を開始ります。今回は、昆虫が持つ素晴らしい能力を活用し、下水処理場から発生する汚泥を減容し、資源化することを目指します。この取り組みは、環境負荷を軽減し、持続可能な社会の実現に貢献することが期待されています。
研究の背景
日本政府は、持続可能な航空燃料(SAF)の導入を進めており、2030年には大量の原料油の供給が求められています。しかし、現在の供給量は目標の7倍以上も不足しているという厳しい状況があります。そのため、バイオ燃料として利用可能な原料の確保は喫緊の課題となっています。この背景を受けて、昆虫を用いた環境に優しい燃料源の開発が重要視されています。
従来の下水処理においては、汚泥は焼却や埋立処理されることが多いですが、これらの方法には多くのエネルギーを必要とし、CO₂などの温室効果ガスを排出するリスクがあります。また、埋立処理の場合、限られた土地を使用する必要があり、環境への影響も懸念されています。
研究の目的と内容
本研究では、スーパーワームやミルワームといった昆虫が、下水処理場から収集した脱水汚泥を食べることによって、以下の項目を検証します。
- - 減容効果:昆虫が汚泥をどれだけ摂取し、分解できるか。
- - 資源化の可能性:昆虫の体内で蓄積される油脂やタンパク質の量。
- - 実用性:大規模な運用に必要なコストやスペース、運用条件の検証。
この技術を活用することで、これまで廃棄されていた汚泥がバイオ燃料や飼料、肥料等の新たな資源として再活用される可能性が開けます。研究は2027年3月末まで続く予定です。
各社の役割
研究を進めるにあたって、水ing株式会社は脱水汚泥の収集や供給元施設との連携を担当し、実証試験の調整や支援を行います。一方、スーパーワーム社は昆虫の飼育試験や成長、減容効果、油脂の蓄積量を評価する役割を担います。
期待される効果
スーパーワーム社の代表取締役、古賀勇太朗氏は、昆虫の自然の分解・変換能力を活かし、持続可能な資源へと変える新技術の開発に意欲を燃やしています。水ing株式会社の島村和彰氏も、下水汚泥を効果的に活用する社会システムの構築に取り組む姿勢を示しています。
この協業により、自治体や企業の廃棄物管理に新たな選択肢を提供し、循環型社会の実現を目指していきます。昆虫による持続可能な汚泥処理技術の社会実装が待たれます。
結論
下水処理場からの汚泥を昆虫によって効果的に資源化するこの研究は、環境に優しい持続可能な解決策として今後の進展に期待が寄せられています。私たちの社会が直面している環境への負荷を軽減するために、これらの新たな技術が加速することが重要です。


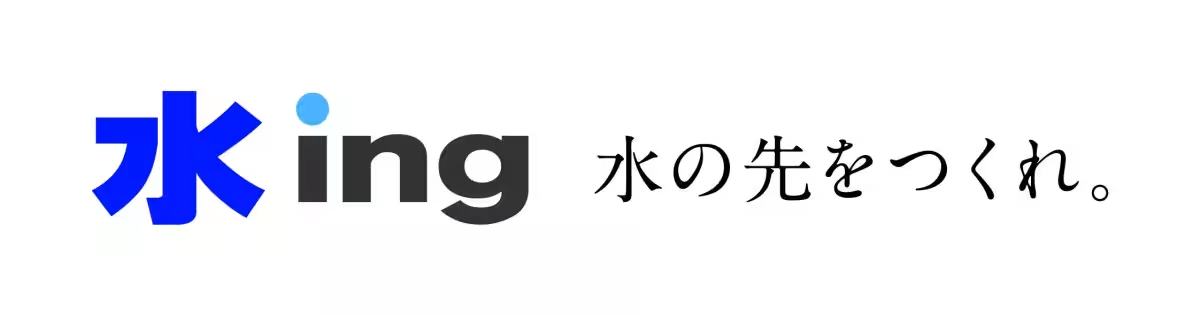

トピックス(その他)




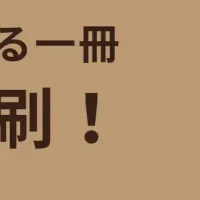


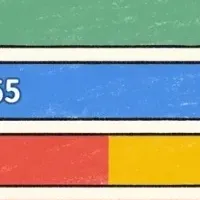
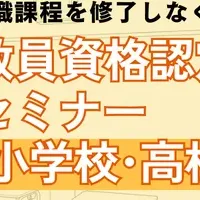

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。