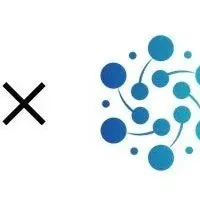
多様化する家庭の形と法律の変遷:共同親権に関する民法改正の意義
共同親権等に関する民法改正の概要
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。この改正は、特に父母が離婚する際に直面する子どもの利益を優先し、養育に関する父母の責任を明確にすることを目的としています。
改正の背景
昨今、社会の変化と共に家族の形も多様化しており、離婚後の親子関係においてもさまざまな課題が浮上しています。このような中で、子どもの権利を確保し、安心して生活できる環境を整えることが、法律改正の大きな背景にあります。具体的には、親権、監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与などに関する法律の見直しが行われました。
改正内容の詳細
改正された法律では、まず親権についての考え方が変わり、従来の「単独親権」から「共同親権」が推奨される形に移行します。これにより、両親が離婚後も子どもの育成において共同で責任を持ち、連携することが求められます。
さらに、養育費に関する明瞭な取り決めを促進するための規定も設けられます。これにより、親が離婚に際しても経済的な負担が公平に分担され、子どもに必要な資源が行き渡ることが期待されています。また、親子交流の重要性も再認識され、面会交流についての具体的なガイドラインが設けられていく予定です。
施行について
これらの改正は、公布から数年間の準備期間を経て施行されることとなりますが、一部の規定については早期に施行される可能性もあります。政府のガイドラインに従い、円滑な実施が求められます。
生活に与える影響
このような民法改正は、特にひとり親家庭にとって大変重要であり、子どもの成長における安定した環境作りに寄与することが期待されます。親としての責任が再定義され、子どもを取り巻く社会全体で支える体制が整えられると、より豊かな家庭生活が実現できるでしょう。
和歌山市においても、この改正に基づいた新たな支援制度や相談窓口が設けられる予定です。これにより、家庭の形が多様化する中でも、薬の効いた制度を通じて、すべての子どもが育成される環境を整えることが可能になるでしょう。
まとめ
新しい法律が施行されることにより、共同親権の考え方を基に、法的、社会的支援が強化されることが見込まれます。今後も家庭の形と法律の在り方がどう変化していくのか、注目が必要です。法律改正が、すべての子どもたちにとって良き未来を提供する手助けとなることを願っています。
トピックス(その他)
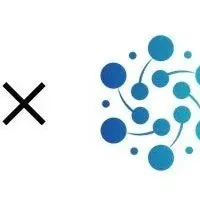
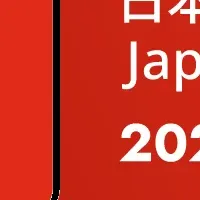
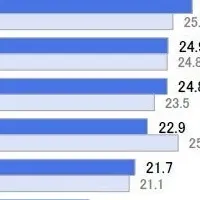



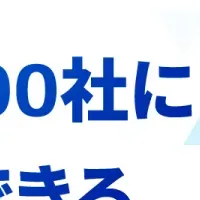
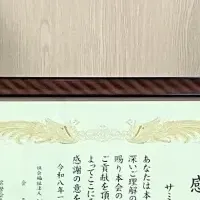


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。