

企業の未来を切り開く!第2回Booostサステナビリティカンファレンス開催レポート
企業の未来を切り開く!第2回Booostサステナビリティカンファレンス開催レポート
2025年10月6日、東京都千代田区のグロービス経営大学院において、第2回Booostサステナビリティカンファレンスが開催されました。主催はBooost株式会社。企業が持続可能性への取り組みを「規制対応」ではなく、成長戦略として捉え、競争力を高める方法を模索する場として多くの専門家が集結しました。
カンファレンスの目的と趣旨
本カンファレンスのテーマは「攻めのサステナビリティ」。企業はまさにトランジション期にさしかかっており、2026年からの制度義務化に向けた準備が急務です。Booostの代表取締役である青井宏憲氏は、サステナビリティを企業成長のエンジンとする必要性を強調しました。彼は、サステナビリティに対する戦略的対応を求め、経営の新たな姿勢「経営3.0」を提唱しています。
議論の焦点
カンファレンスは、機関投資家やコンサルタント、アカデミアなど多様な視点からの議論を交え、企業のサステナビリティをどう進化させるかに焦点を当てました。ゲストスピーカーには、金融庁元長官でBooost特別顧問の栗田照久氏、BCGの半谷陽一氏、一橋大学の野間幹晴教授などの著名な専門家が参加しました。彼らはそれぞれの視点から、企業が抱えるサステナビリティの課題や取り組みを分析し、解決策を模索しました。
各セッションの内容
トークセッション
アセットマネジメントOneの寺沢徹氏とBooostの大我猛は「ダイバーシティ」を核に、サステナビリティと企業価値向上を議論しました。寺沢氏はダイバーシティを競争力の源泉として位置づけ、経営層の実質的な姿勢が外部から評価される重要なポイントであると述べました。
大我氏も、サステナビリティやダイバーシティは形式的な取り組みではなく、経営変革を支える根幹であると強調。重要なのは、投資家から信頼を得るために具体的な施策が必要だということです。
基調講演
BCGの半谷氏は、地政学や市場動向が変革をもたらす現状を分析し、「守り」と「攻め」の両立が求められる時代に突入していると警鐘を鳴らしました。また、企業がサプライチェーンを再設計する際の注意点や、エコシステムの構築の重要性についても言及しました。
新ソリューションの発表
青井氏は、Booostの新しいプラットフォーム『booost Impact』のアップデートについて発表。このソリューションは非財務リスクを財務インパクトに変換するもので、企業のサステナビリティに関わる全てのデータを効率的に管理できる機能を備えています。
パネルディスカッション
寺沢氏と半谷氏、そして大我氏が参加したパネルディスカッションでは、攻めのサステナビリティがどう具体化されるかについて具体的な施策が議論されました。寺沢氏は「勝ち筋」を見える化する投資戦略が、企業の経営に不可欠であると訴えました。
結語と今後の展望
カンファレンスは、攻めのサステナビリティが企業成長にとって不可欠な要素であることを再認識させられる場となりました。今後、Booost株式会社は、サステナビリティ2026問題に直面する日本企業の支援を強化し、企業の持続可能性を向上させる活動を続けていきます。詳細なレポートは『Sustainability Leadership Magazine』で公開されていますので、ぜひそちらもご覧ください。








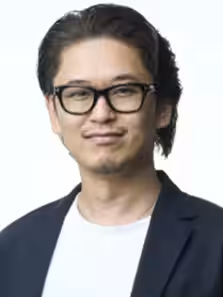

トピックス(その他)



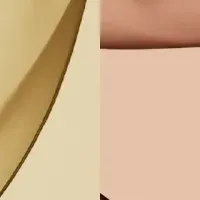

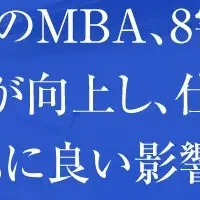
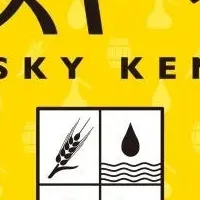

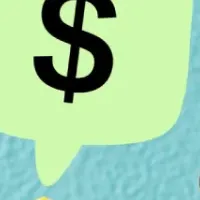
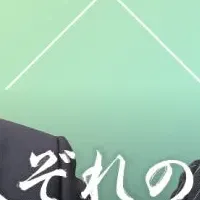
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。