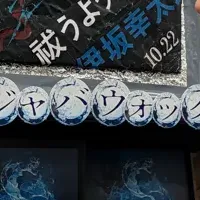
杏林大学が医療機器研究開発事業に新たな挑戦、AI技術で熱傷診療を支援
杏林大学が医療機器研究開発事業に挑む
東京都三鷹市に位置する杏林大学は、最新の医療技術を駆使して熱傷診療の革新を目指しています。今回、同大学は株式会社電通総研セキュアソリューションおよびバイオフィリア研究所と共に、AMED(日本医療研究開発機構)の「医療機器等研究成果展開事業」に挑戦することが決定しました。このプロジェクトは、「熱傷診療に係る自動診断・診療支援プログラム医療機器の研究開発」として進行し、熱傷診療の現場で求められている効率化を図ります。
課題解決のためのAI技術
熱傷診療は専門的な知識と技術を要する分野であり、医師不足が深刻な問題となっています。杏林大学は、電通総研セキュアソリューションおよびバイオフィリア研究所とともに、プログラム医療機器を導入することで、熱傷の診断や治療を標準化し、現場の医療支援に貢献することを目指しています。
特に、自動診断機能を有するAI技術を活用し、熱傷の写真画像を用いて迅速で正確な診断を行うことが可能となります。これにより、専門医の不足をカバーし、多くの患者に対してより良い医療を提供できるようになります。
研究チームの背景
杏林大学の医学部でこのプロジェクトをリードするのは、加藤聡一郎講師です。彼を中心とする研究チームは、2015年から熱傷の写真画像を活用した診断技術の研究を行っており、さらなる発展を目指しています。加藤講師は「当教室と高度救命救急センターは全国に誇る熱傷診療の実績があります。その知見を生かし、熱傷診療を革新させることが重要です」と語っています。
パートナーシップの意義
杏林大学が提携している電通総研セキュアソリューションは、高度なセキュリティを追求する企業であり、その技術力がプロジェクトの成功における重要な要素となります。バイオフィリア研究所も、医療に関する深い知見を持ち、杏林大学との産学連携による研究開発が期待されます。三者の専門知識を融合させ、新たな医療機器の開発に向けた第一歩を踏み出すことで、使いやすく効果的な製品の誕生が期待されています。
今後の展望
このプロジェクトが成功すれば、熱傷治療の現場は大きく変わる可能性があります。迅速な診断が行えるプログラム医療機器の導入により、専門医が不足している環境でも適切な治療が受けられるようになるでしょう。加藤講師は最後に、「確かな技術を持ったチームで、現場をサポートする新しい医療機器の開発に尽力する」との意気込みを示しています。医療現場での変革を期待し、今後の進捗を見守りたいと思います。
- ---
お問い合わせは杏林大学広報室(E-mail: [email protected]、電話:0422-44-0611)までどうぞ。
トピックス(その他)
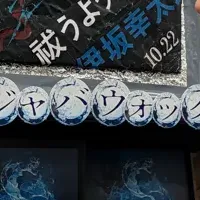



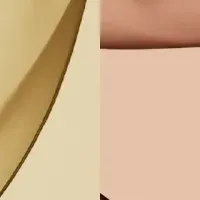

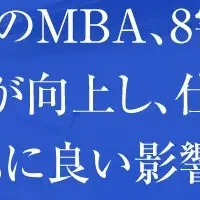
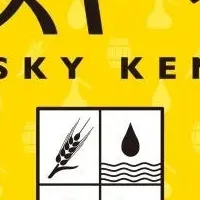

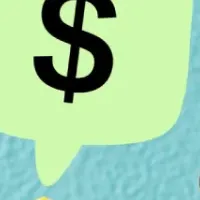
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。