

熊本大学と桜十字グループが推進する多文化共生教育プログラムの展開
熊本大学と桜十字グループが目指す多文化共生の新しい学び
熊本大学と桜十字グループの連携による新しい教育プログラムが、地域社会における多文化共生を促進することを目的に開始されました。このプログラムは、外国人材と共に学ぶことで地域課題の理解を深め、持続可能な解決策を導き出すことを目指しています。
地域課題への意識を高め、学びを深める
地域社会での多文化共生の必要性が高まる中、桜十字グループは外国人との関わりを通じて日々地域の課題を見つめています。熊本では特に外国人労働者が増加しており、今後もその流れが続くと予想されています。こうした背景を受けて、授業では地域問題を「自分ごと」として理解できる機会を提供し、学生たちが実際にフィールドで学べる環境を整えています。
授業の概要と進行方法
授業は主に三つの段階に分かれています。まず、学生は地域の現状や課題について学ぶ「インプット」セクションから始まります。この段階では、地域共生社会に関する理論や課題解決のための基礎的な考え方を学びます。
次に、実際に地域で働く外国人材との「フィールドワーク」が行われます。このセッションでは、参加者が直接外国人の声を聞くことで、より深い理解を得ることができます。
最後に、学生は自ら考えた解決策をグループで発表する「アイディエーション」フェーズに進みます。ここでの成果は、地域の実際の課題解決につながることが期待されています。
外国人材との実践的な交流
桜十字グループは、医療・介護の現場で多くの外国人スタッフを受け入れ、その教育と育成に力を入れています。プログラムでは、桜十字病院をフィールドワークの場とし、学生は実際に働いている外国人スタッフからさまざまな体験や知識を得ることができます。インタビューを通じて、彼らが抱える「困りごと」や「悩み」に触れ、地域の課題に対する理解を深めます。
多文化共生の大切さを認識
授業を通じて学生たちは、異なる文化や価値観を受け入れる力を育むことが求められます。このプログラムが、学生が地域と世界をつなぐ架け橋となり、相互理解を促進することにつながると期待されています。地域の未来を担う次世代の人材が育成されることは、熊本の地域社会にとっても非常に重要です。
地域社会との連携
授業の最終日には、学生たちが企画したアイデアを公開の場で発表するプレゼンテーション・コンテストが開催されます。このプレゼンテーションを通じて、外部の審査員が企画を評価し、地域における実現可能性を見極めます。多くの役割を持つ関係者が参加し、協力することで、学生の提案が実際のイニシアティブへとつながる機会が生まれます。
桜十字グループの役割
桜十字グループは、教育だけでなく地域社会への貢献を通じても重要な役割を果たしています。海外人材教育から医療・介護への取り組みに至るまで、グループの活動は新たな価値を創造し、地域社会を豊かにするための基盤を整えています。
まとめ
熊本大学と桜十字グループの共同プログラムは、次世代の人材育成と地域社会の多文化共生を促進するモデルケースとして、今後の展開が大変注目されています。この取り組みが、より良い地域社会の実現に向けた第一歩となることを願っています。












トピックス(その他)

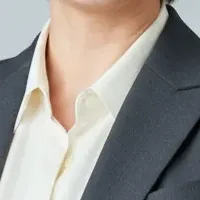
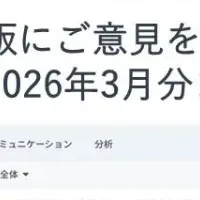

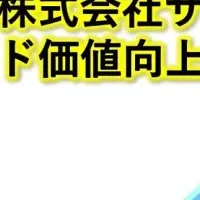
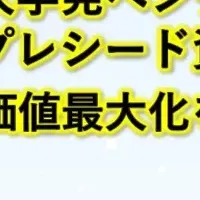
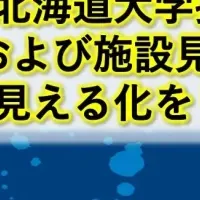
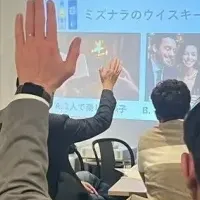
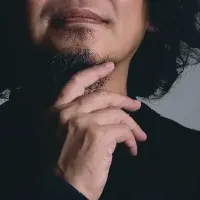
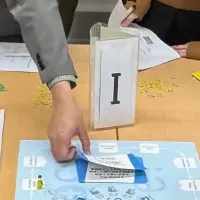
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。