
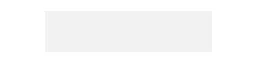
フレキシブルな切り紙型熱電発電デバイスの新たな可能性
フレキシブルな切り紙型熱電発電デバイスの新たな可能性
近年、IoT(Internet of Things)デバイスの自立電源として注目されているフレキシブル熱電発電デバイス。これは、温度差から電力を得ることにより、バッテリー交換が不要という利点を持つ。しかし、フレキシブル性と高い発電性能を両立させるのは難しい課題であった。そんな中、早稲田大学の研究グループが新たに開発したのが、切り紙構造を応用した熱電発電デバイスである。
切り紙構造の利点
本研究では、薄いフィルム基板に切り込みを入れ、立体的な形状を持つ切り紙型の構造を考案した。このポップアップ切り紙構造は、曲面の熱源にしっかりとフィットし、高い発電能力を実現している。具体的には、曲率半径わずか0.1mmの屈曲や、1.7倍の延伸が可能であり、これまで提案されたどのフレキシブル熱電発電デバイスよりも高い発電能力を示した。
この構造により、デバイスは人体の皮膚に貼りつけられ、体温と外気温との差を利用して電力を生成することが可能となった。特に、100μWの電力を生成し、これを使って体温を無線送信できるという革新的な成果も生まれた。これによって、ウェアラブルIoT機器へのさらなる応用が期待されている。
研究の背景と意義
IoTデバイスやウェアラブル機器が広がる現代、バッテリー交換の手間を省くための発電技術が求められている。これまでの研究では、ゴム材料を基板として使用することでフレキシブルなデバイスが提案されていたが、熱抵抗が高く、発電量が制限される課題が存在した。そこで、切り紙や折り紙の構造が注目されるようになった。
しかし、従来の折り紙や切り紙の形状は、熱源との接触が最適化されておらず、熱電発電デバイスにとっては効果的でなかった。本研究で提案されたポップアップ切り紙構造は、その欠点を克服し、発電性能を高める革命的な解決策を提示したのだ。
期待される応用
開発された熱電発電デバイスは、今後のウェアラブル機器や医療分野への展開が期待されている。特に、日常的に健康状態をモニタリングするためのデバイスとしての可能性は非常に高い。患者の体温や脈拍などのデータをリアルタイムで収集し、医療現場での役立ち方も増えていくことが予想される。
また、災害時には、身近な熱源(たとえばやかんなど)から電力を得ることで、停電時でもスマートフォンや通信機器を使用可能にすることができる。この技術は、特に弱い立場に置かれた地域や、災害時の救助活動においても重要な役割を果たすことが期待されている。
研究者の視点
本研究を主導した早稲田大学の岩瀬英治教授は「切り紙技術はアートの世界だけではなく、電子デバイスとの相性も良く、様々な分野での応用が期待されます」と語った。この研究が持つ多岐にわたる波及効果は、IoT社会の進展、持続可能なエネルギーソリューションの実現に寄与するものである。
今後、量産化および様々な熱電材料への応用が進むことで、さらに多くの革新がもたらされることを期待している。
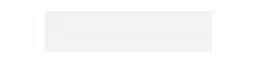


トピックス(その他)

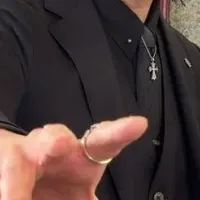


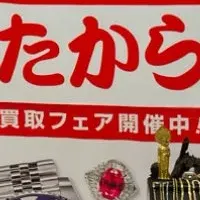
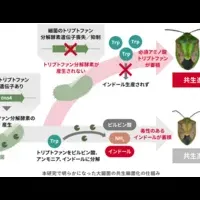




【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。