
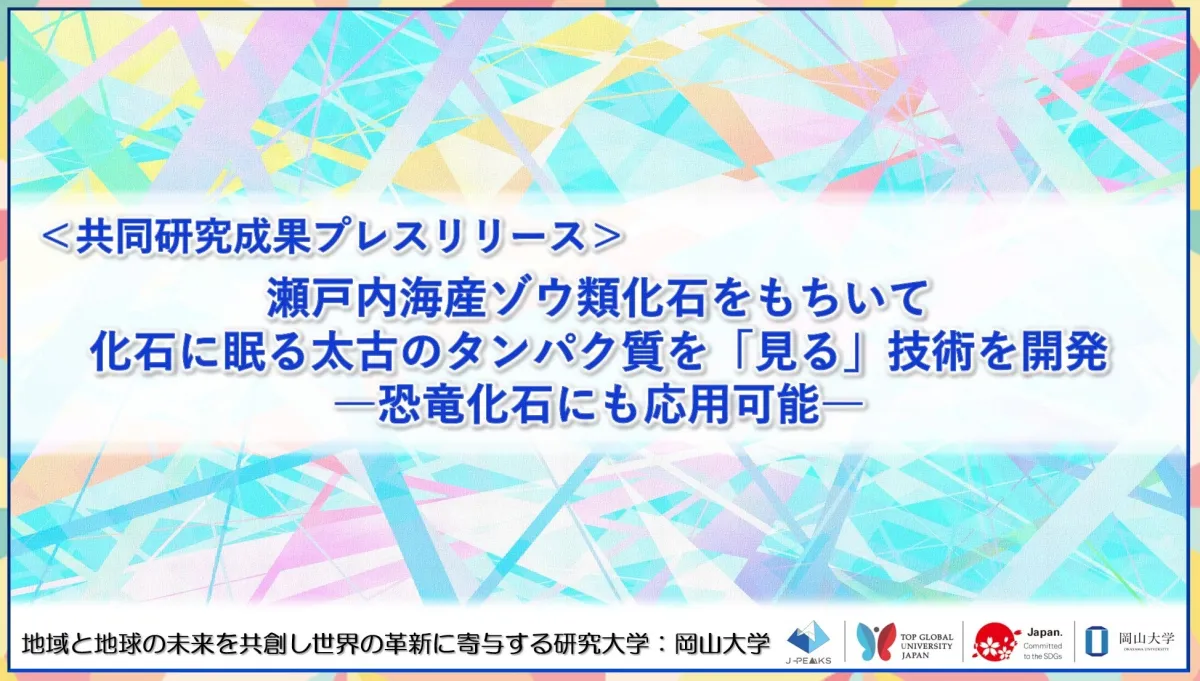
瀬戸内海のゾウ類化石から古代タンパク質を可視化する技術開発
近年、化石学との関わりに注目が集まっており、その中でも特に「パレオプロテオミクス」という分野が急成長しています。この分野は化石に存在するタンパク質を分析し、絶滅した生物の進化を探ることを目的としています。ただし、化石から取り出されるタンパク質は極めて微量で、外部からの汚染(コンタミネーション)も多く、このタンパク質が本当に化石由来であるかを証明するのは非常に難しい課題でした。
そんな課題を克服するために、岡山理科大学、岡山大学、University of Manitoba、倉敷市立自然史博物館、北海道大学およびたんば恐竜博物館が共同で新しい技術の開発に成功しました。この技術は、数万年前のゾウ類化石を用いて、化石内に存在するタンパク質を可視化するもので、化石の組織形態を壊さずにその内容を直接「見る」ことができるのです。
従来の技術に比べて、化石を薄くスライスした「研磨標本」に特異的な染色法を施すことで、化石内に含まれるコラーゲンなどのタンパク質の存在を視覚的に確認し、その分布を把握することに成功しました。この成果により、ブロックの見た目では種の特定が難しい化石でも、タンパク質の残存を確認し配列を解析することで、精度の高い種同定が可能になります。
この新技術は、特に博物館などで保管されている骨の断片のような、状態が悪く見た目だけでは種を特定できない化石に希望をもたらします。これにより、多くの化石が持つ情報を引き出し、理解が深まることでしょう。
さらには、この技術を古い時代の恐竜化石に応用することも期待されています。従来は分析が難しかった恐竜の化石からも、内因性のタンパク質が抽出できる可能性があるため、絶滅動物の進化に関する新たな知見が得られる可能性を秘めています。
これまでの研究は多くの課題を抱えていましたが、岡山大学のチームによるこの技術が、未来の化石研究を支え、さらなる発展を促すことが期待されます。この技術は高価で複雑な分析の前段階として、タンパク質がよく保存されている化石を選別するための簡便で信頼性の高いスクリーニング方法としても機能するでしょう。
この研究成果については、2025年6月25日に発表された論文「New Application of Histological Staining for Visualization of Endogenous Proteins in Fossil Material」に詳しく記載されています。著者には、稲葉勇人氏をはじめ、岡山大学や他大学の研究者たちが名を連ねています。
このような新技術の発展は、今後の化石研究や発展するパレオプロテオミクスの分野において、非常に興味深い進展となるでしょう。これからも、岡山の研究者たちの活躍に注目していきたいところです。
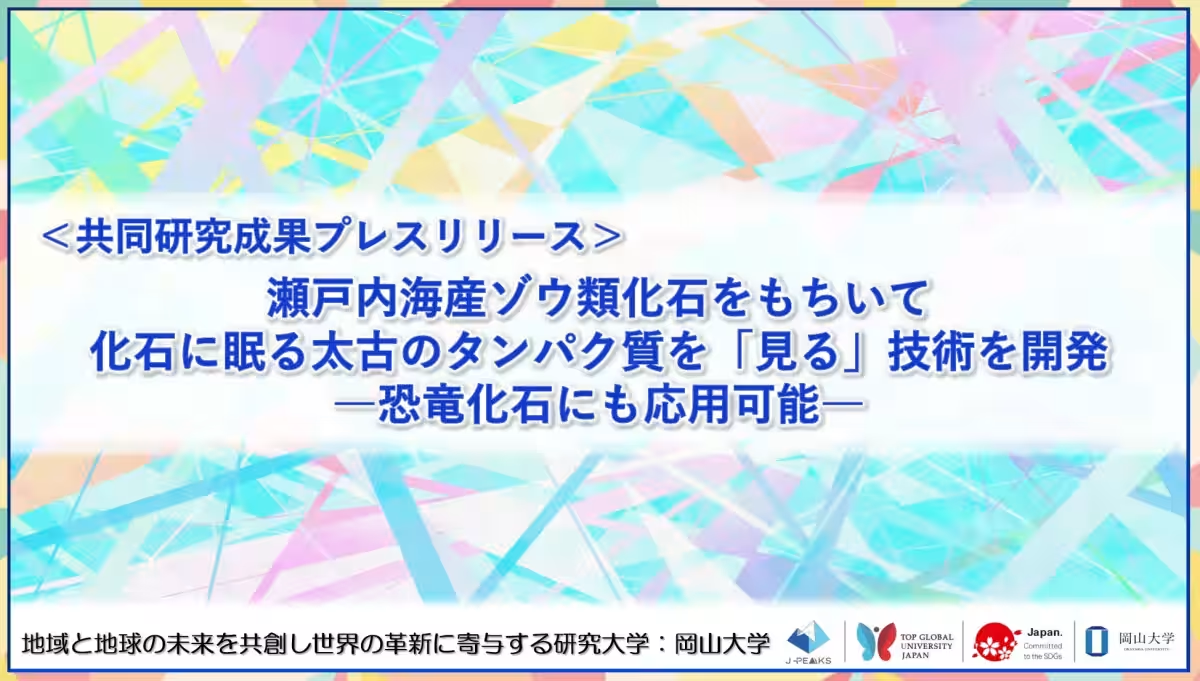





そんな課題を克服するために、岡山理科大学、岡山大学、University of Manitoba、倉敷市立自然史博物館、北海道大学およびたんば恐竜博物館が共同で新しい技術の開発に成功しました。この技術は、数万年前のゾウ類化石を用いて、化石内に存在するタンパク質を可視化するもので、化石の組織形態を壊さずにその内容を直接「見る」ことができるのです。
従来の技術に比べて、化石を薄くスライスした「研磨標本」に特異的な染色法を施すことで、化石内に含まれるコラーゲンなどのタンパク質の存在を視覚的に確認し、その分布を把握することに成功しました。この成果により、ブロックの見た目では種の特定が難しい化石でも、タンパク質の残存を確認し配列を解析することで、精度の高い種同定が可能になります。
この新技術は、特に博物館などで保管されている骨の断片のような、状態が悪く見た目だけでは種を特定できない化石に希望をもたらします。これにより、多くの化石が持つ情報を引き出し、理解が深まることでしょう。
さらには、この技術を古い時代の恐竜化石に応用することも期待されています。従来は分析が難しかった恐竜の化石からも、内因性のタンパク質が抽出できる可能性があるため、絶滅動物の進化に関する新たな知見が得られる可能性を秘めています。
これまでの研究は多くの課題を抱えていましたが、岡山大学のチームによるこの技術が、未来の化石研究を支え、さらなる発展を促すことが期待されます。この技術は高価で複雑な分析の前段階として、タンパク質がよく保存されている化石を選別するための簡便で信頼性の高いスクリーニング方法としても機能するでしょう。
この研究成果については、2025年6月25日に発表された論文「New Application of Histological Staining for Visualization of Endogenous Proteins in Fossil Material」に詳しく記載されています。著者には、稲葉勇人氏をはじめ、岡山大学や他大学の研究者たちが名を連ねています。
このような新技術の発展は、今後の化石研究や発展するパレオプロテオミクスの分野において、非常に興味深い進展となるでしょう。これからも、岡山の研究者たちの活躍に注目していきたいところです。
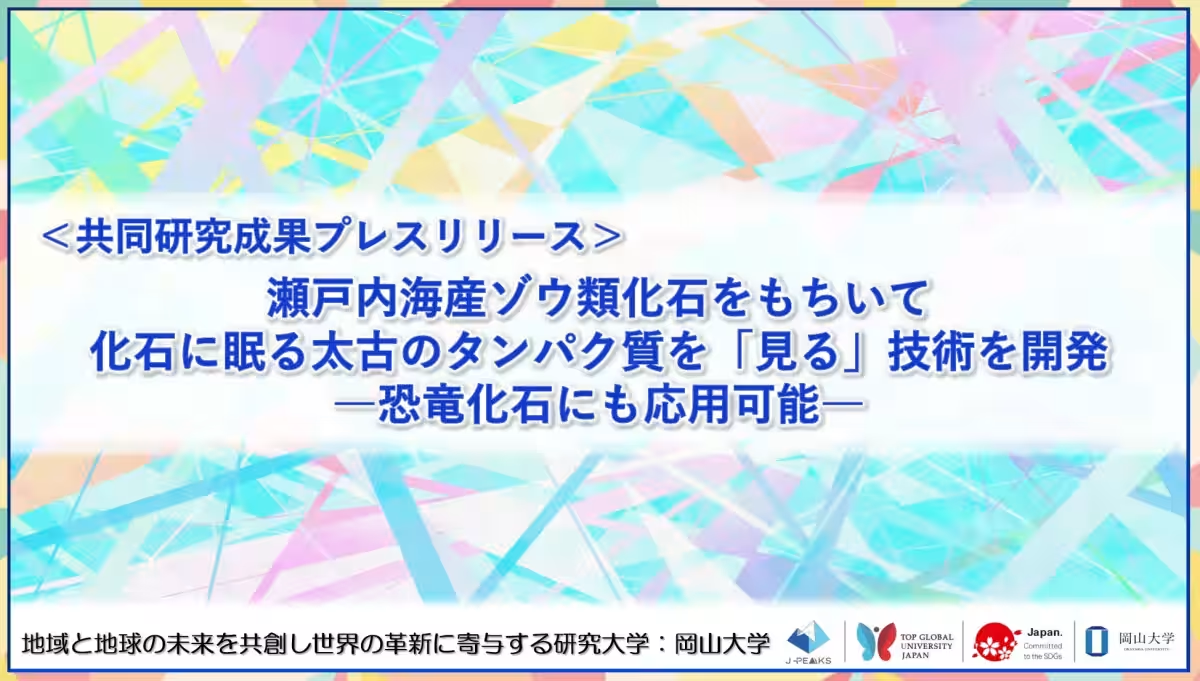





トピックス(その他)

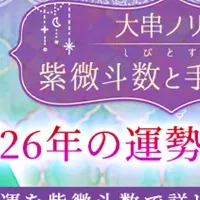




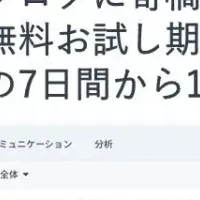


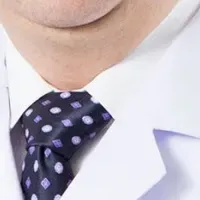
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。