

鮭の日を祝う!サーモン寿司40周年の魅力と新たな挑戦
鮭の日を祝う!サーモン寿司40周年の魅力と新たな挑戦
毎年11月11日は「鮭の日」として記念され、多くの人々に愛されている食材であるサーモンにスポットを当てる素晴らしい機会です。今年は特に、サーモン寿司が誕生してから40年を迎える特別な年でもあります。この特集では、回転寿司に不可欠の存在であるサーモンの魅力、歴史、そして新たな挑戦について深掘りしていきます。
鮭の日の由来
「鮭の日」は、一般社団法人日本記念日協会によって認定されました。記念日の背景には、漢字の「鮭」の部分である「圭」が、数字の「十一」の形に似ていることが起因しています。そして、この鮭の日に合わせて、多様な食文化が広がる時期でもあり、食欲の秋を感じながら様々な美味しい料理が楽しめます。
サーモン寿司の人気の背景
回転寿司の発展により、サーモンは日本中で親しまれる人気のネタとなりました。「くら寿司」の消費者調査でも、サーモンは14年連続で首位を獲得し、その存在感は他を圧倒しています。サーモンが日本に上陸したのは1980年代で、当時はまだ生で食べる文化が根づいていませんでしたが、ノルウェーからの輸入が始まり、徐々にその美味しさが広まりました。サーモン寿司が回転寿司として登場したことで、子どもから大人まで、世代を超えて人気を博しています。
鮭の養殖の変化
日本のサーモン需要の変化に伴い、養殖方法も進化しています。海面養殖だけでなく、陸上養殖も注目を集めています。陸上養殖は、水温や酸素濃度を人工的にコントロールできるため、高品質のサーモンを安定的に供給することが可能です。これにより、海岸に近くなくても養殖が行えるようになり、場所に依存しない新しい養殖システムが確立されています。
ご当地サーモンの魅力
各地で展開されるサーモン養殖においては、地域ごとの特性を活かした「ご当地サーモン」も急増しています。例えば、青森の「海峡サーモン」は外海で育てられ、その肉質や味に定評があります。兵庫の「神戸元気サーモン」は酒粕を与えられ、栄養豊富なサーモンが楽しめます。また、愛媛の「みかんサーモン」は、伊予柑オイルをエサに加えた、風味豊かな一品として人気です。
海外からのサーモン輸入の重要性
ノルウェーからのサーモンはやはり日本でのサーモン人気に大きく貢献しています。ノルウェー大使館の水産参事官に聞くと、1980年代には大量に輸出が始まり、回転寿司の登場によりその人気は瞬く間に広まりました。サーモンは寄生虫が少なく、安心して生食できるため、安全性にも優れています。
料理に活用するサーモン
家でサーモンを活用するのも楽しい体験です。サーモンのタルタルやソテーの焦がしバターソースといった簡単で美味しいレシピを試してみましょう。サーモンはそのままの刺身感も良いですが、アレンジを加えることで新たな発見ができる食材です。
結論
『鮭の日』やサーモン寿司の40周年を迎え、新たな養殖手法やご当地ブランドの設立が進展しています。消費者としては、その美味しさや栄養価を楽しむと同時に、地域の水産業の発展にも貢献する時代が来ています。ぜひ、鮭の日を祝って、サーモン料理を楽しんでみてください!










トピックス(グルメ)







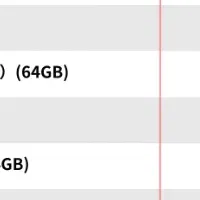


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。