

伝統的な京提灯作りに挑む冨永愛の奮闘!作品の魅力と職人技に迫る
毎週水曜日の夜10時から放送されるBS日テレの「冨永愛の伝統to未来」。この番組では、名だたるモデルである冨永愛が日本各地の伝統文化を掘り下げ、その根付く姿を紹介します。4月2日の放送では、冨永が京都にある京提灯の工房「小嶋商店」を訪問し、代々受け継がれてきた提灯作りの現場を体験しました。
小嶋商店は江戸時代の寛政年間に創業し、南座の大提灯なども手がける伝統ある工房です。200年以上という長い歴史を持ちながら、現在でも多くの海外からの注文を受けています。この工房での提灯作りには二つの方法があります。一つは「巻骨式」と呼ばれ、竹ひごを螺旋状に巻いて作る技法。もう一つが「地張り式」で、こちらは細く割った竹を型に沿わせる方法です。主に京提灯作りに用いられ、丈夫さが求められます。実際、現在では「地張り式」で製作する工房は京都市内に数軒しか残っていないのです。
冨永が工房で体験した作業内容は、竹の骨を糸でつなぐ「糸釣り」や、骨に和紙を貼る「紙張り」です。特に「糸釣り」では、糸を常に緊張させてつないでいくという作業の難しさに直面。「やばい、やばい!これ一回緩んできちゃうと全部緩んできますね」と、冨永は苦戦を強いられました。反対に、九代目の小嶋護さんはこの技術を習得するまでに3年を要したことを明かし、笑顔で「親父には10年かかると言われたんですよ」とコメントしました。
特に難しいとされる「紙張り」では、提灯の曲面に和紙を綺麗に貼る作業に挑戦。冨永は「全然出来ない!」と叫び、その難しさを伝えました。職人の技術によって、形の異なる提灯が美しく仕上がっていく様子を目の当たりにし、感心せざるを得ませんでした。
さらに、「字入れ」や「塗り」の作業も体験。これは護さんにしかできない業務であり、冨永も挑戦しましたが「凹凸してるので真っすぐ塗れない」とその難しさを再認識しました。普段見せることのない難易度の高い作業を、一流の職人の手がけた技術の上に学ぶことの貴重さを実感しました。
小嶋商店では提灯の需要減少にもかかわらず、新たな商品の開発に力を入れています。特に「ちび丸」というミニ提灯のキットは、誰でも気軽に提灯作りを体験できる商品として人気です。また、海外からの注文も増えており、伝統工芸の魅力は国境を越えて広がっています。
京提灯作りの豊かな伝統と、冨永愛の挑戦が生み出したドラマ。それを通じて、視聴者に伝えられるのは、古き良き文化の素晴らしさです。「冨永愛の伝統to未来 京提灯編」はBS日テレで4月2日(水)22時から放送。楽しいオフショットも公式SNSで公開中です。興味のある方はぜひご覧ください。




京提灯の歴史と魅力
小嶋商店は江戸時代の寛政年間に創業し、南座の大提灯なども手がける伝統ある工房です。200年以上という長い歴史を持ちながら、現在でも多くの海外からの注文を受けています。この工房での提灯作りには二つの方法があります。一つは「巻骨式」と呼ばれ、竹ひごを螺旋状に巻いて作る技法。もう一つが「地張り式」で、こちらは細く割った竹を型に沿わせる方法です。主に京提灯作りに用いられ、丈夫さが求められます。実際、現在では「地張り式」で製作する工房は京都市内に数軒しか残っていないのです。
手作りの大変さを実感
冨永が工房で体験した作業内容は、竹の骨を糸でつなぐ「糸釣り」や、骨に和紙を貼る「紙張り」です。特に「糸釣り」では、糸を常に緊張させてつないでいくという作業の難しさに直面。「やばい、やばい!これ一回緩んできちゃうと全部緩んできますね」と、冨永は苦戦を強いられました。反対に、九代目の小嶋護さんはこの技術を習得するまでに3年を要したことを明かし、笑顔で「親父には10年かかると言われたんですよ」とコメントしました。
特に難しいとされる「紙張り」では、提灯の曲面に和紙を綺麗に貼る作業に挑戦。冨永は「全然出来ない!」と叫び、その難しさを伝えました。職人の技術によって、形の異なる提灯が美しく仕上がっていく様子を目の当たりにし、感心せざるを得ませんでした。
職人技の結晶
さらに、「字入れ」や「塗り」の作業も体験。これは護さんにしかできない業務であり、冨永も挑戦しましたが「凹凸してるので真っすぐ塗れない」とその難しさを再認識しました。普段見せることのない難易度の高い作業を、一流の職人の手がけた技術の上に学ぶことの貴重さを実感しました。
新たな挑戦と未来への希望
小嶋商店では提灯の需要減少にもかかわらず、新たな商品の開発に力を入れています。特に「ちび丸」というミニ提灯のキットは、誰でも気軽に提灯作りを体験できる商品として人気です。また、海外からの注文も増えており、伝統工芸の魅力は国境を越えて広がっています。
結び
京提灯作りの豊かな伝統と、冨永愛の挑戦が生み出したドラマ。それを通じて、視聴者に伝えられるのは、古き良き文化の素晴らしさです。「冨永愛の伝統to未来 京提灯編」はBS日テレで4月2日(水)22時から放送。楽しいオフショットも公式SNSで公開中です。興味のある方はぜひご覧ください。




トピックス(その他)


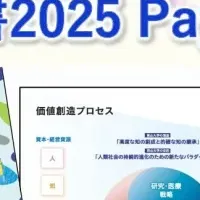







【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。