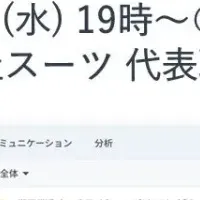

モバイル建築が支援する災害時の応急仮設住宅供給の取り組み
モバイル建築が支援する災害時の応急仮設住宅供給の取り組み
近年、地震や自然災害の頻発により、応急仮設住宅の迅速な供給が求められています。そんな中、一般社団法人日本モバイル建築協会は、移築可能な木造モバイル建築(モバイルハウス)を用いた応急仮設住宅の開発と普及に力を入れています。
モバイル建築の特長
モバイルハウスは、一般の恒久住宅と同じレベルの安全性、性能、耐久性を持っており、災害発生時には応急仮設住宅として機能します。使用後は、被災者や市町村営住宅に払い下げられ、自力再建のための住宅として再利用されることが計画されています。このような循環型の住宅供給モデルが、被災地の復興を支える鍵となるでしょう。
オフサイト生産と地域工務店の協力
日本モバイル建築協会のモバイルハウスは、オープンな工法を採用し、全国の中小工務店に設計情報や製造ノウハウを提供しています。これにより、被災地に大工を送り込むことなく、外部でモバイルハウスのユニットを生産し、短期間で大量の応急仮設住宅を供給できる体制を整えています。
現在の協定状況
協会は、都道府県や政令市と連携し、災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定締結を進めています。2024年2月29日には石川県、8月15日には鳥取県、2025年5月13日には山形県と協定を結びました。全国の市町村とも協議を進めており、現在、14件の協定を道府県や市町村と結んでいます。
具体的な災害事例
令和6年に発生した能登半島地震では、協会のモバイルハウスが災害救助法に基づく応急仮設住宅として採用され、261戸が供給されました。これらの仮設住宅は使用後に無償譲渡され、市町村営住宅として再利用される計画があります。また、一部の住宅は被災者個人へ無償で払い下げられ、自力再建の手助けとなることが期待されています。
現地施工の支援
協会では、応急仮設住宅の供給にあたって、地元の地域工務店が中心となることを原則としています。しかし、現地での施工が難しい場合は、オフサイトで生産したユニットが地域工務店に供給されることで、迅速かつ効率的な供給が可能です。これによって、中小工務店の協力を得て、応急仮設住宅の供給体制をより強化しています。
このように、日本モバイル建築協会は、木造モバイル建築を通じて災害時のサポート体制を強化し、被災者支援に取り組んでいます。今後も、透明性のある信頼構築とともに、さらなる協定の締結を目指し、地域社会の復興に寄与する活動を続けていくでしょう。

トピックス(その他)
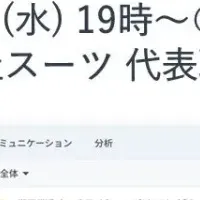
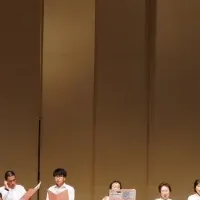
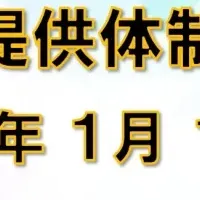




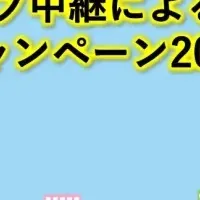
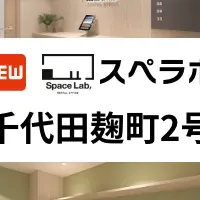
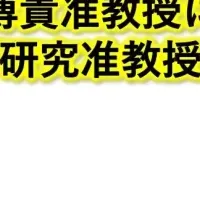
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。