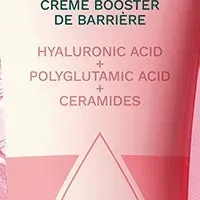

ジャカルタで初開催!イスラム教徒も楽しめる日本のハラール食の魅力
ジャカルタで魅力を発信!日本のハラール食文化
イスラム教徒の皆さんが安心して楽しめる日本の食材と料理を知ってもらうために、日本食品海外プロモーションセンター(以下、JFOODO)がインドネシア・ジャカルタにて、2025年11月13日(木)に食文化イベント『AUTHENTIC CULTURAL DINING』を初めて開催しました。このイベントには、世界中のムスリム人口の増加という背景があり、ハラール市場が注目されています。2030年までにこの人口は22億人に達すると見込まれており、日本のハラール食品やサービスも今後の成長が期待されているのです。
ハラールと日本産食材の魅力
「ハラール」とは、イスラム教で認められている食品やサービスのことを指し、豚肉やアルコールを含まないこと、そして特定の方法で処理されなければなりません。ジャカルタでは日本食に対する関心が急増中で、多くの日本食レストランが登場していますが、イスラム教徒が安心して食べることができる日本産食材の情報はまだ十分に広まっていませんでした。そのため、今回は日本産食材の高さや多様性、クラフトマンシップを理解してもらう機会とすることがこのイベントの目的でした。
豪華な料理の提供
イベント当日には、日本料理の名店「本家 たん熊」から若主人の栗栖純一氏が、ハラールメニューの一環として特別な日本料理をご提供。そのほか、ジャカルタで人気のレストラン「Hutan Kota by Plataran」のChef Reiyan Trisandraも日本和牛を使ったスペシャルメニューを提供しました。日本和牛の柔らかさや旨味が感じられる料理に、現地メディアやインフルエンサーからも大好評を得ました。実際に「ジューシーで美味しい」といった声が多く集まり、参加者には日本産食材の魅力がしっかりと伝わりました。
日本とインドネシアの文化交流
また、インドネシアから日本に訪れる人数は増加傾向にあり、2024年には約517,000人が日本を訪れる見込みです。本イベントを機に、ムスリム向けメディアや口コミアプリ「HALAL NAVI」と提携し、安心して食事ができる情報を提供する仕組みも発表されました。これにより、インドネシアの方々が日本へ訪れる際にも安心してレストラン選びができる環境が整います。
ご挨拶とメッセージ
JFOODOセンター長の小林栄三氏は、「日本の素晴らしい食材を楽しんでもらうため、ハラール対応を最優先に準備を進めた」と語り、在インドネシア日本国大使館の明珍充臨時代理大使も日本食の魅力を広める意義を強調しました。日本の伝統的な食文化である和食は、ユネスコ無形文化遺産にも登録されていますが、このイベントを通じてその多様性と味わいが多くの人々に届くことを期待しています。
ハラール対応の進化
今回のイベントでは、栗栖氏とReiyan Trisandra氏がそれぞれの料理についての解説を行い、ハラール対応の難しさや工夫について話しました。栗栖氏は「生魚を扱うお造りには特に気を使い、繊細な技術が必要」と述べ、日本料理の魅力を伝えました。Reiyan氏も、日本和牛を活かしつつインドネシア料理の特徴を際立たせた料理を提供する難しさについて語り、その努力が料理のクオリティに繋がっていることを示しました。
トークセッションも大盛況
イベントには、元JKT48メンバーのMelodyさんや著名シェフのAiko Sarwosri氏も参加し、日本食やハラール対応についての意見交換を行いました。Melodyさんは「日本食の味わいの多様さに驚き、今や安心して選べる」と喜びを表し、Aikoシェフもその品質を称賛していました。このように、ハラール対応が進化することで、日本食をより自由に楽しめる時代が訪れたことを実感させる素晴らしいセッションとなりました。
まとめ
『AUTHENTIC CULTURAL DINING』を通じて、日本のハラール食文化への理解が深まると共に、両国間の文化交流がさらに進展することを期待しています。日本産食材の魅力が広がり、イスラム教徒をはじめとする全ての人々が安心して楽しむことができる日本食の未来に、ますます目が離せません。今後も、このような交流イベントが続くことを期待しています。

















トピックス(グルメ)
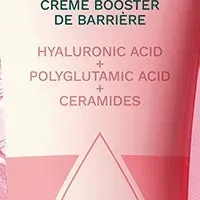
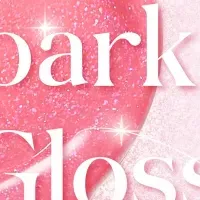


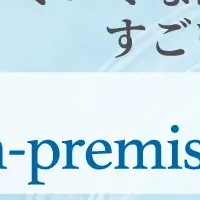
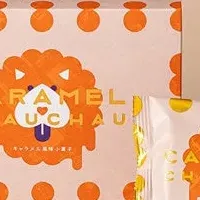
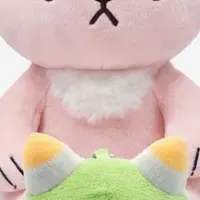



【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。