

ヤングケアラーを支えるための新たな調査結果と取り組み
ヤングケアラー調査の意義
公益財団法人交通遺児育英会は、教育支援を受ける学生の生活実態を把握するために、「ヤングケアラー調査」を実施しました。この調査は、ヤングケアラーの存在や彼らへの支援を考える上で重要なデータを提供することを目的としています。昨年に引き続き、今回は743名の奨学生の中から467名が回答し、調査の結果が明らかになりました。プログラムの一環として、外部の専門家による監修も受けています。
調査方法と結果の概要
調査はWebと記入式の併用で行われ、期間は2025年の6月27日から7月25日まででした。全体の12.4%の奨学生が、過去または現在においてヤングケアラーとして家族の世話をしていることが明らかになりました。特に高校生では12%、大学・短大生以上では12.8%が該当します。この数字は全国調査と比較して非常に高いことが分かります。
主に家事(44.8%)、外出の付き添い(34.5%)、見守り(31.0%)といった具体的な世話の内容が挙げられています。また、お世話をしている高校生では半数が「ほぼ毎日世話をしている」と回答し、25%は1日あたり3時間以上をかけていることがわかりました。これは、彼らが日常的に多くの負担を抱えていることを示しています。
お世話の開始時期と健康状態
お世話を始めた年齢は、「7歳から12歳」が43.1%を占め、早い段階でヤングケアラーとしての役割が始まったことが伺えます。5~9年にわたって世話を続けている方が多いことも印象的で、健康状態については「精神的にきつい」と感じる高校生が10%、大学・短大生以上では23.7%に達しています。
支援のニーズと認知度
特に、自分がヤングケアラーであることを自覚していない学生も多く、全体の36.2%が「あてはまる」と答えています。相談経験については、高校生の50%、大学・短大生以上の63.2%が「相談したことがない」とし、主な理由には「悩みではない」とする意見が多く見受けられました。また、支援を求める具体的な要望としては、高校生が「修学への特別支援金」や「家庭への経済的支援」を希望するなど、様々なニーズが明らかになっています。
認知度の向上と今後の取り組み
興味深いことに、ヤングケアラーに関する認知度は前回よりも上昇し、聞いたことがあるが具体的な内容を知らないという人が19.1%に及びます。これは、私たちが行うべき啓発活動の重要性を示しています。
今後も交通遺児育英会は、ヤングケアラーの実態について深く理解を深め、支援策を検討・実施していく予定です。また、ヤングケアラー対策検討プロジェクトのもと、奨学生への面談も進め、早期で適切な支援を行えるよう尽力しています。これからも彼らのサポートに努めてまいります。
この調査が、多くのヤングケアラーの実態を理解し、彼らに必要な支援を提供する一助となることを私たちは願っています。
トピックス(その他)


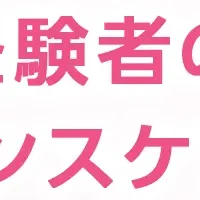


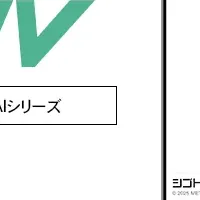

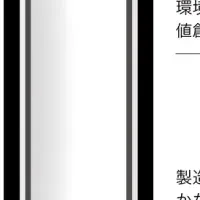

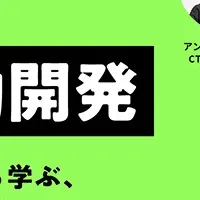
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。