

岡山大学で放射光利用をテーマにした研修会が開催
岡山大学は、2025年8月1日に「放射光利用連携Workshop」を開催しました。このイベントは、放射光をテーマに多様な研究機関や企業、さらには大学から106名の参加者が集まり、放射光の利用促進を図ることを目的としています。ハイブリッド形式で行われたこのWorkshopでは、岡山大学津島キャンパスの創立五十周年記念館を会場にし、オンラインでの参加も可能にしました。
このWorkshopは特に、大型放射光施設「SPring-8」や佐賀県の九州シンクロトロン光研究センター(SAGA-LS)などを初めて利用する研究者や技術者を対象としています。岡山大学は新たに開始する「放射光施設利用サポートサービス」の紹介や、先端分析技術の提供を通し、産学官の連携を強化していくことを目指しています。
イベントの冒頭では、岡山大学の副理事・副学長である佐藤法仁氏が、Workshopの趣旨およびSAGA-LSとの協定について説明しました。続いて、岡山大学総合技術部の堀金和正サイテックコーディネーターが放射光利用分析サポートサービスや、学内の共用機器を簡単に検索できるCFPOUについてのプレゼンテーションを行いました。
第1部では、JASRIの筒井智嗣主幹研究員がSPring-8およびNanoTerasuに関する紹介を行い、SAGA-LSについては廣沢一郎所長が地域産業との連携事例を交えて講演しました。
第2部では、研究者たちが具体的な放射光の利用事例を発表しました。岡山大学の沼本修孝准教授は、クライオ電子顕微鏡と放射光施設を活用した相関構造解析について解説し、東成エレクトロビーム株式会社の西原啓三部長は中小企業が放射光施設を用いる価値とその課題について共有しました。さらに、農業における放射光の利用については東北大学の助教、日髙將文氏が最新の研究を紹介し、JASRIの渡辺剛主幹研究員は有機薄膜デバイスの評価手法としての放射光X線吸収分光・散乱測定について、貴重な情報を提供しました。
このWorkshopを通じて、参加者は放射光に関する分析事例や利用方法を共有し、意見交換が活発に行われました。岡山大学は地域中核機関として、特色ある研究大学を目指しており、今後も放射光を核とした共同研究や技術連携の推進に取り組む意向を示しています。岡山大学による放射光利用に関する取り組みは、文部科学省の地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)の一環であり、政府からも注目されています。地域の皆様にとっても大いに期待される新たな研究の展開が今後の課題となるでしょう。


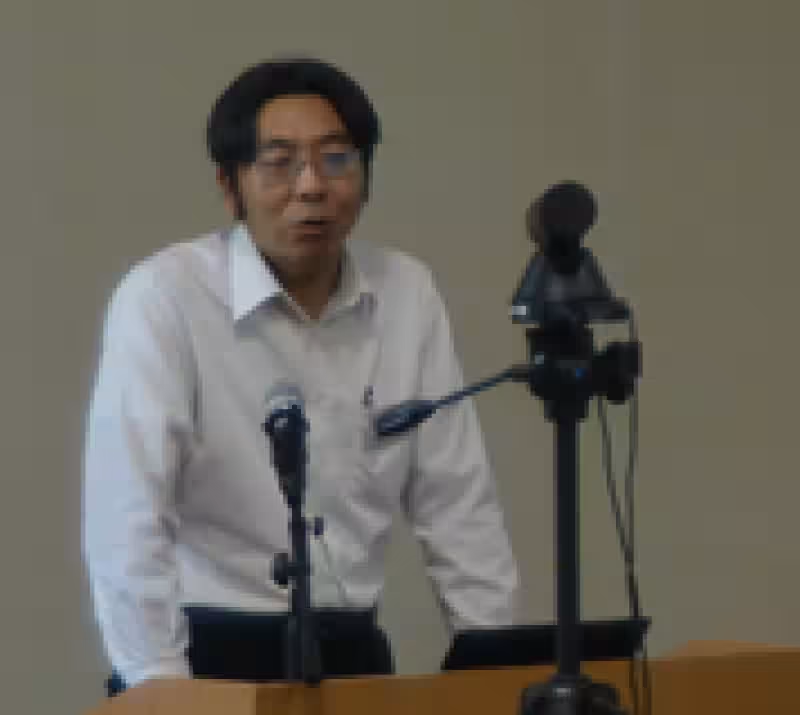











このWorkshopは特に、大型放射光施設「SPring-8」や佐賀県の九州シンクロトロン光研究センター(SAGA-LS)などを初めて利用する研究者や技術者を対象としています。岡山大学は新たに開始する「放射光施設利用サポートサービス」の紹介や、先端分析技術の提供を通し、産学官の連携を強化していくことを目指しています。
イベントの冒頭では、岡山大学の副理事・副学長である佐藤法仁氏が、Workshopの趣旨およびSAGA-LSとの協定について説明しました。続いて、岡山大学総合技術部の堀金和正サイテックコーディネーターが放射光利用分析サポートサービスや、学内の共用機器を簡単に検索できるCFPOUについてのプレゼンテーションを行いました。
第1部では、JASRIの筒井智嗣主幹研究員がSPring-8およびNanoTerasuに関する紹介を行い、SAGA-LSについては廣沢一郎所長が地域産業との連携事例を交えて講演しました。
第2部では、研究者たちが具体的な放射光の利用事例を発表しました。岡山大学の沼本修孝准教授は、クライオ電子顕微鏡と放射光施設を活用した相関構造解析について解説し、東成エレクトロビーム株式会社の西原啓三部長は中小企業が放射光施設を用いる価値とその課題について共有しました。さらに、農業における放射光の利用については東北大学の助教、日髙將文氏が最新の研究を紹介し、JASRIの渡辺剛主幹研究員は有機薄膜デバイスの評価手法としての放射光X線吸収分光・散乱測定について、貴重な情報を提供しました。
このWorkshopを通じて、参加者は放射光に関する分析事例や利用方法を共有し、意見交換が活発に行われました。岡山大学は地域中核機関として、特色ある研究大学を目指しており、今後も放射光を核とした共同研究や技術連携の推進に取り組む意向を示しています。岡山大学による放射光利用に関する取り組みは、文部科学省の地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)の一環であり、政府からも注目されています。地域の皆様にとっても大いに期待される新たな研究の展開が今後の課題となるでしょう。


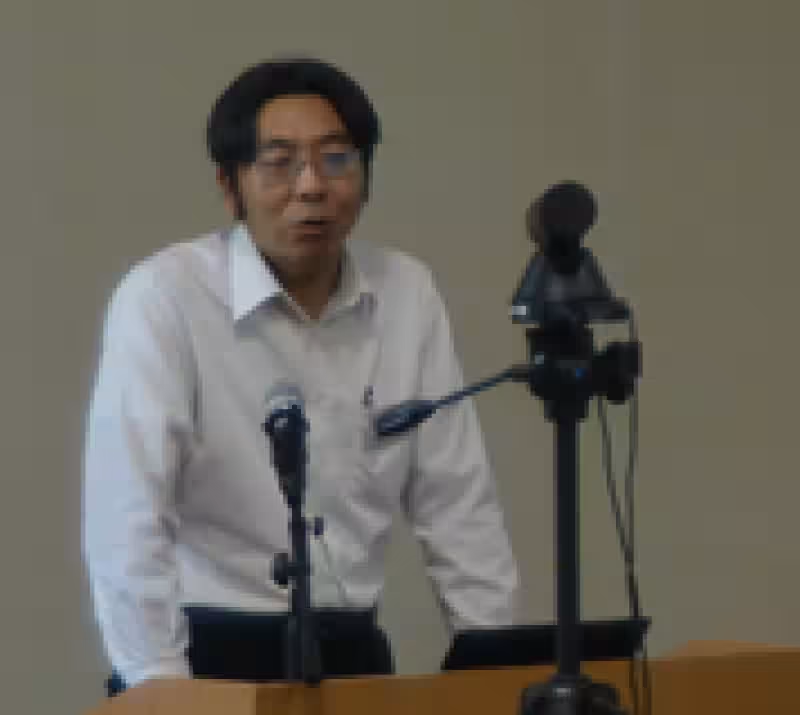











トピックス(その他)

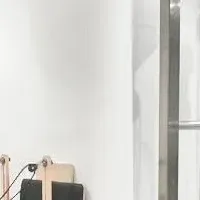
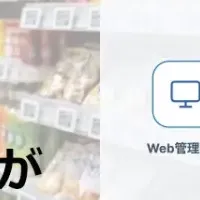
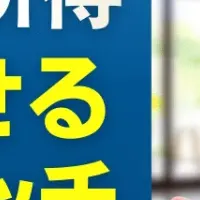



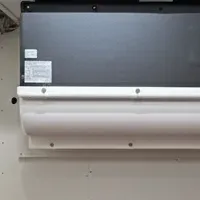

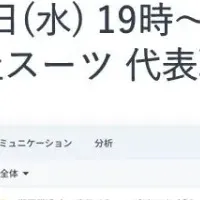
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。