

岡山大学で生成AI活用の最前線を探るイベントが開催されました
岡山大学での生成AI活用共有会
2025年10月31日、岡山大学津島キャンパスにて「OI-Start生成AI活用共有会」が開催されました。この取り組みは、産業界における生成AIの活用事例や課題を共有し、企業の成長を図ることを目的としたものです。
約130名が集まったこのイベントには、岡山県高度情報化推進協議会の後援も受けて、多様な参加者が訪れました。特に目を引いたのは、OI-Start会長である野上保之教授による基調講演です。彼は、最新のAI事情に基づいて、岡山の地で産業界が何を成し遂げられるのか、自らの見解を語りました。「この大AI時代に我々ができることを考え、岡山の個性を活かした革新を推進するべきです」と熱意を持って呼びかけました。
続いて、実際に生成AIを活用している7社からの発表がありました。これらの企業は、AI技術を駆使した実践的な事例を提示し、深層学習モデルによるワッペン画像の自動生成や社内ガイドラインの策定過程など、様々な成功例を紹介しました。また、各社による生成AIサービスのデモンストレーションも行われ、多くの興味を惹きました。
その後、門田暁人教授が「ソフトウェア開発における生成AI活用の現状と展望」というテーマで講演を行い、国内外の事例を比較しながら生成AIの今後の可能性について解説しました。教授は、生成AIを活用することで得られる競争優位性の重要性にも触れ、参加者に新たな刺激を与えました。
イベントの最後には、参加者それぞれからリアルタイムで寄せられた質問を基に意見交換が行われました。議題には「生成AIの新しい使い方」や「著作権問題」、さらには「地方である岡山が競争優位性を持つためにはどうすればよいか」といった多様なトピックが取り上げられ、活発な討論が繰り広げられました。野上教授は、「今日の発表を通じて新たな刺激を受け、岡山ならではの創造性を発揮してほしい」と締めくくりました。
参加した学生からは、「大学院で植物の研究にAIを活用している。今、AIの導入に遅れを取ることが損だと感じており、非常に価値ある勉強の機会」との感想が寄せられました。このようにOI-Startは今後も地域の革新を促進し、製品やサービスの発展に寄与していくことを目指しています。
岡山大学は今後も、地域との連携を深めつつ、生成AIの更なる活用に向けた取り組みを進めていく方針です。産学官の枠を越えた交流が、今後の岡山の産業界にどのような変革をもたらすのか、大いに期待されます。












トピックス(その他)

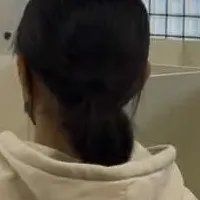
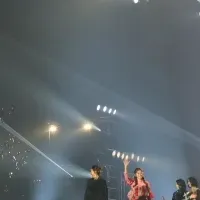
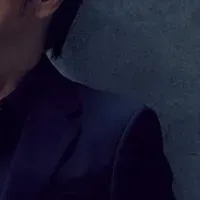
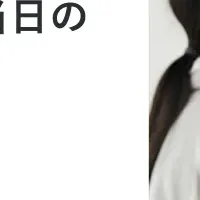
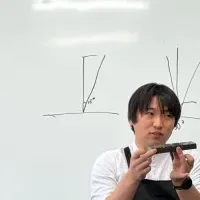
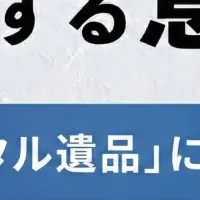



【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。