
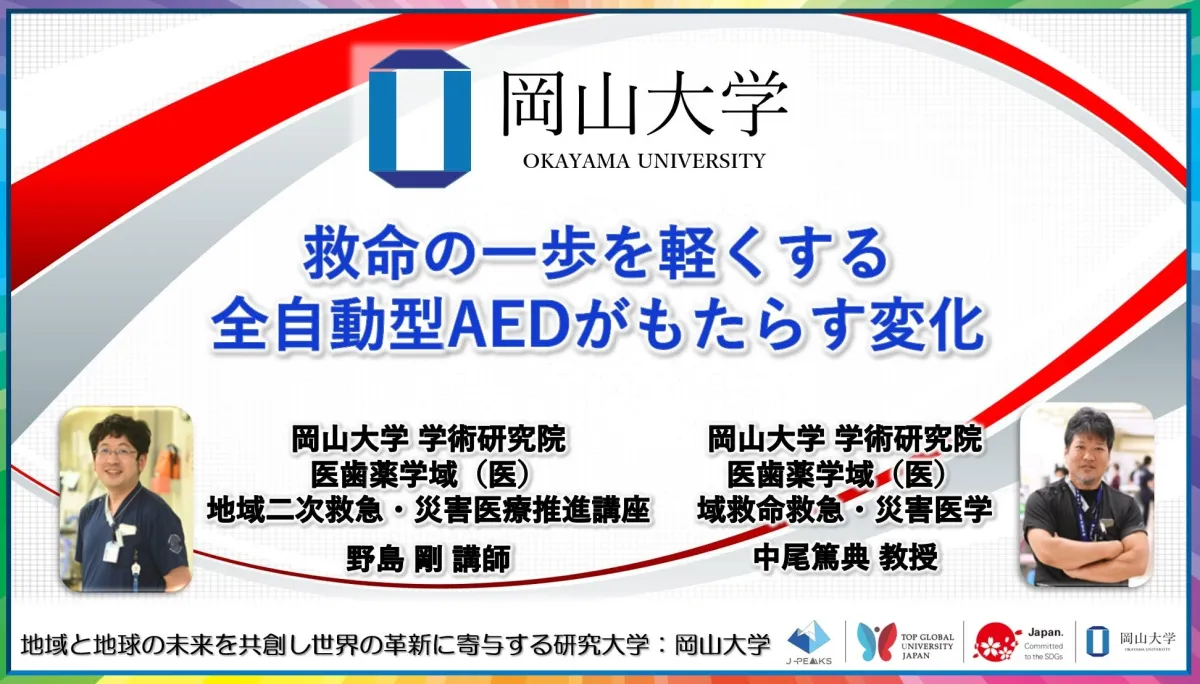
救命活動を変える全自動型AEDの武器となる研究成果
救命活動を変える全自動型AEDの武器となる研究成果
日本国内で、突然の心停止から命を救うためには、一般市民による迅速かつ適切な初期対応が不可欠です。この役割を担うAED(自動体外式除細動器)の使用が、その要となります。AEDには、使用者がボタンを押す「半自動型」と、機械が自動でショックを行う「全自動型」があります。ここ数年、「全自動型」が国内の公共施設で普及し始めていますが、その使用に関する調査が行われたことはありませんでした。
国立大学法人岡山大学が行った研究では、一般市民と医療従事者の両方がAEDを使用する際の心理的負担や操作のしやすさを比較しました。2021年から2022年にかけて、443人がこの実験に参加。結果、一般市民は全自動型AEDの使用を歓迎し、「ボタンを押す」という行為に対するためらいが少なくなる傾向が見られました。その一方で、医療従事者は慣れ親しんだ半自動型を選ぶ傾向が強く、全自動型に対しては「危険」との意見もありました。
この研究の結果は、国際医学誌『Internal Medicine』にて発表されました。研究に参加した岡山大学学術研究院医歯薬学域の野島剛講師と中尾篤典教授は、「全自動型AEDは、心停止時の迅速な対応を促進し、救命率の向上につながる可能性が高い」と述べています。使用が一般市民にとって容易であることから、今後の普及が期待されています。しかし、実際の講習では全自動型AEDの内容がほとんど取り上げられておらず、この課題に対する教育内容の見直しが急務であると強調されています。
AEDの背景
日本では急性心停止のケースは年間約7万件に及ぶとされています。適切な対応が行われれば、救命できる確率は格段に向上します。これまで使用されていた半自動型AEDでは、使用者がボタンを押す心理的なためらいが、救命行動の妨げになることがしばしばありました。その点、全自動型AEDは操作が簡素化されており、特に専門的な知識がない一般市民にとっては、使用へのハードルが下がると考えられています。
ここで全自動型AEDがどのように進化を遂げたかについても触れておきます。2021年から日本に導入され、今では多くの公共施設に設置されていますが、その認知度はまだ十分とは言えません。理想としては、全自動型AEDが日常的に使用され、誰もが利用できる環境が整うことです。そのためには、これからの講習内容の改革や、一般市民への広報活動が重要だとされています。
研究の意義
研究結果は、全自動型AEDが率先して救命に繋がるツールになる可能性を示唆しています。ボタンを押す心理的負担が少ないことで、緊急時に即座に反応できる可能性が高まります。さらに、今回の調査は将来的な教育の根拠ともなり、一般市民によるAEDの使用が次第に増加する見込みです。
現在、岡山大学では全自動型AEDに関する講習の資料やプログラムの改善にも力を入れ、より多くの人々にこの重要な知識と技術を広める活動を推進しています。心停止が発生した際に、誰もが迷うことなくAEDを使える社会を実現するため、今後の取り組みが期待されます。全自動型AEDは救命活動の新たな武器となりつつあるのです。この研究成果を受けて、ぜひ次のステップとして全自動型AEDの使用方法を多くの人と学び合う場を持つことをお勧めします。
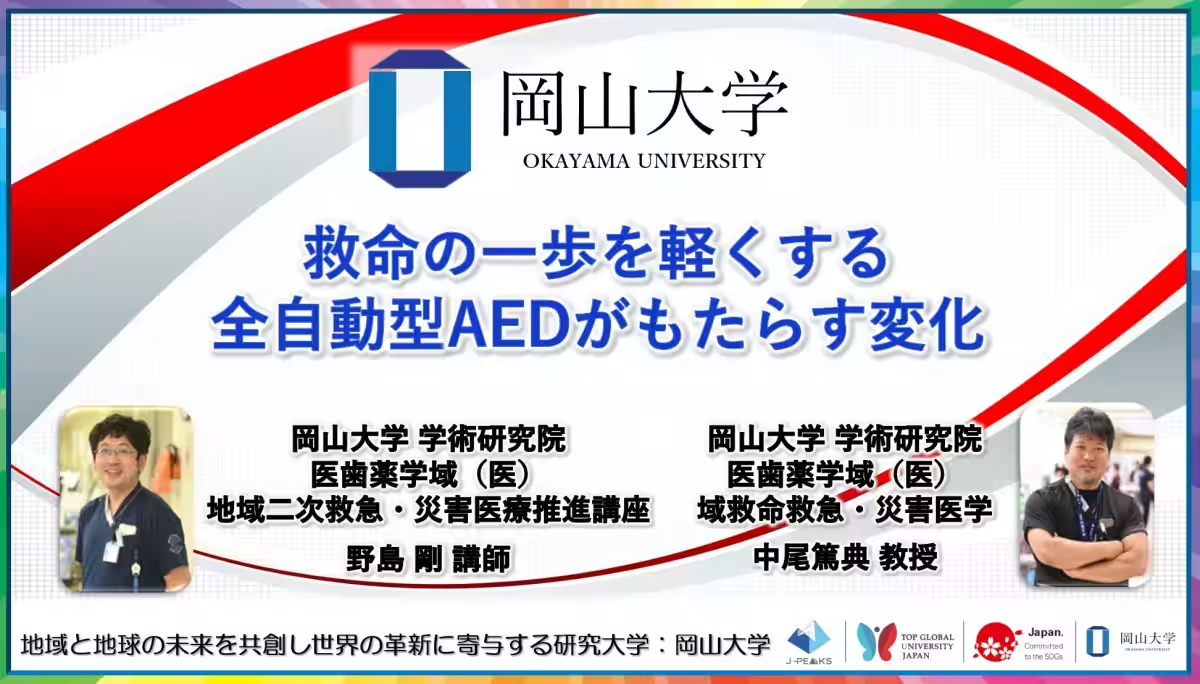







トピックス(その他)




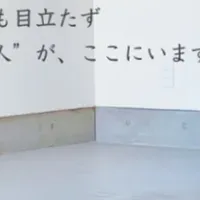

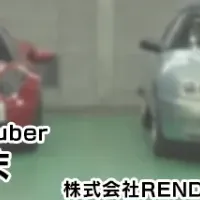


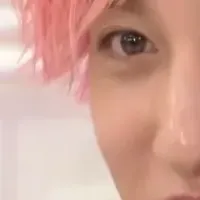
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。