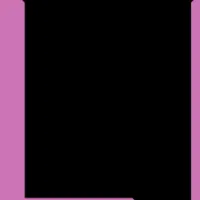
学校給食で始める地場産物活用ガイドブックのご紹介
学校給食での地場産物活用を促進するガイドブック
文部科学省は、食育の一環として学校給食に地場産物を活用するための新しいガイドブックを発表しました。この取組みは、農林水産省と協力して進められており、地域の特産品を取り入れることで、子どもたちの健康を促進するとともに、地元経済の活性化を目指しています。
ガイドブックの主な内容
このガイドブックでは、地場産物の活用を始める際のスモールステップに焦点を当て、具体的な手法や成功事例を紹介しています。特に、地域の農産物や加工品を学校給食に取り入れる際の注意点や工夫が詳細に説明されており、実際に各学校がどういった方法で地場産物をメニューに組み込んでいるかの事例も多く掲載されています。
スモールステップの重要性
地場産物の活用には、一度にすべてを取り入れるのではなく、小さなステップで進めることが推奨されています。例えば、まずは特定の季節に採れる地元の野菜から献立に追加し、徐々に品目を増やしていく方法です。このアプローチによって、教職員や生徒が地場産物に対する理解を深めることができ、地元愛を育むきっかけともなります。
成功事例
ガイドブックには多くの成功事例が掲載されています。例えば、ある地域の小学校では、地元の米を使用した給食を提供し、子どもたちからは「おいしい!」との声が上がっています。また、地域の農家との連携を深めることで、食育活動や交流イベントも実施されています。これにより、子どもたちは食材の旬や生産者の思いを知ることができ、食への興味を高めています。
地元との連携が鍵
地場産物を給食に活用するためには、地域の生産者との協力が不可欠です。学校と農家が連携することによって、食材の新鮮さを保ちながら、地域経済を支える仕組みが形成されます。このようにして、給食の質を向上させると同時に、地域の活性化も図ることができるのです。
環境への配慮
また、ガイドブックでは環境への配慮も強調されています。地場産物を使用することで、輸送にかかるコストやCO2排出を削減し、持続可能な社会の実現に寄与することが期待されています。子どもたちも、食育を通じて環境問題に目を向けるきっかけとなるでしょう。
まとめ
学校給食における地場産物の活用は、子どもたちの健康を守るだけでなく、地元経済を活性化し、環境問題にも配慮する取り組みです。文部科学省の提供するこのガイドブックを参考にしながら、各地で地場産物の利用を進めていくことが大切です。地域と学校が協力し、子どもたちにとってより良い食環境を整えるための一歩を踏み出しましょう。
トピックス(その他)
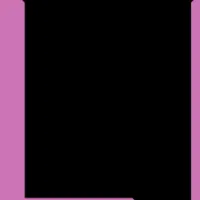

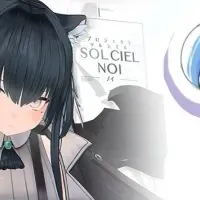
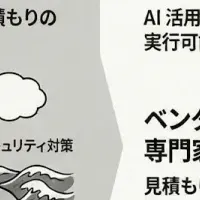

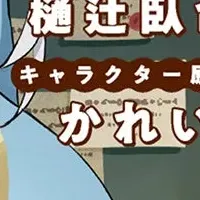
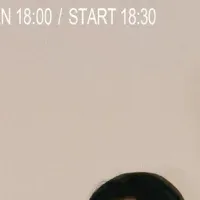
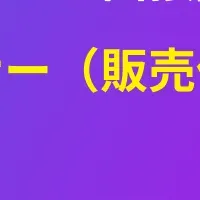
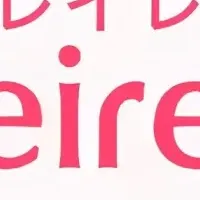

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。